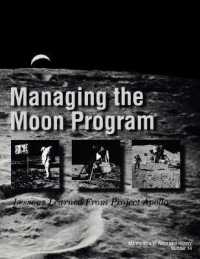- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
内容説明
太夫から、神職へ―。身分は変われど神楽は続く。広島県庄原市に伝わる比婆荒神神楽は、なぜ350年以上も継続されてきたのか。その「伝承の原動力」とは何か。備後一宮から認証を受けた神仏混淆の「太夫」は、やがて吉田神道配下の「社人」となり、明治には国家神道下の「神官」、現在も神社本庁包括下の「神職」として宗教活動を継続してきた。身分や社会の変化に応じて神楽をブランディングする「人」の創造性に注目した、画期的な神楽の社会史。
目次
第一部 神楽を伝承する太夫の社会的立場と宗教活動(中近世における社人の組織と階層;近世における社人の宗教活動とその権利;明治初期の宗教政策と備北地方の神職の動向;備北地方における太夫の現在)
第二部 太夫が執行する儀礼の変遷(朽木家文書に見る太夫の宗教活動の変遷;梓弓による口寄せ儀礼―「六道十三佛之カン文」の位置づけをめぐって;広島県庄原市西城町(旧奴可郡)の神弓祭)
第三部 比婆荒神神楽の近現代史(広島県の神楽が経験した近代―政治・民俗学・国家神道;神楽と国譲り神話―近代における芸能の創造;比婆荒神神楽の近代―新たな執行体制の成立と稼ぎとしての神楽;近代史における名の変容と神楽の継承;比婆荒神神楽の現代的展開)
著者等紹介
鈴木昂太[スズキコウタ]
1988年静岡県生まれ。専門は、民俗学・芸能史研究。博士(文学)(2020年総合研究大学院大学)。東京文化財研究所無形文化遺産部研究補佐員を経て、国立民俗学博物館人類文明誌研究部助教(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。