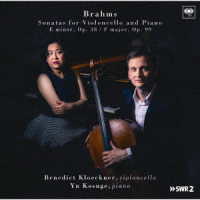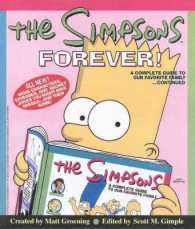内容説明
室町時代を生きた一休宗純(1394‐1481)の実証研究とその没後に生まれた一休“像”の変遷とをつなぎ、戦後日本における禅文化の追究へ―前田利鎌・芳賀幸四郎・市川白弦・柳田聖山ら「禅」を修めた代表的知識人が、一休を語ろうとしながら、語る側からみた像が提示されてきたその変遷を、戦後思想史の一断面として捉え、“語り”のイメージリーディングの新たな地平を探る。
目次
序論 一休の“像”は如何に形成されてきたか―室町期から戦後日本へ
第1章 一休像の近代的「発見」―前田利鎌の「禅」を手がかりに
第2章 戦後日本における中世禅文化論と一休の像―芳賀幸四郎を中心に
第3章 市川白弦の一休像―「即」の論理の批判的継承として
第4章 二十世紀の「禅学」と一休像―柳田聖山の視座を再考する
補論 「瞎驢辺滅却」をめぐって―一休と臨済禅への研究覚書
終章 禅門と俗世と一休の像―論のむすびとひらき
著者等紹介
飯島孝良[イイジマタカヨシ]
1984年、東京都生まれ。上智大学外国語学部卒業。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。現在、花園大学国際禅学研究所専任講師。専攻は禅文化史・日本宗教思想史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
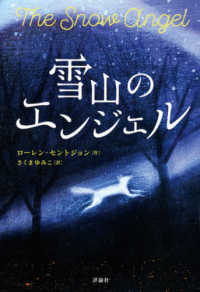
- 和書
- 雪山のエンジェル