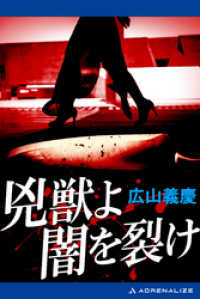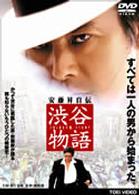出版社内容情報
芭蕉は現代にどのように生きているのか、生き残っているのか。今日の「俳句」と直接結びつく高浜虚子を起点として"芭蕉受容"という視点から昭和の俳人たちをとらえ直す。
●目次●
はじめに
Ⅰ 虚子から秋桜子へ
一 虚子の芭蕉観―俳句の「伝統」をどのようにみるか―
一、「伝統」派と「反伝統」派
二、虚子の俳句観
三、虚子の伝統観
四、俳句の伝統観、諸説の検証
二 虚子の「芭蕉句三種類」説をめぐって―風体としての「かるみ」論―
一、虚子の「かるみ」認識
二、「主観的写生」から「客観的写生」へ―虚子と芭蕉―
三、「心の色」としての「かるみ」の論―山本健吉と森澄雄―
四、「姿」と「情」の論からみた「かるみ」―「かるみ」は風体を示す用語か―
三 「景」を写して「情」を詠む―秋桜子の方法と波郷―
Ⅱ 俳句の近代―波郷を核として―
一 芭蕉と近代俳人たち―楸邨・波郷・誓子・草田男―
はじめに
一、加藤楸邨と芭蕉
二、石田波郷と芭蕉
三、山口誓子と芭蕉
四、中村草田男と芭蕉
二 波郷と俳句文体
一、喚体の呼格
二、「切れ」の効用
三、文法という規範
四、省略の叙法
五、韻律
三 波郷の韻文精神
一、俳句の魂
二、型としての韻文
四 波郷の散文精神―『江東歳時記』とわたし―
Ⅲ 俳句私小説論―俳句表現構造論へ向けて―
一 俳句は私小説なり―波郷のなかの葛西善蔵―
二 私小説性からの脱出―藤田湘子の波郷観―
三 俳句私小説論のゆくえ
一、志賀直哉の「私」と波郷の「私」
二、横光利一の「四人称」設定説と波郷の「私」脱出
Ⅳ 俳句の現代
一 芭蕉と現代俳人たち―龍太・澄雄・兜太
はじめに
一、飯田龍太と芭蕉
二、森澄雄と芭蕉
三、金子兜太と芭蕉
二 情感の頂点で発止と打出される句―森澄雄の波郷論―
三 "型"にはめる、"型"にはまる―金子兜太の波郷論―
四 俳句は叙情詩なり―能村登四郎の世界―
五 「多行形式俳句」という挑戦―高柳重信論―
六 「俳句即生活」説と「心象造型」論―高柳重信の波郷観―
あとがき
初出一覧
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
るい
石川さん