内容説明
中国・南宋時代に登場した朱子学が、普遍思想として朝鮮・日本に広がり、各地域の固有性と融合していった経緯を解明し、東アジア文化の共通性と特殊性を検証する。さらに、近代において明治日本の「教育勅語」等に朱子学用語が横領されてきた事実を見据えたうえで、現代社会における民主主義・基本的人権の価値観と朱子学との親和性を描き出す。
目次
第1章 日本朱子学と神道(北畠親房の「神」概念;山崎闇斎の「神」概念;「神」の垂加と「心」)
第2章 日本と朝鮮における朱子学の受容(北畠親房と李檣;山崎闇斎の「敬」概念;李退渓の「敬」概念)
第3章 東アジアの朱子学とその現代的意義(朱子の「格物・致知」と李退渓の「敬」;朱子学の現代的意義;朱子学と自由主義思想)
著者等紹介
下川玲子[シモカワリョウコ]
1965年、名古屋市生まれ。筑波大学大学院哲学・思想研究科倫理学専攻博士課程修了。博士(文学)。日本学術振興会特別研究員を経て、愛知学院大学文学部日本文化学科准教授。専攻日本思想史・東アジア思想史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きさらぎ
6
朱子の思想が、朝鮮、日本にどのように受容されたかを、朱熹、李退渓、北畠親房、山崎闇斎の思想を中心に論じる。朱熹と退渓は「理」「善」を希求し、よりよき生を問う点は同じだが、朱熹が格物致知を重視し、外の理を極めることで心を正しくしようとしたのに対し、退渓は心を正しくする「敬」を重視し、内面を正すことで外世界がうまく治まるとした。それに対し、日本の儒学者である親房と闇斎は「心を正しくする」「敬」が神への「誠」と結びつき、それゆえに世界に対して受容的で、朱熹や退渓のごとく改革の思想とはなり得なかった、と説く。2018/12/04
-
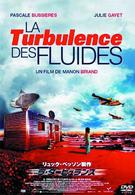
- DVD
- ラ・タービュランス






