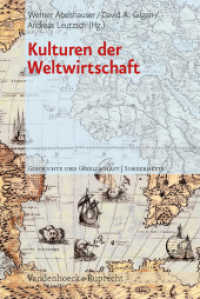内容説明
世阿弥や同時代の能役者の環境という視点から読み解いた、斬新な大成期の能の実態。彼らの制作になる能がいかにパトロンである室町将軍の意を体したものであるかを、作品の総合的かつ統一的な把握から析出し、室町時代研究にも新たな視点を提示する。
目次
序章 世阿弥がいた場所概観(世阿弥がいた場所―義持以前の御用役者の環境;世阿弥という名前―能役者の阿弥号の意味と由来)
第1章 義満時代の脇能と世阿弥(能における対権力者意識についての覚書―“金札”“養老”“弓八幡”“難波”などの「君は舟臣は水」をめぐって;“金札”の作意と成立の背景―原形の復元と作意の把握を通じて永徳元年の「花の御所」落成との関連におよぶ;“弓八幡”成立の時と場―『申楽談儀』の「当御代」と応永初年の義満をとりまく状況をめぐって;“養老”の典拠と成立の背景―『養老寺縁起』と明徳四年の義満の養老瀧見物をめぐって)
第2章 義満時代の能と能役者(足利義満の禅的環境と観阿弥の能―観阿弥作の“自然居士”と“卒都婆小町”をめぐって;井阿弥をめぐる二、三の問題―その素性と“丹後物狂”などからみた御用役者としての環境;“小林”成立の背景―足利義満の明徳の乱処理策との関連をめぐって;“合浦”の成立と南北朝合一―明徳三年の神璽(勾玉)の京都帰還をめぐって
“笠間の能”をめぐる諸問題―大成期における将軍周辺の能という視点から)
第3章 義持義教時代の能と世阿弥(足利義持の治世と世阿弥―義持と後小松父子との関係をめぐって;“難波”の作意と成立の背景―応永十五年の将軍義持の家督継承前後の状況をめぐって;“白楽天”と応永の外寇―久米邦武と高野辰之の所説を検証する)
終章 世阿弥がいた場所拾遺(鎌倉末期の田楽界と相模入道高時―東大寺文書の田楽関係資料をめぐって;今熊野猿楽の実現―義満台臨の背景をめぐって)
著者等紹介
天野文雄[アマノフミオ]
昭和21年、東京都生まれ。大阪大学大学院文学研究科教授(芸術学講座)。文学博士。専門は能楽史。國學院大学大学院文学研究科博士課程修了。國學院久我山高校、上田女子短期大学、大阪大学文学部助教授、教授(芸能史・演劇学講座)を経て、平成11年から現職。著書に、『翁猿楽研究』(平成7年、和泉書院。第18回観世寿夫記念法政大学能楽賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。