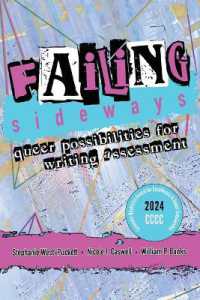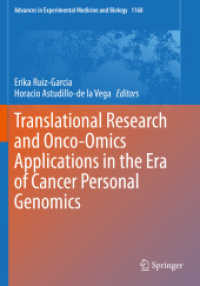内容説明
本書は欧州から現れたまったく新しい経営戦略論研究「実践としての戦略」の全容を示すものである。「何が組織を戦略的にさせるのか」「戦略的であることの弊害は何か」、それぞれの組織で起きるひとつの組織的現象としてもう一度経営戦略を捉え直してみたとき、これまでとはまったく違う経営戦略の姿が見えてくる。
目次
第1部 (実践としての戦略パースペクティブへの招待;実践的な理論;戦略の実践を研究する)
第2部 事例研究(構造化への契機としての技術―CTスキャナーがもたらす放射線科の社会構造への影響;急速に変化する環境における迅速な戦略的意思決定;合理性の再考―組織が取り組む調査や研究に隠された目的;戦略転換の始動におけるセンスメーキングとセンスギビング;教育としての事業計画―変化する制度フィールドにおける言語とコントロール;生きられた経験としての戦略化と戦略の方向性を決定しようとする戦略担当者たちの日常の取組み;組織変革とミドルマネジャーのセンスメーキング;戦略クラフティングにおけるメタファーから実践まで)
第3部 (総括)
著者等紹介
ジョンソン,ゲリー[ジョンソン,ゲリー][Johnson,Gerry]
ランカスター大学経営大学院、Sir Roland Smith教授(戦略経営論)。ロンドン大学ユニバーシティカレッジで文学士号(社会人類学・自然人類学)を取得後、アストン大学でPhDを取得。企業のマーケティング担当役員や経営コンサルタント、またアストン大学、マンチェスター大学ビジネススクール、クランフィールド大学マネジメントスクール、ストラスクライド経営大学院での教職を経て、現職。また、UKマネジメントリサーチ研究所(AIM)の上級研究員を兼職
ラングレィ,アン[ラングレィ,アン][Langley,Ann]
モントリオール理工科大学教授(戦略経営、リサーチ・メソッド)。イギリス(オックスフォードとランカスターのそれぞれ)で学士と修士を取得し、民間企業および公的機関の双方においてアナリストとして数年勤務した後、1987年にモントリオール理工科大学でPhDを取得。2003年から2006年までモントリオール理工科大学で理学修士(MSc)ならびにPhD課程のディレクター、1985年から2000年までケベック大学モントリオール校で教授(戦略論)を歴任し、現職
メリン,レイフ[メリン,レイフ][Melin,Leif]
ヨンショーピング大学国際ビジネススクール(JIBS)教授(戦略論、組織論)。リンショーピング大学でPhDを取得後、のちに、同大学で戦略経営教授となる。また、JIBSのCeFEO(同族企業ならびにオーナーシップに関する研究センター)を創設し、さらにJIBSで学部長と最高責任者を務めている。組織における戦略化と組織化の分野、とりわけ戦略転換活動におけるオーナーシップと戦略的リーダーシップの役割、そして持続的成長企業における戦略的実践に関心を持つ
ウィッティントン,リチャード[ウィッティントン,リチャード][Whittington,Richard]
サイード・ビジネススクール、Millmanフェロー、ニューカレッジ、オックスフォード大学教授(戦略経営論)。ウォーリック大学、そしてパリ工科大学、トゥールーズ大学、ハーバード・ビジネススクールの客員研究員を歴任。最近の研究は、戦略的課題のマネジメントや戦略化の学習、ひとつの実践としての戦略の歴史的進化と拡散に関するプロジェクトと共に、実践としての経営戦略(SAP)に焦点を向けている
高橋正泰[タカハシマサヤス]
1951年新潟生まれ。早稲田大学商学部卒業、早稲田大学大学院商学研究科修士課程修了(商学修士)、明治大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得退学、経営学博士(明治大学)。1982年小樽商科大学短期大学部専任講師に就任。その後、小樽商科大学商学部教授を経て、明治大学経営学部教授。明治大学大学院経営学研究科科長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。