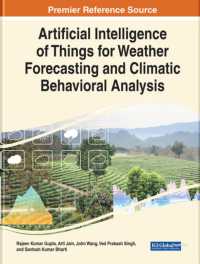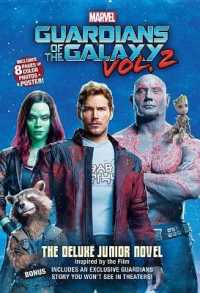内容説明
河川に沿って分布を拡大し、その旺盛な成長で在来種を被圧するニセアカシア。日本に導入された後、荒廃地緑化用に利用された歴史を持ち、現在でも養蜂の蜜源植物として重要な位置を占めるこの有用な外来生物を、これからどう扱うべきなのか?生態学的知見に基づき、現実的な管理・利用の途を探る。
目次
第1部 ニセアカシアの利用の歴史(ニセアカシアによる治山・砂防緑化;「アカシア」香る町―小坂鉱山煙害地における緑化;蜜源植物としてのニセアカシア;養蜂業におけるニセアカシア林の利用の実態;ニセアカシアの木材利用について―長野県から発信するこだわりのフローリング)
第2部 ニセアカシアの生態(可川敷におけるニセアカシアの分布拡大に果たす種子の役割;ニセアカシアの種子発芽特性;増水による撹乱と外来種ニセアカシアの発芽定着―荒川での研究事例;海岸マツ林に広がるニセアカシア―秋田県夕日の松原での研究例より;ニセアカシアの光合成能力;ニセアカシアの萌芽力;マイクロサテライトマーカーが明かすニセアカシアの繁殖特性;ニセアカシアの侵入が渓流生態系に与える影響―腐食連鎖の視点から;ニセアカシア人工林に出現した植物の多様性;ニセアカシアのアレロパシー)
第3部 ニセアカシアの管理(広域を対象としたニセアカシア林の分布把握と分布要因;多摩川におけるニセアカシア林の構造と防除対策;渓畔域におけるニセアカシアの除去;ニセアカシアの除去;今、ニセアカシア林をどのように扱うか?)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
竜王五代の人
5
地元でも海岸近くで見かけるニセアカシア(そのあたりの歴史や現在の施策がわかる一章があるのがうれしい)の、特徴や何が問題なのかが分かる一冊。緑化以外にも、養蜂の強い支え(透明なハチミツ!)になっているのが分かった。繁殖力はあるがアレロパシーで他の植物を排除し、さらに三十年くらいで倒れて荒れる(そうやって遷移を留める作戦?)、そのあたりが問題なんだな。勉強になった。2025/06/16
ちちもん
1
要注意外来生物としてのニセアカシアについて様々な面から論じている。主旨とは異なる部分ではあるが,ミツバチの生態に興味を持った。他の本を読んでみたい。14章は駆除すべき外来種との色眼鏡をはずした見方にはっとした。しかし15章のアレロパシーについて読むと14章では単に多様性についてのみ考えており,15章で述べられているような生育できる種が選択されてしまう点については考えられていない不十分さを感じた。地域固有の生態系や固有種を保護する意味ではこの点は無視できないと思う。7章は文章がおもしろおかしく読みやすかった2012/03/12
リラ
0
読んだ読んだ!また読みたい。2009/10/05