内容説明
看板書、錠前直し、便り屋、井戸掘り、刷毛師、灰買い、冷水売り、歯磨売り、早桶屋、宝舟売り…江戸時代の「食と住」に関わる仕事250種をすべて絵で見せます。
目次
第1章 商い―商売の形態と運輸(主人も奉公人も、一つ屋根の下で寝起きして商いに励む;商店;小商い;金融;運輸)
第2章 住まい―家の普請と暮らしの道具(暮らしの基本、住まい造りを支えるのは職人の仕事;普請;建具;調度;台所;器;灯り)
第3章 味わい―日々のご飯と嗜好品(日々の飯から特別な日の宴の膳まで、和食の基礎は江戸時代から;朝餉夕餉;嗜好品;料理)
第4章 養生―医療と薬(病には、医者か薬か呪いか。求める者に救いを施す江戸の医療;医療;薬)
第5章 祈り―神と仏に祈る(江戸時代は、生きていくのに必要だった神と仏の世界;仏;神)
著者等紹介
飯田泰子[イイダヤスコ]
東京生まれ、編集者。企画集団エド代表。江戸時代の庶民の暮らしにかかわる書籍の企画編集に携わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tokkun1002
9
2020年。こうして眺めると、今現在も変わってない事が如何に多い事かと驚く。過程から学ぶ事があるに違いない。情報を残す事。維持してくれた人々、分かり易くまとめてくれた飯田先生に感謝。2020/03/14
さぁとなつ
8
江戸の生業図鑑。食と住に関わる仕事を中心に250余りの職業がすべて絵で見せる趣向で載っている。江戸の市井の人々の暮らしが活気とともに伝わってくる。 時代小説を読むときに「?」と思っていた職業が知れたり、そこから芋づる式に江戸の暮らしが見えてきたりする。知らなかった職業もたくさんあった(もちろん死語もあり) 何より、古典落語が分かるようになり、クスリと笑えるようになる。2022/05/06
yakinori
5
江戸の食と住まいに関わる職業を当時の文献に描かれた図を挿入しながら紹介。ほとんど文章という文章はなく、まさに図鑑といった趣。例えば、ひとつの製品がユーザーの手元に届くまでには材料調達業、製造業(工程それぞれに職人がいる)、販売業があり、それが製品それぞれにあるのだから実に様々な職業があるものである。2021/08/29
じじちょん
5
江戸時代に描かれた図が今でもこんなに残っていることに驚く。現代みたいに、一つのお店でたくさんのサービスを取り扱っているわけでなく、道具それぞれ直す職人がいたり、物売りにしても、何か一つのモノを専門に扱う。何でも再利用する時代だと再認識させられる。2021/01/16
林芳
2
江戸時代の職業。実際にこれらを見ることが出来たら面白いだろうな〜と思う。日本人ってこんななの?って感じで、視野が開け、殻を破ることが出来そう。2025/02/09
-
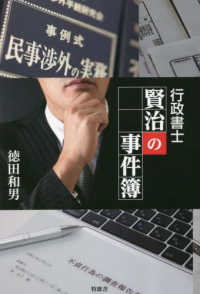
- 和書
- 行政書士賢治の事件簿






