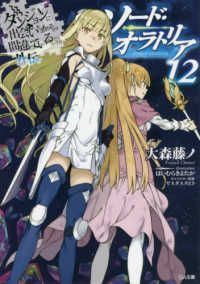内容説明
本書の特徴は、まず、フェアネスへのアプローチの斬新さにあると言えるだろう。それは具体的には、スポーツからそれを取り巻く社会全般へ至る広範なパースペクティヴの中でフェアネスを語るという手法を採ったところにある。競争性とその弊害を持つに至った今日のスポーツの状況が、本書で「肘鉄社会」と名付けられた今日の社会状況と決して無縁ではないことを示しながら、それらに通底するモラルの問題を浮かび上がらせている。また本書は、清潔さ、純粋さをスポーツの理想に掲げ、ともすれば現実から目を逸らしがちな他のスポーツ論とは一線を画している。「フェア」に対する今日的な通念を「フェアなファウル」という言葉で表現してみたり、フェアプレイのアピールやキャンペーンでさえ、それを「二枚舌」だとしてそこに潜む欺瞞や取り繕いを鋭く指摘したりするなど、現実を直視する姿勢が随所にみられる。フェアプレイを声高に叫んだり、ドーピング問題などで個人に責任を帰したりするだけではもはや不十分であることを主張し、新たに制度責任という責任の類型を提示する。
目次
第1章 フェアプレイに関わる論争
第2章 定義:フェアネスとはなにか?
第3章 フェアプレイの歴史の概観
第4章 システムによって制限されたフェアネスの変化
第5章 フェアプレイ・キャンペーンの吟味
第6章 経済におけるフェアネスの問題
第7章 フェアネス奨励のチャンス
著者等紹介
ピルツ,グンター・A.[Pilz,Gunter A.]
1944年生まれ、’81年にハノーバー大学にて博士号を取得。その時の学位請求論文が、“Wandlungen der Gewalt im Sport”という題名で’82年にドイツ・アーレンスブルクのCzwalina社から刊行されている。現在はスポーツ社会学者として、暴力論を中心にハノーバー大学のスポーツ科学部にて研究活動を展開している
レンク,ハンス[Lenk,Hans]
1935年ベルリン生まれ。’61年キール大学にて哲学博士、’66年哲学教授資格、’69年社会学教授資格をそれぞれ取得し、現在はカールスルーエ大学の哲学正教授である。この間、客員教授としてイリノイ大学(’73年)、マサチューセッツ大学(’76年)、サン・パウロ大学、ベロ・オリゾンテ大学(いずれも’79~81年)、ザルツブルク大学、グラーツ大学(いずれも’85年)、フォートワース大学(’87年)などに招かれ、現在もストラスブール大学の客員教授を務めている。また、カールスルーエ大学人文・社会学部長、国際スポーツ哲学会長、ヨーロッパ法哲学アカデミー副会長、ドイツ哲学会長、ドイツオリンピック委員、国際オリンピック・アカデミー名誉会員などを歴任している。研究者としての業績としては、カール・ディーム科学賞(’62年)、ジーフェルト賞(’73年)、ノエル・ベーカー賞(’78年)などの受賞歴があり、他方、競技者としては’60年のローマ・オリッピックのエイトで優勝している。さらにコーチとして、’66年の世界選手権でドイツのエイトを優勝に導いている。専門の哲学の分野を中心に多数の編著作を著しているが、その中でも主なスポーツ関係の編著書は「Werte-Ziele-Wirklichkeit der modernen Olympischen Spiele」(’64年)ほか多数
窪田奈希左[クボタナギサ]
1966年大阪府出身。’96年筑波大学大学院博士課程体育科学研究科単位取得満期退学。現在、上越教育大学学校教育学部保健体育講座助手
深沢浩洋[フカサワコウヨウ]
1966年秋田県出身。’98年筑波大学大学院博士課程体育科学研究科修了。現在、電気通信大学人間コミュニケーション学科講師。博士(体育科学)
笛木寛[フエキユタカ]
1968年新潟県出身。現在、筑波大学大学院博士課程体育科学研究科在学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。