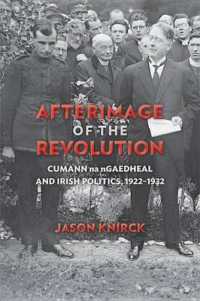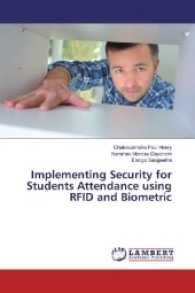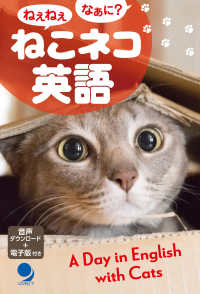出版社内容情報
経済学の第一人者が、日銀の金融緩和政策に警鐘を鳴らす、緊急出版。
このところ円安が止まらない。円の価値は、今年春から数カ月で25円程度も下落した。これは、アメリカをはじめ世界が金利を上げる政策に転換しているのに、日本だけが低金利を維持しているためだ。日本は、金融緩和政策でインフレを起こし、経済を活性化するというのが、アベノミクス以来の方針だった。しかし、円安で物価は上昇しても、労働者の賃金は上がらない。このままでは生活がひっ迫する。それ以上に問題なのは、日銀が投機筋から狙われていることだ。日銀はいつか政策を転換し、金利を上げざるを得ない。そうなると、国債の価格は下落する。それを見越して、世界中の投機筋が国債の先物を大量に売りさばいているのだ。日銀は国債を買い支えて価格の下落に対抗しているが、それにも限界がある。日銀は、本来ならば金利を上げる政策に転換すべきなのだが、それを行うと、大量に購入した国債の価格が下落し、債務超過に陥る。そのために、日銀は動きが取れなくなっているのだ。しかし、日銀が債務超過に陥っても、日常業務に直接の支障が出るわけではない。円安がこのまま進むと、円を売ってドルで運用する「円キャリー取引」が激しさを増し、日本の円資産が国外へ流出することになる。これは国力の低下につながるから、絶対に阻止しなければならない。
日銀は、いますぐ低金利政策を転換し、長期金利上昇を認めるべきである。
内容説明
岸田文雄内閣のマクロ経済政策は、基本的な点で深刻な矛盾を含むものになっている。なぜなら、一方で物価高騰が問題だとしながら、他方で金融緩和を続けることによって、円安を放置しているからだ。もちろん、これでは賃金は上がらない。経済のもっとも重要な問題に関して矛盾した政策が続けられているのは、日本の政策決定体制が深刻な機能不全に陥っていることを示すものだ。そして、日本の国際的地位は、確実に低下を続けている。本書の目的は、いま日本が直面する経済問題の本質が何であるかを明らかにすることである。それを踏まえて、日本が向かうべき方向を示したい。
目次
第1章 円安で物価高騰
第2章 円安で日本が衰退した
第3章 日銀と投機筋の壮絶な戦い
第4章 金融政策の転換が必要なのに日銀が動けない理由
第5章 補助金漬け体質になる日本の製造業
第6章 デジタル化はどこに向かうか?
第7章 新しい日本をつくるのは高等教育の充実
著者等紹介
野口悠紀雄[ノグチユキオ]
1940年、東京生まれ。1963年、東京大学工学部卒業。1964年、大蔵省入省。1972年、エール大学Ph.D.(経済学博士号)を取得。一橋大学教授、東京大学教授(先端経済工学研究センター長)、スタンフォード大学客員教授、早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授などを歴任。一橋大学名誉教授。専門は日本経済論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
templecity
ピンガペンギン
uD
訪問者
Humbaba