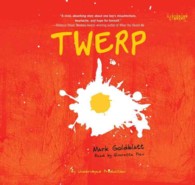内容説明
日本初の女装家はヤマトタケルだった!?日本史をオカマ視点で抉りとる、知らなきゃわからない日本のこと!
目次
第1章 神話の時代の男色―皇紀二六八一年の事始め
第2章 平安仏教の男色―なぜ男色が市民権を得たのか?
第3章 院政期の男色―男色が歴史を動かす
第4章 鎌倉時代の男色―男色文化の鎌倉への伝播
第5章 室町時代の男色―庶民への男色文化の降下
第6章 戦国時代の男色―宣教師は男色をどう見たのか?
第7章 江戸時代の男色―なぜ幕府や藩は衆道を禁止したのか?
第8章 明治大正の男色―なぜ男色はヘンタイとなったのか?
第9章 LGBTが市民権を得るまで―そして無知と軋轢
著者等紹介
山口志穂[ヤマグチシホ]
1975年、広島市生まれ。吉備国際大学卒業後、一般企業、ニューハーフクラブ等に勤務。3歳頃から、自らの性別に違和感を覚える。自らの心の性別を公表できないことに悩み、LGBT問題の解決を図るために当初はLGBT活動家に賛同。しかし友人が活動家からの甘えで鬱になったことで、LGBT活動家に疑問を感じる。またLGBT活動家の主張が日本の歴史に即してないことから、オカマが日本の歴史の中でどう位置づけられていたのかを調べ始める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
南北
44
オカマという切り口で日本史を語った本。江戸時代までは時代や地域によって異なるものの男色が当たり前で(全くなかった場合もある)、男色を前提とした「浄愛」と「不浄愛」がわからないと院政期や戦国時代の人間関係がほんとうに理解できないのだとわかる。明治以降は西洋文明の影響で変化してくるが、現代でも無理解な言動があるのはこうした過去の経緯を知らないのが原因だと思う。冒頭の「心と体の生が食い違っているか」「恋愛対象は同性か」「男装か女装か」のキーワードはわかりやすいと思った。2021/09/24
かやは
11
昨今の大河ドラマでは同性愛的な側面も表現されているが、事実に照らし合わせてみるとまだまだ隠されているんだな、と感じた。実際の男色文化で語られる日本史をもっと見てみたい。近代化される以前の性の価値観は面白かった。2022/11/25
Y田
11
このテーマはほぼ全く事前知識が無かったので結構驚いた。思った以上に男色というのは一般的だったのかと。というか、今の「LGBT」「同性愛」と感覚が違うのかなとも感じた。例えば本書によると、足利将軍家はほぼほぼ男色家だった記録があるとの事だが、今の感覚で「確率的にそんな事あるの?」って最初思った。今のところの自分の解釈だけど、男色は一つの文化たしなみ、フツーの嗜好の一つっていう感じだったのかなと。同性愛=異常という感覚は最近100年程度の話だという。このテーマも大変興味深い。また類書も読んでいきたい^_^2022/04/12
とも
7
神話の時代から戦後までの日本史をオカマの目線で紐解く本とのこと。最初にLGBTに触れてたので満遍なく扱うのかと思いきやほぼ男色についてでした。まぁ遡る程男性目線、男性についての記録しかないだろうしな…っていうか男色についての記録めっちゃ残っとんのね?聞いたことあったけどそこまでがっちりと構築されてたとは驚き。時代によって当たり前だったり最先端だったり犯罪になったり差別されたり。イメージや文章の軽妙さでだいぶ緩和されてるけど遍歴のそこここで色々と考えさせられます。2021/08/31
チョビ
4
筆者は学者ではなくブロガーのため基本的には歴史オタクの「ホモ」が歴史を作ってきたという、ある意味女を除外している本である。著者は女でありながら男を見ているのだ。また、キリスト教がホモを迫害しているというが、反面連中女郎の迫害は許さない…。こうした矛盾に突っ込まないのは、やはり筆者の思惑が見え隠れする。そういうところがLGBTの理解がえられないところではないか。また学者さんだってホモやオカマがいるかもしれないのに、声高々に自分の性を押し出すところも気に入らない。2021/10/14
-

- 電子書籍
- この二次会をさっさと抜け出して家でパン…
-
- 洋書
- Wild Hearts