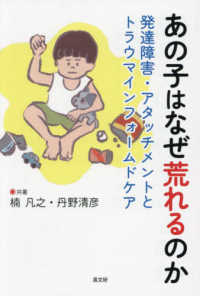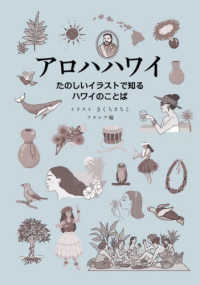内容説明
東京(江戸)、京都、大阪、神戸、福岡、仙台、静岡、奈良、鎌倉、甲府―街はどのようにつくられ、賑わったか!?
目次
はじめに―日本文明の地形史観
奈良盆地での文明誕生
桓武天皇の京都への脱出
日本列島の地理的な中心・京都
平清盛と神戸への遷都
なぜ、頼朝は辺境の地・鎌倉に?
モンゴル軍を破った福岡の地形
「信玄堤」という画期的な治水事業
信長が戦った比叡山と大坂の地形
なぜ秀吉は大坂城をつくったか
日本最初の運河・小名木川の謎
禿山に中の関ヶ原の戦い
家康が関東で発見した宝
利根川東遷事業の謎
都市を支える命の水
伊達政宗がつくった仙台
家康はなぜ静岡に隠居したか
200年の平和が生んだ堤防と文化
日本堤と墨田堤の仕掛け
明暦火災後の復興事業
日本列島の旅とは歩くこと
断崖絶壁の江戸文明
番外編 地形が生んだ「日本将棋」
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





ヒロの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kk
30
図書館本。内容は正にタイトルのとおりで、各地の都市が栄えた背景としての地理的な状況や防災的な要素を簡潔に紹介。ある意味、ブラタモリのさわりをメドレーにしたような感じ。お話の典拠などは示されないので、どこまで真に受けて良いのかは分かりませんが、論旨は明快、読んでいて楽しいです。江戸末期には日本の多くの山が禿山になっていたとの指摘にはビックリしました。「縮み志向」と移動モードの関係など、日本人論としても興味深いものを感じました。2023/01/18
りょうみや
26
著者の本は初。地形と人々の生活の間に「安全、食料、資源、交流」の社会インフラを挟んで考えているところが特徴で、とても見通しがよくなる。著者が地理や歴史学者でなく土木出身ということも独自性を出している。日本の各都市が成立に様々な考察がなされていてとても説得力を感じるのだが推測の面も大きい。読んでいて教養が身につく気になれる。中高の授業でもこのように社会インフラの側面から教えてもらえればもっと興味を持っていたはず。2023/03/09
gtn
23
奈良盆地に都を置いたのは、四方の山により外敵を防ぎ囲まれ、その森林がインフレ整備に直結したこと。その奈良を捨て、長岡京に遷都したのは、過剰な伐採により森林資源が枯渇し、当時10数十万人の生活を支えきれなかったため。その長岡京をわずか10年で捨て、京に遷都したのは、長岡京は低地にあり、巨椋池がしばしば氾濫したためと非常に明解。産業、金融、教育、医療、文化といったピースも地形という土台が崩れれば、バラバラになることが分かる。2023/11/21
まえぞう
20
建設省河川局長だった技術畑の著者が、歴史を考えるベースとしての地形について様々な例をあげながら説明しています。なるほどと思わせる指摘が多くありますが、一方で、ちょっと無理筋ではという話しも出てきます。最後の番外で、日本の将棋で捕った相手の駒を自分の駒として使えるというユニークなルールができた理由を考察してるところは、なんとなくですが合点がいきました。2025/01/16
mft
8
自説と事実の境界が曖昧なのは気になったが、主に上下水道の整備に繋がる自然条件というような視点で奈良から江戸までを見ていく内容は面白かった。近代初期まで日本全国の山で禿山化が進んでいた(そこまで素材・燃料として消費してしまっていた)というのは忘れがちな事実2023/04/15