内容説明
江戸時代は、親はもとより社会全体で人を育てた時代であった。とくに父の役割と責任は大きく、あらゆる職分の父たちが遺した教訓書や往来物を丹念にひも解くと、江戸の人育て人づくりの根底には「正直」思想があることがわかる。現存唯一の『親子茶呑咄』をはじめ、数多くの貴重な資料を現代語訳や図版でわかりやすく紹介。企業経営者、教育者、子育て世代など、人育て人づくりに関わるすべての方に一読をおすすめする。
目次
第1章 父が遺した処世訓(全二六章で綴られた父の教訓;庄屋教育は一〇年がかり ほか)
第2章 江戸の父道(父の一生は人づくりの連続;父の一言は「遺言」のつもりで ほか)
第3章 江戸の生涯指針(子どもに生涯の展望を自覚させた『九々往来』;大商人が教えた人生六〇年の計 ほか)
第4章 人づくりと正直思想(「中らずと雖も遠からず」の意味;嘘をつかないこと=正直は人づくりの基本 ほか)
著者等紹介
小泉吉永[コイズミヨシナガ]
1954年、東京生まれ。小・中・高校の教員を経て、現在、法政大学文学部講師。江戸時代の寺子屋などで使われた読み書き教科書「往来物」の蒐集と研究に傾倒し、近世庶民資料の復刻やCD‐ROM出版を精力的に行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
きょーこ
25
今より寿命が短く、早期の自立が望まれた。ひとりひとり、自分にあった本で、自分のペースで勉強した。父親の役割が大きく、子どもを預けあって、みんなで育てた。今は、学校にいく年数は長いのに身に付かないのは何故だろう。我が家も寺子屋のようなもの。親が教えるって難しいのは、江戸時代も同じなんだとクスリと笑った。2016/05/10
シュラフ
19
江戸時代の子育て論、生き様の指針、などが紹介されている。目にとまったのが、江戸時代の正直思想として紹介されている石田梅岩と石門心学の正直論。「正直」の対極としての「私欲」、「私欲」の対立概念たる「倹約」、そして「正直」と「倹約」の一体的なとらえ方。「正直」こそが天地の理にかなった生き方であると説く。現代の我々ビジネスマンも、コンプラ、コンプラなどと訳の分からないことを言うのではなく、私欲を捨てた正直な生き方をすべきなのではなかろうか。私欲に走った生き方はいつか天罰がくだるのである。2014/11/15
wasabi
1
自分を省みて、決して誉められた子育てをしてこなかったに違いなく、学ぶにはちと遅い。我が子には気の毒であった。それにしても、江戸期の学者の教えは立派なものだ。2012/10/16
atsut101
1
今も昔も子育てに関する悩みは変わらない。日本人の子育てにおいて、確認できるだけでも遡ること安土・桃山時代頃から、体罰を禁止していたことがわかっているらしい。ということは、もっと昔からそういう文化があったということ。日本てすごい‼2012/07/11
旅猫
0
いつの時代も「育てる」というのは大変なようです。わが身を振り返りつつ「きちんと」生きてみたいものだと思います。2009/07/07
-
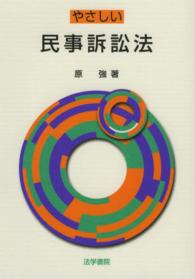
- 和書
- やさしい民事訴訟法








