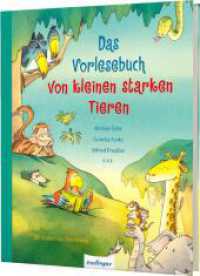内容説明
農政学から民俗学へと、柳田國男の学問の展開を方向づけたものが、国民の主体形成=教育への課題意識であったことを示し、柳田が構想した主体的な思考力を支える「考へる言葉」を育てる国語教育と、歴史的な思考力・判断力を基礎づける「史心」を養成する社会科教育を明らかにし、柳田の教育への情熱が混迷する現代の教育に新たな光明を与える。
目次
第1章 教育への関心―なぜ「教育」に関心を持ったのか(農政学期における課題意識―一九〇〇~一〇;「郷土研究」期における課題意識―一九一〇~三〇;一九三〇年以前の教育観の形成;前代教育への注目とその視角;前代教育から何を学ぼうとしたのか;教育の習俗研究の意味)
第2章 国語教育の構想―「考へる言葉」を育てる国語教育(ことばへの関心;前代国語教育への課題意識;学校国語教育の問題点と改革の方向;一九三〇年代の国語史研究;国語史研究と国語教育構想との関係;戦後の国語教育論)
第3章 社会科教育の構想―「史心」を育てる社会科教育(社会科への関わり;柳田社会科の形成;社会科教育の目的と方法;教科書『日本の社会』;子どものための歴史教育構想)
著者等紹介
関口敏美[セキグチトシミ]
奈良女子大学文学部卒業。同大学大学院文学研究科(修士課程)修了。同大学院人間文化研究科(博士課程)単位取得退学。大谷大学特別研修員、同大学短期大学部専任講師、同大学文学部准教授を経て、同大学文学部教授。博士(学術、奈良女子大学)。専攻は、教育学・教育史、特に近代日本の教育史研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。