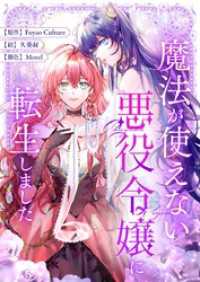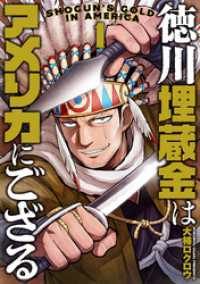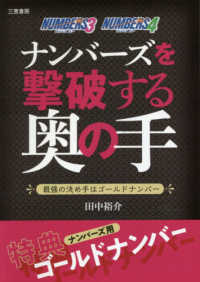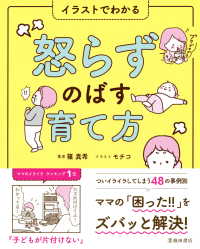出版社内容情報
ナビゲーション能力は、長い進化を通して培われた人間の根源的な力。
私たちは人類史上初めて、その力を手放そうとしている。そこにはどのような代償が伴うのか――
心理・脳・社会など多彩な論点であぶり出す、空間認知の驚きの真実。
ナビゲーション能力は、空間を把握する以外にも、「出来事を記憶し思い出す」「人間関係を理解する」「抽象的な概念を操る」「良好なメンタルヘルスを保つ」「認知症を防ぐ」など、さまざまな働きにかかわっている。
GPSや現代的な生活によって、方向や場所を把握する必要のなくなった今、その力は急速に衰えはじめている。
人間に備わるナビゲーション能力が、人を人たらしめているものだとしたら、それを失うとどうなるのだろうか――
その危機感を柱に、人と場所、心と空間の関係を、心理学、人類学、神経科学、社会学などから探る。
移動が制限され空間認知力をさらに使わなくなっている今、タイムリーな一冊。