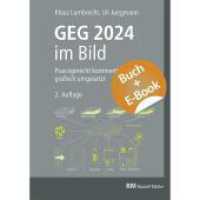内容説明
人間の会話は超弩級の離れ業だった!声の進化からAIの会話まで、科学・社会・文化・政治など多彩な角度から「話す」ことの本質を探る画期的な声の本。
目次
1 進化
2 声の三つの時代
3 私の声は私
4 声のカリスマ性
5 電気で声を変える
6 ロボットは役者にすぎない
7 コンピューターの耳にご用心
8 コンピューターのラブレター
著者等紹介
コックス,トレヴァー[コックス,トレヴァー] [Cox,Trevor]
イギリス・マンチェスターにあるソルフォード大学の音響工学教授。英国音響学会より2004年にティンダル・メダル、2009年に音響工学の普及貢献賞を受賞。BBCラジオやディスカバリーチャンネルなどのテレビ番組にも数多く出演し、音響について一般向けにわかりやすく解説している。『世界の不思議な音』で米国音響学会のサイエンスライティング賞を受賞
田沢恭子[タザワキョウコ]
翻訳家。お茶の水女子大学大学院人文科学研究科英文学専攻修士課程修了(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
山のトンネル
12
★★★★超面白い。副題「話すこと・聞くことの科学」がタイトルの方が内容を捉えていた気がする。前半では、文字の発明、蓄音機の発明によって人間の言語コミュニケーションがどのような変遷を遂げたかを紐解く。そして、中盤では声の解剖学なメカニズムの話や聴覚がどのように声を捉えるかなどを人類学の観点も交えて解説している。本書の終盤で、タイトルの「コンピューターは人のように話せるか?」に関連する内容に触れている。しかし、本書では「話せるかどうか」に限らず、コンピューターがどこまで創造的な活動に従事できるかを議論する。2021/05/18
yahiro
4
表題の通り、「コンピュータと言語」に関するパートは一部で、多くは「話すこと」に対する言語学的なアプローチ。AIに期待していると肩透かしを食います。2022/03/20
コービー
3
人間の『発声』についての歴史や未来について書かれています。具体的には◼️『声に関するその人の印象や偏見のこと』◼️『蓄音機やマイクなどの技術革新が起こる度に喉の使い方が変わったこと』◼️『嘘は見破りにくいこと』などです。そして本書の結論としては『コンピューターは人のように話せる』です。近いうちにアナウンサーや声優などの仕事はロボットが行うようになるかもしれませんね。ちなみに、本書の訳文はとても読みやすいです。2020/11/30
takao
1
ふむ2021/11/10
Kolon
1
主に人間の音声の仕組み、また音声記録の歴史、技術変遷、合成音声、音声識別等について書いてある。 意外とアッサリした本だった。2021/01/25