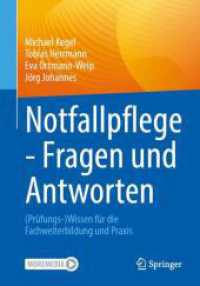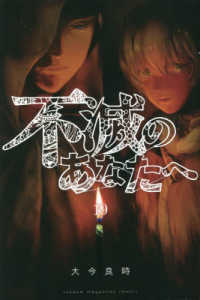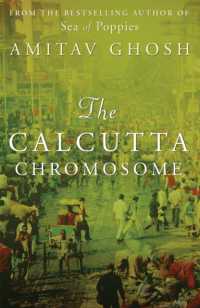内容説明
私たちはいかにヒトになったか?文化は人の心や行動を操ることで人類の進化を方向づけた。タブー、儀式、料理などが体や心に刻んだ進化の痕跡をつなぎあわせ、斬新な理論を提唱する。
目次
不可解な霊長類
それはヒトの知能にあらず
遭難したヨーロッパ人探検家たち
文化的な動物はいかにしてつくられたのか
大きな脳は何のために?―文化が奪った消化管
青い瞳の人がいるのはなぜか
信じて従う心の起源
プレスティージとドミナンス、生殖年齢を過ぎたあと
姻戚、近親相姦のタブー、儀式
文化進化を方向づけた集団間競争
自己家畜化
ヒトの集団脳
ルールを伴うコミュニケーションツール
脳の文化的適応と名誉ホルモン
人類がルビコン川を渡ったのはいつか
なぜ私たち人類なのか?
新しいタイプの動物
著者等紹介
ヘンリック,ジョセフ[ヘンリック,ジョセフ] [Henrich,Joseph]
ハーバード大学人類進化生物学教授。ブリティッシュコロンビア大学心理学部教授および経済学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まいこ
17
ヒトは個体が特に賢いわけではないが、集団の中で蓄積してきた知恵や技術をシェアする集団脳としては賢くなった。集団の人口が多く平均寿命が長く相互連絡性があるほどに集団脳は賢くなる。賢いが孤立しがちで知恵のシェアの少ないテンサイ族と、賢くはないが友人を多く持ち情報のやり取りの多いチャラい族では、後者のほうがイノベーションが普及しやすいという。占いで狩りをする場所や耕作地を決定するのは、サピエンスが陥りがちな認知バイアスを排除してランダム化する丁度よい方法で、そういうのを信じる部族が残ってきた話が面白かった。2020/05/29
Hiroo Shimoda
14
文化と遺伝子の「共進化」の考察。ヒトは他の動物と違い集団から学ぶことで生き残る生物。乳糖耐性のように、文化が遺伝子レベルに影響する。幼児がオトナの真似をするのも当然。2020/08/22
テツ
13
人間の進化は築き上げた文化と共にある。時間をかけて世代を繋ぎ、徐々に肉体を環境に適応させていくよりも、その環境に見合った道具を創造する方が手っ取り早く効率的であり、その道具で補える部分は生きるために不必要なので削ぎ落とされていく。火を扱えるようになり食材を煮炊きすることで効率良く栄養を補給でき、衣服を着て保温や防護が容易になり、言語を生み出したことで生きる上での様々な知恵を一代で終わらせることなく他者や次の時代に受け継がせられるようになった。ああ確かに文化の積み重ねは人間の進化と絡み合っている。2022/05/01
izw
13
人間が現在のように高度に進化したのは何故か、何が他の動物とは違うのかを探求し続けた著者の主張をまとめている。ヒト個体の能力・知能には限界があり、ヒトの進化を支えているのが文化である。この文化の進化こそが、ヒトの進化を加速させた原動力となっていることを様々な研究成果を根拠に論証している。文化進化がヒトの生物的・遺伝的進化を引き起こし、生物的・遺伝的進化が文化進化を加速するという好循環がヒトをここまで進化させた。その循環が最初どうやって起こったかについても一つ一つ論証を重ねている。非常に興味深く、面白い。2020/03/08
shin_ash
13
人類進化生物学の教授が人類の進化と文化の発展を実は密接な相互作用の産物であると解説する。著者の主張は仮説とは言え膨大な学術的エビデンスに基づいており十分な説得力がある。本書の主張は人類の進化論では決してメジャーではないが、"人は皆が思っている程、賢くも合理的でもない"と言う近年の心理学的な知見とも符号する様に思える。本書の多くは数百万年前の人類と文化を論じているが、この"文化ー進化プロセス"が現在も継続中と言う。それは最終章にある様に現在の私たちを理解し、より良い選択を行う為の大いなるヒントに繋がる。2019/10/13
-
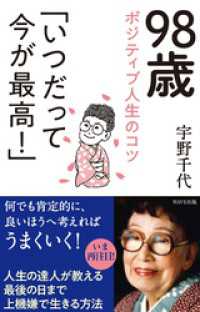
- 電子書籍
- 98歳ポジティブ人生のコツ「いつだって…
-

- 電子書籍
- 週刊アスキー 2013年 12/17号…