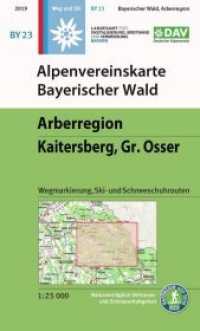内容説明
さえずるピラミッド、歌う砂漠、ささやく回廊、世界一音の響く場所…視覚に頼りがちな私たちが聞き逃してきた豊かな世界を旅する画期的な“音の本”。
目次
1 世界で一番よく音の響く場所
2 鳴り響く岩
3 吠える魚
4 過去のエコー
5 曲がる音
6 砂の歌声
7 世界で一番静かな場所
8 音のある風景
9 未来の驚異
著者等紹介
コックス,トレヴァー[コックス,トレヴァー] [Cox,Trevor]
イギリス・マンチェスターにあるソルフォード大学の音響工学教授。英国音響学会より2004年にティンダル・メダル、2009年に音響工学の普及貢献賞を受賞。BBCラジオやディスカバリーチャンネルなどのテレビ番組にも数多く出演し、音響について一般向けにわかりやすく解説している。『世界の不思議な音』で米国音響学会のサイエンスライティング賞を受賞
田沢恭子[タザワキョウコ]
翻訳家。お茶の水女子大学大学院人文科学研究科英文学専攻修士課程修了(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MASA123
12
訳者あとがきが、本書を読んだ感想に近いと思う。訳者も「すきな音プロジェクト」や「サウンドアート」に関心を寄せている。自分も、音楽とは違う、サウンドアートに興味を持った。日常で耳にする、気になる音、不快な音、好きな音、ほとんど静寂のなかの微かな音。音からどのような感情がわきあがるかは個人によって異なる。西洋音階的な不協和音に対して平気な人たちもいるなどの事例も紹介されている。 本書を読むと、音楽ではない、サウンド、音、そのものに関心をもてた。しかし、書いてある内容はマニアックすぎて理解困難な部分多し。 2024/04/15
_apojun_
6
図書館本。 著者は音響学者ということで、世界の色々な場所で聞こえる音について紹介してくれています。 とても残響音が長く聞こえる洞窟とか、ささやき声でも離れた場所で聞こえる建物のような興味深い話がいっぱい。 ランドスケープと同様にサウンドスケープという、その土地でなければ経験できない音という概念にはなるほど、という感じ。 確かに音って記憶にも残ってるし、もっと注目してもいいような気がしてきました。2026/01/16
ヘビメタおやじ
5
音を文章で読む。どうかなと思って読み始めましたが、音は聞こえてきませんが、新たな発見に心躍ります。特に、海洋生物に対する騒音については、全く考えたこともなく、しかし、言われてみれば当たり前のことで、真剣に考えなくてはいけないことだと知らされました。また、管楽器の音色は材質に影響されないというのも、サックスを習っている身として、興味津々でした。2016/08/27
vonnel_g
3
音響物理学の専門家である著者が案内する「音」の世界。コンサートホールの設計に携わる方らしくホールから始まって、無音の荒野である北極まで、人工・自然の別なく様々な音とその仕組みが紹介されている。「気泡ができるときに発生する音を研究している」研究者というものが存在するとは。ワシントンにあるという人工のストーン・ヘンジにはちょっと行って中央で風船を割ってみたい。2019/01/19
のぶ
2
(私の世代はジブリ映画ではなく本田路津子さんの歌で覚えた)「耳をすます」という行為、考えてみたら耳コピする時とか鳥を見つけた時ぐらいにしか普段やらないなあ。でも本書で刺激を受けた私、この先は折々にふと目を閉じて音空間に注意を払ってみる、という暮らしをしそうです。視覚だけで生きてきた人間に人生の別の楽しみ方を教えてくれる本、とも言えそうです。いま巻頭の地図をあらためて眺めてみたら広く世界中の事例が紹介されていますね。あ、でも、鴬張りとか鳴き竜とか日本にも貴重な文化があるけど残念ながらそれは含まれていません。2019/04/28