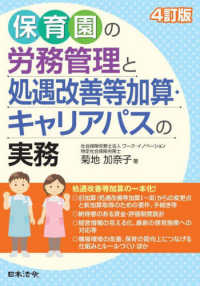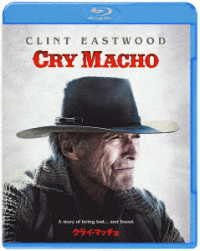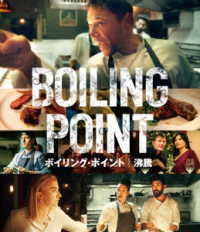内容説明
明治期にドイツからステンドグラスの技術を持ち帰った宇野澤辰雄、アメリカで学んだ技法を大正期の日本で開花させた小川三知。日本のステンドグラス黎明期に活躍した二大作家の代表作をそれぞれフルカラーで紹介。
目次
1 明治・大正・昭和の名品(開東閣(旧岩崎彌之助高輪邸)
西川本店(旧西川甚五郎邸)
夢二カフェ五龍閣(旧松風嘉定邸)
大阪市中央公会堂
神戸迎賓館須磨離宮ル・アン(旧西尾類蔵邸) ほか)
2 新たに発見された小川三知の作品(東京都美術館(旧東京府美術館)
海上自衛隊田戸台分庁舎(旧横須賀鎮守府司令長官官舎))
3 対談 日本のステンドグラス(増田彰久;田辺千代)
4 資料
著者等紹介
増田彰久[マスダアキヒサ]
1939年生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業。増田彰久写真事務所を主宰。第33回写真協会年度賞(1983)、第9回伊奈信男賞(1984年度)、2006年度日本建築学会文化賞など受賞
田辺千代[タナベチヨ]
1942年生まれ。日本海事新聞横浜支局勤務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
依空
74
明治から昭和に作られたステンドグラスの名品が収録された『日本のステンドグラス』シリーズ3冊目。ヨーロッパでは宗教色が強いステンドグラスですが、日本では室内装飾の意味合いが強く独自の発展を遂げており、葵祭や時代祭、鹿や車といった意表を突くデザインには驚きました。またステンドグラスは神社仏閣にまであったそうで、新しい文化を受け入れていく日本の文化を感じることも出来て面白いです。優れた作品がこれだけ多く現存するのに、それがある建物は非公開の所が多く、現地を訪れ実物を見ることが出来ないというのが何とも残念ですね。2017/02/06
WATA
61
日本の洋風建築の窓に残る、明治〜昭和初期に制作されたステンドグラスの写真集。日本のステンドグラスはヨーロッパのものに比べ、緑の表現が繊細で美しい。絵の下草の部分に使われている深緑色、草花の茎の濃い黄緑色、葉っぱに使われているエメラルドグリーンや裏葉色、背景色として絵全体を覆っているクリソライトのような薄い色。そして何より、無色ガラスに薄く写り込んでいる外の庭木の緑色。これらの彩り豊かな緑色がうまく組み合わされて一体となっており、じっと眺めていても飽きがこない。2014/05/17
リコリス
29
海外では教会のイメージが強いステンドグラス。この本に登場するのは絵画のようだったり菊や菖蒲、竹など日本らしいものがとても新鮮で自由な感じがする。和室の楕円のスタンドグラスや表紙のも素敵。ステンドグラスだけじゃなくガラス自体もレトロでおしゃれでため息がでます。2020/12/17
Rosemary*
20
ステンドグラスと言うと、中世ヨーロッパの修道院、大聖堂、教会などの装飾から、数多く広まり、とても美しいものです。日本にも、明治時代に「小川三知」さんと「宇野澤辰雄」さんにより伝わってきたようです。和洋折衷のような作品も多く、とても面白いです。ノスタルジックで、欧米にはない繊細な作品を堪能しました。2013/11/23
花林糖
18
(図書館本)ヨーロッパの物とは違う、日本らしさのある美しいステンドグラスにうっとり。何気なく気になり借りてみたら大当たり。大丸心斎橋店の建物はレトロなので何度も見ていたけれど、ステンドグラスは見落としていたなぁ。どれがお気に入りかは選べない程に全てが美しい。(購入)2016/10/06