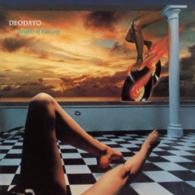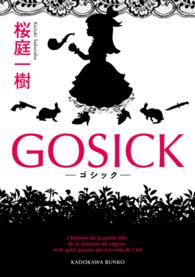内容説明
世界を揺るがした衝撃の超ベストセラーは「本当は何を書いた本なのか?」多くの読者を悩ませ楽しませてきた問いに、ついに著者自ら答える序文収録。20周年記念版。
目次
1 GEB(音楽=論理学の捧げもの;MUパズル;数学のおける意味と形;図と地;無矛盾性、完全性、および幾何学 ほか)
2 EGB(記述のレベルとコンピュータ・システム;脳と思考;心と思考;ブーとフーとグー;形式的に決的不可能なTNTと関連するシステムの命題 ほか)
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たかしくん。
31
後半のEGBは更に手強いです。AI(人工知能)の矛盾を検証、中でも英仏独日組曲、ASU、「罪と罰」のS横町の逸話を通し、機械語に対する、より高く纏められた見方の必要性を論じる部分は秀逸。更に「クワイン化」初め自己言及のパラドックスに論点が進み、遂には人間最大の矛盾「個人の非在」に及びます。最終章での本書の問掛け「我々は、心或いは脳を理解することが望めるか」「ゲーデルの悪魔的命題(≒矛盾?)がそれを阻むのか」、この「不思議の環」が残る限り、ゲーデル、エッシャー、バッハの三本の糸は編み続けられるのでしょうね。2015/01/12
たかしくん。
28
再読かつ漸く前半部「GEB」読了。バッハの音階、エッシャーの階段を不思議の環と譬える話から始まり、パラドックスをテーマとしたゲーデルの数学に誘う序章。しかし本論からは、まず「MIU」「pq」なる形式システムに面喰います。その中で、ユークリッド、素数、フェルマー等を例に、数々のTNT(字形的数論)にトライします。そして前半の最終章で愈々「禅」が登場。まさに禅問答のような対話集のあと、「数学の形式システム」と「善の言葉」の各々のジレンマに共通点を見出すところで前半部が終了します。半端ない読み応え歯応えです!2014/10/19
デビっちん
21
物質的な構成要素から抽象的なパターンへ焦点を移すことで、意味論的でないものから、意味論的なものへ、生命のないものから、生命のあるものへ魔法のように飛躍できることをあの手この手で解説してくれているように感じました。そのプロセスは渦のように捩じれ、ある階層システムの段階を移動すると、以外にも出発点に帰ってくる不思議の環のパターンを経ています。生命のないものから、生命のあるものへの飛躍は、人の意識や心にも当てはまるようです。理解できたという実感ははとんど持てませんが、読みきったという充実感は残りました。2017/03/26
ちゅん
13
この本は何の本なのかを形容するのは難しいですが、私の拙い言葉で表すならば「科学本の『カラマーゾフの兄弟』」といったところです。どんなところが「カラマーゾフの兄弟」なのか?…ということですが、10以上のテーマが1つのメインストリームを紡いでいるところが「カラマーゾフの兄弟」と類似していると感じました。「カラマーゾフの兄弟」が扱うテーマは、ミステリー、キリスト教、人間の欲、貧困問題、人間の愛、裁判、ギリシア神話、旧約聖書…といった感じです。(続きます)2018/06/19
やす
9
めっちゃ長いのでパート1までの予測を含めた雑記。一言でいうとパート1はゲーデルの不完全性定理の概要を解説。原論文のパート1をゴールとしてすべての言明を数に置き換える仕組み、そのため記号論理学の結構ガチな導入。これにより体系内で表現できるすべての主張は数に置き換え可能でありこれを順番に並べることでR(n)という順序関係を策定でき、W=証明できないn[R(n);n]という類を作ることができ、S(n)をnはWに属すという命題があり、これはRの中でR(q)と表されるがこのqはWに属すかは決定できない2025/01/27