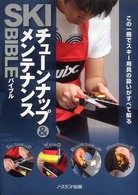感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1959のコールマン
17
☆4。題名で勘違いする人が多いのではなかろうか。戸惑う人続出だろう。これは研究本ではなく、調律師が書いた、ピアノの調律をテーマにしたエッセイである。故に謎解きはされず謎のまま。引用文献、参考文献の表記もない。ただ、うれしい誤算なのは、文章が面白く、味わい深いことだ。それもそのはず。著者紹介で「子どものころから青年期まで、彼女の関心はつねに言葉の世界にあった。・・・高校ではたえず物語を書きつづけて、カレッジに入ると英語学を専攻した」p140とある。楽しい読書の時間。2019/06/13
できアン
3
ピアノの調律について。ただ単に完全な音にするのではなく、均等に加減をする。調律を終えた音は耳が錯覚することや調律者の好みで微妙に変わってくる。調律は完璧な音を目指すのではなく、目的にかなったものを求めていく。一音は唯一だけど絶対ではないという解釈で著者の意に沿っているだろうか。2013/11/22
kaizen@名古屋de朝活読書会
3
調律という観点から、平均律の意味について、興味深い内容になっている。 これから、調律師になろうとしている人だけでなく、ピアノを弾き、ピアノを聴くすべての人に知っていて欲しいことが書かれている。音楽が何故、数学と仲良くできていないかの根源的な問題を浮き彫りにしようとしている。 平均律は、倍(2)音を、オクターブ(8)、12音でどうやって区分するかという、一面では非常に数学的な問題に取り組んでいる。波という物理的な現象に関係し、共鳴、共振という現象と、うなりという現象に着目している。 2011/11/04
古西 広之
2
人の耳は平均律の3倍くらい音階があっても十分聞き分けられるのに、なぜこのシンプルな音階に収束してきたのだろう。 もちろん伝統音楽にはこの音階にない音まで伝えられてはいるが、平均律に慣れた現代人や楽譜上に完全な記録ができない曲は徐々に変化してしまっているかもしれない。 中全音律を前提として作曲された古典派作品を平均律で演奏すると、作曲者の意図とは違う曲の印象を受け止めているということか。2017/11/03
ヨーク
1
調律師の仕事の難しさと平均律の深さが味わえた。オクターブ以外の割り切れない音程の調律が、いかに難解なのかが説明されていたが、知識不足で完全に理解できなかった...2012/04/30
-
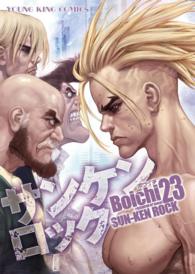
- 電子書籍
- サンケンロック(23)