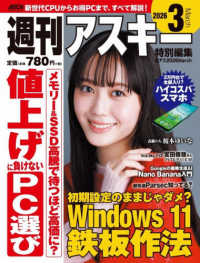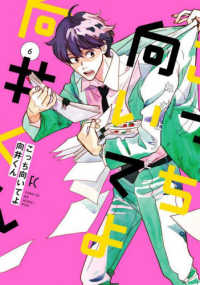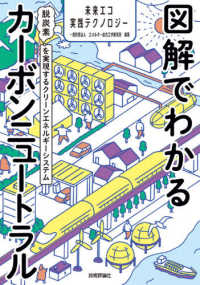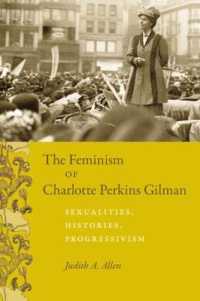内容説明
顕微鏡からコンピュータまで、オルガンからシンセサイザーまで、科学と芸術はどのように補い合い、われわれに知的調和をもたらしてきたか。
目次
1 神意により!?―オルガンと音楽の創造、そして科学が発見した世界(完璧な秩序と自然の理法;何もかも完全な形で自然界にある ほか)
2 無限の可能性?―錬金術、不確定性、ストラディヴァリの音の秘密(大いなる神秘;人間の能力はどこまでも ほか)
3 知りたいことをすべて知る―モデル実験、そしてシンセサイザーと意味のありか(洞窟の光;何としても新しい道具が必要)
フィナーレ 描写は啓示である
著者等紹介
中島伸子[ナカジマノブコ]
1956年神奈川県生まれ。国際基督教大学教養学部人文科学科卒業(フランス文学専攻)。貿易会社、編集プロダクション勤務を経て、現在翻訳業に専念
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
75
図書館本。いつか入手したい。音楽史の本であり、科学史の本でもあるが、詰まるところ、哲学史というより哲学の本と思っていいだろう。 といっても、堅苦しさは全くない。知見に富んでいて、西洋哲学を少しは齧った小生も水の哲学者タレスの「水」の意味するところ、ピタゴラスにとっても、それとも西欧における音と数の今日に至る洞察の意味合いの深さを改めて感じさせてくれた。 2005/08/21
ふみ
1
タイトルから受ける印象とはうらはらに、この本の焦点は科学であって音楽ではない。西洋科学史を科学と音楽の関係性から論じた一冊。最初の科学の一つはピタゴラスの論じた「天球の音楽」説であった。中世の数学4科は、算術、幾何学、天文学、音楽であったが、ルネサンス期に音楽が切り離され、他3科は真実を追求する学問、音楽は倫理の学問として他3科から解析される対象となり、科学としての音楽は終焉を迎える。バッハの対位法(絶対的真)からベートーヴェンの和声法(個にとっての真)の流れは神学が近代科学へ取って代わった道筋と重なる。2013/03/04
Ai
1
パイプの長さから平均律が定められてオルガンが作成された話からストラド(主にチェロ)の音色の謎、そして2進数のコンピュータに至るまで、多岐に渡った考察が非常に面白かった。2011/04/01