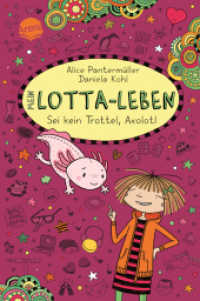出版社内容情報
今日、トチ餅は日本各地でお土産として販売されている。実はトチの木は東京の中心、霞ヶ関にも植生しており、夏の終わりには無料でトチの実を入手することができる。しかし、簡単に手に入るトチの実でも、それを食用にすることは現代でも意外と難しい、高度なアク抜きの技術が必要となってくる。そのトチの実は、遥か何千年も前の縄文時代から、日本各地で食されていた。なぜ、そしてどのようにして縄文人はトチの実の食用を可能にしていたのか?
現代に手に入れたトチの実を、文献を基に縄文時代の手法を用いてトチ餅にする過程をとおして、今なお息づく日本の食文化の歴史を辿る。
序章 トチの実の産地は霞ヶ関
第一章 トチノキを究める/1 トチノキの植物学/2 トチノキの人文学/3 トチノキの応用学
第二章 アク抜きの食文化/1 アク抜きの科学/3 木の実食の民俗学
第三章 東京産トチ餅の味/1 木灰によるアク抜き再開/2 木灰を使わないアク抜き/3 東京産のトチは美味
第四章 縄文人はなぜトチの実を食べたか/1 縄文時代の概観/2 縄文時代の食料資源/3 縄文時代の人口/4 縄文時代の食料危機
第五章 縄文飢饉の原因に迫る/1 クリの衰退原因を見直す/2 クリに病害が大流行
第六章 木の実食の伝承/1 弥生時代/2 土師器時代以降
著者あとがき
参考文献
学名
内容説明
身近にあって手に入れる事は容易でも、食用にするには高度な技術が必要なトチの実。そんなトチの実を、何千年も昔の縄文時代から人びとは食用としていたのである。なぜ、そしてどのようにして縄文人はトチの実を食べていたのか?実際に霞ヶ関でトチの実を入手してトチ餅をつくる体験をとおして、今なお息づく日本の食文化の歴史を辿る。
目次
序章 トチの実の産地は霞ヶ関
第1章 トチノキを究める
第2章 アク抜きの食文化
第3章 東京産トチ餅の味
第4章 縄文人はなぜトチの実を食べたか
第5章 縄文飢饉の原因に迫る
第6章 木の実食の伝承
著者等紹介
濱屋悦次[ハマヤエツジ]
1929年東京生。東京大学農学部卒。農学博士。専攻は植物病理学、植物ウイルスに関する研究で日本植物病理学会賞受賞。農林水産省在職中は各種作物病害の研究に従事、東京大学大学院講師、科学技術会議専門委員(組換DNA分科会担当)を兼務。農林水産省退職後は日本女子大学講師、東京バイオテクノロジー専門学校講師など。現在は各地の食文化について情報収集中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
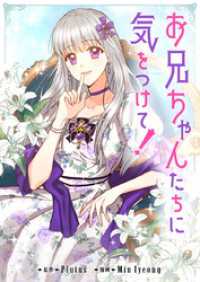
- 電子書籍
- お兄ちゃんたちに気をつけて!【タテヨミ…