出版社内容情報
教師の仕事というのは、つねに子どもの「こころ」と「からだ」に働きかけることである。優れた教師とは子どもの立場に立って個々の子どもたちの状況を把握し、臨機応変に対応するためのテクニックを身につけ、使い分けられる教師である。
ところが最近の教育状況は、「心のノート」(河合隼雄監修)を通した子どもたちの「こころ」の支配に始まり、儀式における「日の丸・君が代」の強制によって「こころ」と「からだ」を行政権力が直接支配しようとする。
さらに、ジェンダーフリー教育や性教育の否定(東京都教育委員会)など一連の動きは、教育基本法における「宗教教育」の改変によって『聖なるもの〈万世一系の天皇制〉に対する畏敬の念』(高橋史郎・明星大教授)を注入し、国家神道の自然観に根ざした「宗教的情操」教育を通して教育の再編をもくろむものである。
もはや学校という空間は、行政権力があらゆる機会をとらえて子どもたちの心と身体をコントロールし、所属集団への帰属意識を注入して国家イデオロギーを強要する装置になりつつある。
教育現場の苦悩と挫折を超えて、抵抗とたたかいの展望を多面的に収録した教育最前線の緊急報告!
序章-「型から入る」教育の意味◎柿沼昌芳
■ 第1部 〈対談〉イデオロギーとしての身体=教育◎斎藤貴男+尾崎光弘+[司会]永野恒雄
■ 第2部 宗教的情操と「こころ」の支配
第1章 「宗教的情操」とは何か ◎柿沼昌芳
第2章 教育基本法「改正」と<宗教的情操> ◎青木茂雄
第3章 『心のノート』と「こころの支配」 *宗教的情操を中心に ◎金子隆弘
第4章 中高一貫校と教科書問題 ◎和田章子
第5章 内心を表現する自由 ◎柿沼昌芳
■ 第3部 学校における「からだ」の支配
第6章 部活動顧問のカリスマ性 ◎森山陸雄
第7章 教室の中の身体 *遊び空間の変容から考える ◎尾崎光弘
第8章 地域事例に見るボランティア活動と就労体験の諸相 ◎飯淵興喜
第9章 ジェンダー・フリー・バッシング ◎江熊隆徳
第10章 「暗誦朗誦文化の復活」は時代錯誤の幻想だ ◎向井吉人
■第4部 心と身体の支配の歴史
第11章 国家神道と「日の丸・君が代」 ◎川口和也
第12章 戦時・戦後教育と心身の支配 ◎田丸 啓
第13章 戦後教育の出発とナショナリズム感情 ◎永野恒雄
終章 教育の身
●【SERIES「教育改革」を超えて】の第4巻です。
●斎藤貴男×尾崎光弘対談収録
*装画=石塚アキ
*装丁=臼井新太郎
*組版=字打屋(西澤章司)
目次
「型から入る」教育の意味
第1部 対談・イデオロギーとしての身体=教育
第2部 宗教的情操と「こころ」の支配(「宗教的情操」とは何か;教育基本法「改正」と“宗教的情操” ほか)
第3部 学校における「からだ」の支配(部活動顧問のカリスマ性;教室の中の身体―遊び空間の変容から考える ほか)
第4部 心と身体の支配の歴史(国家神道と「日の丸・君が代」;戦時・戦後教育と心身の支配;戦後教育の出発とナショナリズム感情)
教育の身体性をめぐって
著者等紹介
柿沼昌芳[カキヌママサヨシ]
1936年生まれ。元東京都立高校教諭。全国教育法研究会会員、明治大学・中央大学などの非常勤講師
永野恒雄[ナガノツネオ]
1949年生まれ。都立大崎高校教諭。全国教育法研究会会長、日本教育法学会理事、歴史民俗学研究会会員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
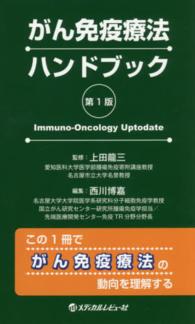
- 和書
- がん免疫療法ハンドブック






