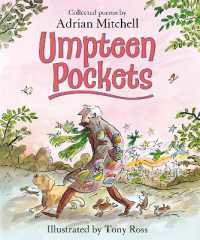出版社内容情報
「尻の穴を開け!!」
男色を容認してきた日本の風土、文化と日本人の深層に迫る!
高野六十那智八十(高野山や那智山の坊主は男色をやっているので高齢になって
も色気がある)。古来日本は男色が盛んな国であった。近代以前の僧侶・武士・芸能者という男色の「三大勢力」に、明治以降は学生が加わった。その系譜は今日のオウム真理教や自衛隊にまで脈々と連なっている。
未開拓な部分が多いわが国の男色研究史の中から、明治20年代~昭和30年代の知られざる男色論・ユニークな男色論21編を紹介する、「男色」を通して見る日本精神史。
■解説篇
◎男色の沿革を略述し日本人の国民性に及ぶ(礫川全次)
オウムと自衛隊/明治の学校と男色の悪弊/『ヰタ・セクスアリス』と金井湛の受難/金井湛、二度目の受難/薩摩武士と男色/硬派と軟派/薩摩の郷中教育について/きだみのると「尻つき」/「レイプ容認」の風土/「ケツの穴が小さい」/その昔陰間だった老人の回想/通和散と安入散/陰間の養生法
■資料篇
凡例
1 男娼(一八九〇年) 独笑居士
2 男色に就て(一八九九年) 舟岡英之助
3 学生の暗面に蟠れる男色の一大悪風を痛罵す(一九〇九年) 河岡潮風
4 婦女を童に代用せし事(一九一二年) 南方熊楠
5 男子間相愛の風俗の沿革(一九一八年) 森徳太郎
6 同性愛の歴史観と其意義(抄)(一九二一年) 鷲尾 浩
7 男色に関する史的及び文学的考証(一九二四年) 田中香涯
8 男倡を出現させた当代の好(一九二七年) 中山太郎
9 男娼(一九二九年) 田中香涯
10 本朝男色雑考(一九三〇年) 鈴樹大允
11 男色考(一九三〇年) 旭 寿雄
12 日本の文学に現はれたる同性愛(一九三〇年) 守田有秋
13 売笑婦男装考(一九三四年) 田中香涯
14
『週間朝日』の連載インタビュー記事「マイクなんていらない」に、新進気鋭の狂言師・野村萬斎氏が登場したのは、その一九九九年三月一九日号であった(聞き手は、ニュースキャスターの安藤優子氏)。
当時たまたまこの記事を読み、狂言における所作の特徴について野村氏が述べている内容に関心を抱いた。
野村 このあいだ、朝日新聞に古武道の記事が載ってましたけど、西洋のスポーツは基本的にねじりの構造で、(いすから立ってふつうに歩きながら)右足が前に出ると左手が前に出る。古武道やわれわれは、(空手のようにグッと腰を落とし、右手と右足を同時に前に出して)こう、同じ方向に動かすわけですね。
安藤 ああ、なるほど。
野村 重心のありどころが決まってるから、ふだん立つと、出っ尻ふうというか、(お尻を突き出して)こう、お尻を非常に強調した立ち方になってしまうんですね。能楽師、能狂言に携わる人の立ち方は共通していて、なんとなくトリっぽい。(お尻をグッと突き出し、サギのような格好をする)
安藤 アハハハハ……。
野村 バレエの人はこう立つ(背筋をピンと伸ばして胸を張る)。お尻の穴を締めるか締めないからしいんですけどね。バレエ自体が目的で、その目的を達成するために工夫されたのが、「腰を落とし、尻を突き出す」という独特の所作だったのではないか。
この資料集の読者諸氏に対しては、「尻の穴を開く」修行がありえたことをクドクドと説明する必要はあるまい。ただ、「尻の穴」の大小ということについては「解説編」を参照いただきたく、また、猿楽と男色との関係については、「資料編」の森徳太郎「男子間相愛の風俗の沿革」(一九一八)中の、「室町将軍の時代には田楽。猿楽の舞伎が大に行はれて……此役者の中の美容あるものは貴紳の寵遇を受くるやうになつた」云々の記述に注意していただければと思う。
数年前、本巻編集用の材料を求めて、上野広小路の「上野文庫」(古書店)を訪れた。入口から見て右奥下段、つまり店主のすぐ近くに関係の書籍があった。あれこれ手にとって見ていると、店主がそれと察したのか、どこからか緑色のカバーの本を取り出して近づいてきた。「こんな本もありますよ」といって手渡されたのは、『第三の性』(一九五七)という未知の本であった。本巻資料編で紹介した伊藤晴雨の「同性愛の秘技を探る」は、この本に収録されていた対談である。
本年(二〇〇三)九月、そ
好評「歴史民俗学資料叢書・第2期」の第3巻です。
内容説明
古来日本は男色が盛んな国であった。近代以前の僧侶・武士・芸能者という男色の三大勢力に、明治以降は学生が加わった。その系譜は今日のオウム真理教や自衛隊にまで脈々と連なっている。男色を通して見る日本精神史。未開拓な部分が多いわが国の男色研究史の中から、明治20年代~昭和30年代の知られざる男色論・ユニークな男色論21編を紹介する。
目次
解説篇 男色の沿革を略述し日本人の国民性に及ぶ
資料篇(男娼(一八九〇年)(独笑居士)
男色に就て(一八九九年)(舟岡英之助)
学生の暗面に蟠れる男色の一大悪風を痛罵す(一九〇九年)(河岡潮風)
男子間相愛の風俗の沿革(一九一八年)(森徳太郎)
同性愛の歴史観と其意義(抄)(一九二一年)(鷲尾浩)
男色に関する史的及び文学的考証(一九二四年)(田中香涯)
男倡を出現させた当代の好尚(一九二七年)(中山太郎) ほか)
著者等紹介
礫川全次[コイシカワゼンジ]
1949年生まれ。ノンフィクションライター。歴史民俗学研究会代表
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。