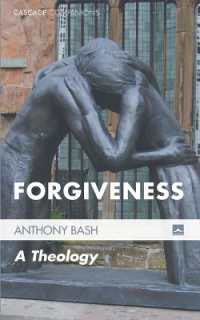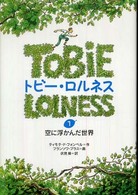出版社内容情報
読書趣味と学問道楽と猟奇癖!
糞尿の〈呪力〉と〈汚穢性〉にみる近代日本人の糞尿観とは?
三島由紀夫の『仮面の告白』によれば、主人公の「私」は、五歳の時に道で〈汚穢屋・おわいや〉(糞尿汲取人)に出遭い、「汚穢屋になりたい」という憧れを抱いたという。三島由紀夫の出自の秘密にかかわる汚穢屋に対する過剰な思い入れは、汚穢屋に〈賤民性〉を見出す大正期以降の近代都市住民の誤解や偏見の反映であるとはいえ、糞尿の〈呪力〉に対する日本人固有の情念と憧憬に根差していたといえるのである。
近代日本における糞尿利用の変遷と近代日本人の糞尿観の変化に焦点を当てつつ、糞尿をめぐる日本人の心意を解読し、基層文化の深層に迫る資料集。
宮武外骨「小便考」、田中香涯「糞と尿」、井上一之「日本便所考」他、埋もれた資料や閲覧しにくい26の文献を収録、注釈も付した読みやすい全文新組み版。
『週刊朝日』で高橋源一郎氏、好評!!!
●解説篇
糞尿はいつから〈汚物〉になったのか~近代ニッポン糞尿史序説(礫川全次)
・三島由紀夫の〈汚穢屋〉願望/三島由紀夫の「出自」について/〈汚穢屋〉は賤民にあらず/昭和初年の東京における〈汚穢屋〉の実像/竹内武雄氏の「汲み取り」体験/徳富蘆花の見た「不浄取り」/都市住民の〈汚穢屋〉に対する意識/本資料集の編集方針について
●資料篇
凡例
●「古糞鑑弁之記」大原栗(一八一二) 『下肥』(一九一四)より
●「阿房陀羅経(下肥の注意)」堀之内片田舎生 『新潟県農事報』(一九〇六)より
●「小便考」宮武外骨 『滑稽新聞』(一九〇八)より
●「下肥」中尾節蔵 『修正実用肥料学』(一九〇八)より
●「糞と米とは何れが尊き乎」矢崎亥八 『日本農業雑誌』(一九〇九)より
●「人糞尿又下肥」佐々田源十 『最新実用肥料学』(一九一〇)より
●「日本の糞と西洋の糞」岩村透 『ニコニコ』(一九一一)より
●「支那の厠神」吉田巌 『人類学雑誌』(一九一四)より
●「名古屋市に於ける屎尿市営方法」燕佐久太 『下肥』(一九一四)より
●「人糞尿の話」古市末雄 『軍隊農事講習講演集 第二輯』(一九一五)よ崎憲正・中村治郎 『犯罪証拠』(一九四七)より
●「しようべん考」(他)滝川政次郎 『別嬪と美人』(一九五六)より
●「旧十五区市営前の屎尿処分の実態」黒川義雄 『東京都における屎尿処理の変遷』(一九六一)より
歴史民俗学資料叢書(第1期)全5巻の内容を予告すると同時に、その第1巻『糞尿の民俗学』を刊行したのは、1996年のことであった。埋もれた資料や閲覧しにくい文献を集め、それを「原形」のまま影印で紹介した資料集であった。
「読書趣味と学問道楽と猟奇癖」に徹した構成がよかったのか、この叢書は、幸いにも読者から好評をもって迎えられ、1998年までに第1期全5巻を完結させることができた。多くの公立・私立図書館に受け入れられたほか、書籍・論文の末尾に「参考文献」として紹介される機会も多く、本叢書所収の文献をフルに活用した卒業論文もインターネット上で見つけた。
第2期全5巻の計画は早くから立てていたのだが、集めた資料の「捜索」と整理に手間どり、ついに世紀を跨いでしまった。
タイトルをご覧になればおわかりのように、今回のシリーズも、「読書趣味と学問道楽と猟奇癖」の産物である。また、その目指すところや編集方針も第1期と同様である。ただ、第2期においては、原文を影印で紹介するのではなく、全文を正確に入力し直すことにした。これによって原文は非常に読みやすくなり、同時に注釈を付すことも可能になった(「原形」の雰囲気を紹介でき
歴史民俗学資料叢書・第1期・全5巻も好評発売中!
内容は
第1巻・糞尿の民俗学
第2巻・人喰いの民俗学
第3巻・浮浪と乞食の民俗学
第4巻・刺青の民俗学
第5巻・生贄と人柱の民俗学
です。
●いずれも、当・版元ドットコムより購入可能です。
内容説明
近代日本における糞尿利用の変遷と日本人の糞尿観の変化に焦点を当て、糞尿をめぐる日本人の心意を解読し、基層文化の深層に迫る資料集。
目次
解説篇(糞尿はいつから“汚物”になったのか―近代ニッポン糞尿史序説)
資料篇(古糞鑒弁之記(一八一二年)(大原栗)
阿房陀羅経(下肥の意)(一九〇六年)(堀之内片田舎生)
小便考(一九〇八年)(宮武外骨)
下肥(一九〇八年)(中尾節蔵) ほか)
著者等紹介
礫川全次[コイシカワゼンジ]
1949年生まれ。ノンフィクションライター。歴史民俗学研究会代表
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。