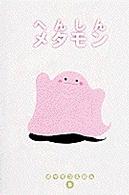出版社内容情報
1986年のチェルノブイリ原発事故をひとつのきっかけに、社会主義の大国ソ連はその威信を失い始め、それ以前から顕在化していた東欧諸国の社会主義離れを加速する。
国内では、アメリカのレーガン大統領と「ロン・ヤス」と呼び合う中曽根首相が、保守・反動の流れを誘導していった。「日本列島不沈空母化」発言(1983)、米原子力空母の佐世保寄港(同)、首相の靖国神社公式参拝(1985)、国鉄の分割民営化(1987)、防衛費GNP一%枠突破(同)などは、そうした流れを象徴する出来事であった。
この時代、教育の面でも、臨時教育審議会設置(1984)、文部省の「国旗・国 歌」徹底通知(1985)、『新編日本史』検定合格(1986)など、「反動化」が進んだ。気をつけなければならないのは、当時、《学校》や《教育》をめぐって生じた「事件や犯罪」が契機となって、そうした「反動化」の流れが加速していった点である。
1983年の「横浜浮浪者襲撃致死事件」や「町田忠生中ナイフ刺傷事件」が、翌年の臨教審設置に結びついたのは、単なる偶然ではない。1980年代後半にいたって、教育をめぐる混乱は一層深まり、学級崩壊・学校崩壊が叫ばれる中で、教育行政の攻勢が強まる一方、教育の地方分権
まえがき
凡 例
第1章……都立高校教師ホーム転落死事件……1986
第2章……鹿川君いじめ自殺事件……1986
第3章……浦安市暴走族抗争致死事件……1989
第4章……福岡市中学生「生き埋め」事件……1989
第5章……神戸高塚高校「校門圧死」事件……1990
第6章……兵庫県立農業高校不正入試事件……1991
第7章……神戸高専「エホバの証人」事件……1991
第8章……風の子学園事件……1991
第9章……龍野市体罰自殺事件……1994
第10章……大島南高校飛び込み事件……1995
第11章……近大付属女子高校体罰死事件……1995
第12章……生徒会誌切り取り事件……1996
第13章……尼崎東高校セクハラ事件……1996
第14章……旭川市中学校・校内監禁強姦事件……1996
第15章……神戸須磨児童連続殺傷事件……1997
第16章……大阪・中学校教師セクハラ事件……1997
第17章……東京・足立十六中・社会科授業介入事件……1997
第18章……都立高校授業編成「虚偽報告」事件……1997
第19章……黒磯市女性教師刺殺事件……1998
第20章……落語居眠り観客退出事件……1998
第21章……広島県世羅高校・校長自殺事件……1999
第22章……都立高校「
まえがき
戦後起った数多くの事件・犯罪の中から、本巻では1986年以降の事件がまとめられているが、件数の多さに驚き、同時に時間の激流の中に身をゆだねているような私たちは、多くの事件を無意識の内に忘れ去っていることを改めて実感させられている。
学校教育について1980年代をみると、1984年には臨教審が発足して四次にわたる答申を提出した。その後、本シリーズ『戦後教育の検証』(特に別巻)でまとめたように、現在、新自由主義、新保守主義の影響下に「教育改革」が激しく進行している。
その一方で、文部科学省の「少年の問題行動等に関する調査研究協力者会議」は、『心と行動のネットワーク―心のサインを見逃すな、「情報連携」から「行動連携」ヘ―』 (2002年4月)の中では「最近の児童生徒の問題行動の状況」を次のように捉えている。「少年非行については、少年による主要刑法犯の検挙人員の推移を基にすると、昭和26年、39年、五58年をそれぞれピークとする三つの波があり、昭和59年(1984)以降は減少していたものが平成8年(1996)以降増加傾向にあり、第4の波を迎えていると言われている」したがって、本書が取り上げた1986年以降は、1983年をピークとする第うかのような錯覚が生まれている」、しかも「心」の部分を「事件は発生のカギ」とみなすようになり不安を募らせるだけになっている、と不必要なまでに微細にセンセーショナルに報道するマスメディアの責任を糾弾している。
私たちは、多くの事件をマスコミなどの報道を通して知るが、いま、改めて、社会的背景などもふまえて事件の核心に迫ることが現在の教育を考えるうえでも重要であると考えており、ぜひ、前巻はもとより、本巻で紹介した事件も年表と対応させながら、各事件を検証していただければと思う。
編者
◎装幀……臼井新太郎
◎組版……字打屋
新シリーズ『学校の中の事件と犯罪』第2巻です!
●2005年10月10日、第2刷出来!
内容説明
1997年の「神戸少年A事件」、1998年の「黒磯ナイフ事件」をきっかけに「少年法」は厳罰化され、1999年の「広島県世羅高校・校長自殺事件」を機に国旗・国歌法が制定されるなど、ナショナリズムへの回帰が加速し、「教育基本法」までもが改正されようとしている。これらは戦後教育の流れを変える「教育改革」が、常に“事件”を契機に進化することを証している。教育をめぐる事件と犯罪の実態を、教師としての知性と感性と経験をもとに解読し、教育の今日的状況を検証する。1945~2001の戦後教育事件史年表収録。
目次
都立高校教師ホーム転落死事件(1986)
鹿川君いじめ自殺事件(1986)
浦安市暴走族抗争致死事件(1989)
福岡市中学生「生き埋め」事件(1989)
神戸高塚高校「校門圧死」事件(1990)
兵庫県立農業高校不正入試事件(1991)
神戸高専「エホバの証人」事件(1991)
風の子学園事件(1991)
龍野市体罰自殺事件(1994)
大島南高校飛び込み事件(1995)〔ほか〕
著者等紹介
柿沼昌芳[カキヌママサヨシ]
1936年生まれ。元東京都立高校教諭。現在、全国教育法研究会会員、明治大学・中央大学などの非常勤講師
永野恒雄[ナガノツネオ]
1949年生まれ。都立大崎高校教諭。全国教育法研究会会長、日本教育法学会理事、歴史民俗学研究会会員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。