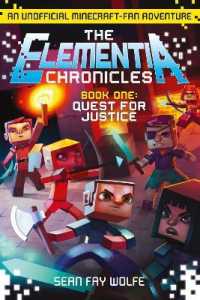出版社内容情報
★あなたの「対話」、この一冊で変わります★
●なぜ、「対話」が困難を抱える人のケアの助けになるのか?
支援に携わる専門職にとって、「聞く」と「話す」は基本中の基本です。しかし、時に言葉がかみ合わず、それが致命的なすれ違いを生んでしまうこともあります。正しい対話の仕方を意識することによって、ケアを必要とする人の支援の糸口を見出す手がかりとなります。
本書第1章では、対話を単なるコミュニケーション技術ではない「主観と主観の交通」と定義し、支援場面で陥りがちな落とし穴について指摘します。そのうえで、対人援助に欠かせない対話の「原則」と「型」に触れ、支援の土台となる対話の根本的な考え方を深めていきます。
●対話場面を丁寧に掘り下げた解説
第2章では、業務範囲を超えた支援や高圧的な上司、利用者不在のカンファレンス、貧困妄想のある利用者への対応など、支援場面における対話の進め方をリアルな事例で解説しています。
さらに、第3章では、対話の始め方・終わり方、感情的なやり取りへの対処、消極的な参加者の巻き込み方といった実践的なFAQを幅広く取り上げています。
すべての対人援助職が安全かつ効果的な対話を実践するための本質的な考え方と具体的な方法を1冊にまとめた必携の書です。
【主な目次】
Chapter 1 対人援助職としての対話とは
01 対話とは何か
02 コミュニケーション技術と対話の違い
03 人は対話が下手になる(内側と外側の言葉は一致しなくなる)
04 知らずに声は封殺される―権威勾配
05 透明性を意識する
06 対話が促進されやすい3つの「原則」
07 対話の安全性を担保する5つの「型」
Chapter 2 場面別の対話
01 支援を共に考える対話
Case #01: 業務範囲を超えた個人の善意で支援が成り立っている
02 管理者とチームの対話
Case #02: 高圧的な上司への不満が募り、職場の雰囲気がギスギスしている
03 利用者支援における対話
Case #03: 利用者の状態がよくない状況での利用者不在のカンファレンス
Case #04: 家族の関与が過剰になり、利用者にとってつらさが増している
04 リフレクティングによる対話
Case #05: 貧困妄想により暖房を拒否するうつ病の利用者
Chapter 3 対話実践で困ったときのFAQ
01 対話を円滑に行うために
02 こんなときどうする?
03 チーム内での対話について
04 利用者支援における対話について
05 リフレクティングについて
【目次】
内容説明
対話が続いてさえいれば、何とかなる!その人には、まだ、話せていない思いがあるかもしれない―対話を続けるために大切なこと―
目次
1 対人援助職としての対話とは(対話とは何か;コミュニケーション技術と対話の違い;人は対話が下手になる(内側と外側の言葉は一致しなくなる)
知らずに声は封殺される―権威勾配
透明性を意識する
対話が促進されやすい3つの「原則」
対話の安全性を担保する5つの「型」
対話の原則・型一覧)
2 場面別の対話(支援を共に考える対話;管理者とチームの対話;利用者支援における対話;リフレクティングによる対話)
3 対話実践で困ったときのFAQ(対話を円滑に行うために;こんなときどうする?;チーム内での対話について;利用者支援における対話について;リフレクティングについて)
著者等紹介
小瀬古伸幸[コセコノブユキ]
訪問看護ステーションみのり副社長(広報戦略担当)。精神科医療や福祉に貢献する研修・コンサル事業を行うTOKINO AIMS株式会社取締役。精神科単科病院勤務後、2014年、訪問看護ステーションみのり入職。2016年、訪問看護ステーションみのり奈良を開設し、所長として勤務。2019年、同法人にて統括所長に就任。2025年3月より現職。精神科認定看護師、WRAPファシリテーター、Family Work Practitionerを取得。精神医療分野における在宅医療の実践はもちろん、多数の執筆、研究実績あり。現在は訪問型の家族支援に力を注いでいる。Youtube「TOKINOチャンネル」、X、(旧Twitter)で支援に役立つ情報を配信中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme
hirokoshi