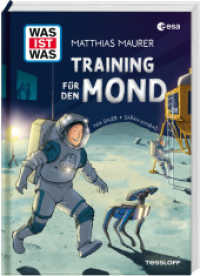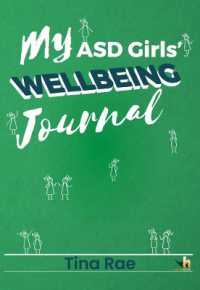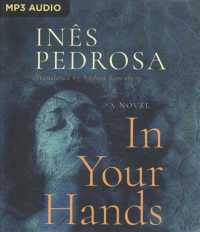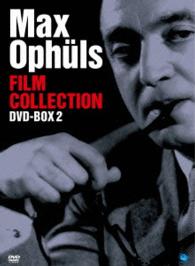出版社内容情報
■人間以外の動物について知ることは、人間について知ることそのもの!!■
【動物園社会も少子高齢化中!】
旭山動物園を一躍日本一にした元園長が、動物のすごさを魅せる行動展示の先に辿りついた、動物のウェルビーイングとは? 老い方と死に方に執着する日本人がぜひ知っておきたい、「ただ、生きて、死ぬ」動物たちの世界。
・座布団を用意して、歯科検診を待つ協力的なオランウータン
・柵から落ちた人間の子供を抱きかかえるゴリラ
・仲間の出産を超音波でサポートするゾウの群れ
・四季を人工的につくり、ヒグマの子作りを促す
・水を怖がるスカンクの子供にプールで泳ぎを教える
■動物園ぐらし50年のベテラン獣医が伝える、裏側(バックヤード)で起きる種々のケア■
【目次】
<第1章 未来より今を生きる動物>
動物の生きる目的/生きるために食べる/食べてはいけないもの/誰の子でも自分の子/「托卵」という/命をつなげなかった反省/ゾウの群れの最小単位/ゾウの出産の砂かけ/子はかすがい/生き延びるために一夫多妻/繁栄する群れ/子だくさんとヒエラルキー/老化しないネズミ/コミュニティで育てる/無駄と遊び
<第2章 動物の老い 寿命と延命>
動物の寿命/高齢化社会/人間の余生/野生動物の認知症/動物の睡眠時間/老いと孤独/動物の最期/「死」という概念/静かに死ぬ/嫌われ者の獣医/「泣く」と「鳴く」/サケの遡上
<第3章 ケアをする動物 そして人間>
動物同士のケア/甘い関係/種を越えたケア/チンパンジーの利他行動/シカの産後ケア/障害のある動物/「異端」と「個性」/群れの中で看取り/動物園での看取りケア/「安楽殺」という選択/最高齢のカバ/自分の手の中で動物に死んでもらう/動物園の弔い
<第4章 らしさを引き出すケア>
介護する動物/笑いとケア/言葉と引き換えに失ったもの/動物園で暮らす動物のQOL/環境エンリッチメント/ヒグマに四季をつくる/飼料の栄養計算/動物に協力してもらう健康診断/動物が生き生きと暮らす環境/ボルネオの森/あえて楽をさせない/長老の知恵/?む力は生きる力そのもの/スキャフォールディング/人だけが介護をする理由
著者情報:小菅 正夫 (こすげ・まさお)
獣医師。札幌市環境局参与(札幌市円山動物園担当)、旭川市旭山動物園元園長。北海道大学客員教授。国立動物園をつくる会代表。北海道札幌市出身。北海道大学獣医学部卒業語、1973年に旭山動物園に入園。飼育係長、副園長などを経て、1995年に園長に就任。一時は閉園の危機にあった園を再建し、日本最北にして“日本一の入場者を誇る動物園”に育て上げた。2004年には「あざらし館」が日経MJ賞を受賞。2009年に同園を定年退職後、名誉園長となる。2015年には、札幌市円山動物園のアドバイザー(参与)に就任し、現在に至る。
内容説明
旭山動物園を一躍日本一にした元園長が辿りついた動物のしあわせとは?動物園社会も少子高齢化中!動物園ぐらし50年の獣医が動物から学んだ―私たちと違う、「老い方」と「死に方」
目次
第1章 未来より今を生きる動物(動物の生きる目的;生きるために食べる ほか)
第2章 動物の老い 寿命と延命(動物の寿命;高齢化社会 ほか)
第3章 ケアをする動物 そして人間(動物同士のケア;甘い関係 ほか)
第4章 らしさを引き出すケア(介護する動物;笑いとケア ほか)
著者等紹介
小菅正夫[コスゲマサオ]
獣医師。札幌市環境局参与(円山動物園担当)、旭川市旭山動物園元園長。北海道大学客員教授。国立動物園をつくる会代表。北海道札幌市出身。北海道大学獣医学部卒業後、1973年に旭山動物園入園。飼育係長、副園長などを経て、1995年に園長に就任。一時は閉園の危機にあった園を再建し、日本最北にして“日本一の入場者を誇る動物園”に育て上げた。2004年には「あざらし館」が日経MJ賞を受賞。2009年に同園を定年退職後、名誉園長となる。2015年には、札幌市円山動物園のアドバイザー(参与)に就任し、現在に至る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
清掃員·D
young
Go Extreme
takao
ペコリーナ