出版社内容情報
「文学の革命」と「社会の革命」を目指し、戦後文学を牽引した文学運動60年のエッセンス。焦土から重い出発を遂げたはずの日本文学は、いま、奇妙なケバケバしさに包まれている。新しい出発のため、戦後の精神に立ち返る里程標。
"はじめに/鎌田慧
歌声よ、おこれ──新日本文学会の由来/宮本百合子
第三十六号/野間宏
ちっぽけなアヴァンチュール/島尾敏雄
嘘と文学と日共臨中/なかの・しげはる
組織と人間と方法──被害者と加害者/菊池章一
「共産主義者」ホセとの対話/花田清輝
旅にて/吉田欣一
闇黒を這ふ唄/金子光晴
狼がきた──現代詩の方向についての感想/関根弘
創刊百号記念号 目次
ヒロシマ十年/中島斌雄
秋/石塚友二
秋/大野林火
柱の傷/加藤楸邨
今井橋附近/石田波郷
不信の世/橋本夢道
基地の杭/栗林一石路
杵島炭礦/榎本冬一郎
苦境/斎藤喜博
今日につずく日/信夫澄子
颱風の前/近藤芳美
秋の草々/小野十三郎
かくされた村へ/黒田喜夫
沖縄の古謡──オモロについて/西郷信綱
ゾーッとする話/神田貞三
或る時代の雰囲気/埴谷雄高
ある日ある時/佐多稲子
ファンキー・ジャズ デモ/小関智弘
コイナさん談義/ベルトルト・ブレヒト(長谷川四郎訳)
ジャンケンポン協定/佐木隆三
猪/江原光太
新日本文学会第十一回大会/長谷川四郎
原初的条件/藤田省三
まぐろときれいな汽車/向坂唯雄
皇族駅/長谷川龍生
鼎談 常陸坊海尊は生きている/秋元松代・花田清輝・広末保
シジミ/石垣りん
対馬・樫根部落の人びと──公害問題をめぐる奇妙な現象/鎌田慧
ぼくのマザア・グウス/菅原克己
常識外記/国分一太郎
月並み常套句と金芝河/井上ひさし
反戦川柳人鶴彬の記録と一叩人命尾小太郎/秋山清
未整理の断想──新日本文学会創立三十周年/中島健蔵
30周年記念号 目次
桃栗三年──飛ぶ鳥跡をにごす/石田郁夫
小野二郎よ、安らかに眠れ!/久保覚
対談 歴史からみた天皇制
網野善彦/広末保
新日本文学会の半世紀/小沢信男
「大衆的な芝居という高望み」の時代──一九七〇年前後/津野海太郎
私の徒弟時代──新日本文学会の頃/辻井喬
一九五〇年まで/久保田正文
一九五五年の曲り角/田所泉
「小説の終わり」とその周辺──小沢信男論/野呂重雄
六十年近くの読者として/鶴見俊輔
本誌終刊と会解散の責任者として/針生一郎
新日本文学会の解散/永尾眞
言葉の路地/土方鐵
講道館時代のこと、など/栗原幸夫
あとがき/佐藤修
コラム
コラム
新日本文学会の「創立大会」/一九四〇年代の創作欄
「五〇年問題」
新風と屈折
一九五〇年代の創作欄/詩 短歌 俳句
記録芸術運動とエコール・グループの自由
「六〇年安保」と労働者の自己表現
「国際」という視点
「新日本文学賞」入選作一覧
日本文学学校の統合/一九六〇年代の小説から
日本共産党との袂別
新たな結合原理の模索/花田清輝のアプローチ
一九七〇年代以降のおもな作品
「思想運動」問題から創立三〇周年まで
「民衆文化」運動
季刊『新日本文学』/復刻縮刷版/「変革」と再月刊化
「解散」を決めるまで"
はじめに 鎌田 慧
今日はわざわざおこしいただいてありがとうございます。いま紹介していただいたように、『新日本文学』最後の編集長ということとなりました。名誉なのか不名誉なのか、それはわかりませんが、ただぼくが編集長になったから雑誌がつぶれるんじゃないんでして、これは文学史的にもきちんとしておかないと困ります。ぼくが編集長になったから赤字になって雑誌がつぶれるんじゃなくて、雑誌がつぶれるのが決まってから、編集長を押しつけられまして、それで先輩の初心といいますか、遺訓といいますか、その精神を継いだ雑誌になんとかもどす形で閉めたいっていう、いわば死化粧を施すお葬式担当みたいな感じでおります。
新日本文学会はご存知のように一九四六年の一月に創刊準備号をだしまして、四六年の三月に創刊号を発刊致しました。ですから、ちょうどこの三月でまる六十年、まさに命運尽きて消えるっていう日であります。そういう時に集まっていただきまして、本当に故人も喜んでおると思います。
創刊準備号はご存知のように、宮本百合子さんの「歌声よ、おこれ」という呼びかけから出発しています。これは「全く新しい社会各面の人々の心の声を誘い出し」て、雑誌を創っていこうっていう精神でして、もちろんそれはなんどもなんども討論して準備された雑誌でしょうから、新日本文学をつくる先輩たちの初心といいますか、想いだったと思います。
宮本百合子さんは、「翔望」という言葉を使ってまして、未来にむけて翔んでいく想いで、創刊準備号が発行されました。
その号にはもちろん、中野重治さんもお書きになってまして、中野さんは「書け、その堰を切って落とせ」と書いてます。これは、「小説を書けない小説家」だったのが、敗戦になって新しい時代をむかえ、ようやく書けるようになった、そういう風な想いをこめて、「堰をきって書け」と書いたのでしょう。
まあ、いずれにしろ、「文学の砦」、これは宮本百合子の言葉ですけど、文学の砦というような形で出発して、いま六十年をむかえて終焉、という感慨にとらわれています。もちろん、新日本文学会は戦後すぐ出発したとはいっても、たんに雑誌を創刊するっていうんじゃなくて、新しい民主主義の国を創っていくんだという、それを文学ではたしていこうっていう、そういう熱望があったと思います。
蔵原惟人さんが最初の編集長をやってますけれど、彼の規定の仕方は「封建時代を超えて民主主義」に行くという歴史観で編集するといってますが、戦後になって、封建制度から近代国家にむかう、そういうふうなところに文学運動の意図があったんじゃなくて、戦後民主主義革命を徹底していこう、社会を徹底的に変えていこうという、そういう想いや声を全国から集めてやっていこうというのが大方の気持だったと解釈しています。まあそれが、中野重治さんとか第二期の編集長の壺井繁治さんとかの創成期だったと思います。
そのあと、六〇年代の高揚期を迎えます。このころ新日本文学は長谷川四郎編集長で、「別冊新日本文学」(六一年七月)というのを刊行してます。別冊は二冊くらい出してつぶれましたが、はじめて新日本文学が原稿料を払った雑誌で、それも最後だったんですけど、そのころは「砦を守る」、ひとり孤塁守るっていう、そういう悲壮感じゃなくって、もっとそこからひろげていこう、ジャンルをひろげていこうという方向になっています。これらの別冊は、たとえば小説ですと、最初の、巻頭の小説が「アクチュアルな女」で、泉大八が登場します。野間宏、松本清張、水上勉、小林勝、黒井千次、富士正晴、久保田正文、長谷川四郎、この人たちが小説を書いてまして、座談会には「現代文学の可能性」というので、安部公房、石原慎太郎、大江健三郎。小林祥一郎さんが司会しています。それからもうひとつの座談会は、「天皇、ナショナリズム、伝統」というタイトルで、宮本常一、岡本太郎、日高六郎、花田清輝という人たちが集まって、いかに文化状況全般に、それも視聴覚文化もふくめて、攻勢を強めていこうか、そういう想いがよくこもっています。
六〇年代は新日文ばかりではなくて、文化的にものびやかな時代でして、いまは消滅したソ連にも、「黄金の六〇年代」というのがあったほどです。最近、六〇年代の回顧みたいなのがはじまってますが、新日文もすごく豊かな可能性をもっていた時代だったと思います。六〇年安保闘争から一〇年たって七〇年安保闘争になったのですけれども、そのころはぼくもずっと編集委員に加わっていました。たとえば、三里塚闘争、沖縄闘争、被差別部落の運動とか、あるいはアジア・アフリカへの視野とか、そういう運動の総合雑誌としての機能を発揮していた雑誌だった、と思います。
実はぼくが新日文に入ったのは、学生のころから花田清輝さんの大ファンだったからですが、学生のころからこの雑誌はずうっと読んでいて、六〇年代後半、都電撤去問題などなん本かのルポルタージュを寄稿して、七〇年代はじめころに入会したと思います。このあと、新日本文学会の会員を中心に、三里塚「廃港要求宣言の会」っていう団体が組織されて、その事務局を会の事務所に置き、ぼくが事務局長をやらされていました。そういう意味で、戦後民主主義っていうよりは、七〇年代を経由したあとは、もうすこしラディカルに、いままでの旧左翼っていう感じじゃなくて、もっと幅のひろい、いろんな市民運動や住民運動と共闘していこうという、そういうのが七〇年代の新日本文学会の運動だったと思います。
いつも事務局には、若い人たちが集まっていました。事務局長の石田郁夫が煙草を横にくわえて椅子に立て膝で坐ってホラを吹いていて、電信柱に文学学校のポスターを貼ったりとか、集会を準備するとか、講座をひらくとか、文学学校の生徒や卒業生たちが中心になって活動していました。これが、花田清輝のいっていた、「文学活動家」というものの具体的な表れだったと思います。
新日本文学会には日本共産党のイメージが強かったんですけれど、それは六〇年代には完全に払拭しました。払拭っていうか、無関係になってました。これには六〇年安保闘争をめぐる総括もあったし、ソ連の核実験の問題もあったし、チェコの六八年の「プラハの春」にたいする問題もありました。いままでの古いコミュニズムでは対応できない時代に入ってました。新日本文学会の有志は、「さしあたってこれだけは」という形で、第八回共産党大会にむけて批判の「意見書」を出して除名処分になっています。六〇年の安保闘争を経たあとに、新日本文学会は共産党の運動から自律した文学運動体となり、だからこそ、いままで存続してきたのです。
政治と文学の関係でいいますと、戦後の出発以来、党員作家が多かったこともあり、共産党が直接支配する傾向とのたたかいでもあったのです。が、ようやく六〇年安保闘争を経たあと、共産党と決別して、労働運動ばかりか、市民運動や住民運動とともにある、という形で運営されてきました。夜の文学学校にやってくるひとたちのエネルギーを受けて、活性化したのです。
いま、この時代、もっとも新日本文学の運動が必要な時期になってきていると思います。大資本によるマスコミには、もともと資本への批判というのは弱いのですが、ジャーナリストや物書きもいまの政治状況に対して、あるいは憲法改悪の動きにたいして、きわめて力弱い存在になってます。そういう状況の中で、戦争にむかって進んでいく状況の中で、文学運動を標榜する新日本文学会こそ、きちんと旗印を掲げ、さまざまな表現を駆使して対抗していく時期なのですが、残念ながら、すれ違いといいますか、こちらの方は息も絶え絶え、衰弱して消えてしまう。皮肉というか、とても残念なめぐり合わせで、これまでささえてきた先輩に申し訳ない、という気持があります。
先輩といいますと、もちろんそれは、すでに他界した中野重治、花田清輝、野間宏、長谷川四郎、佐多稲子、野間宏、杉浦明平と、数えられないほどさまざまな人たちが、それこそ運動としてつくりだしてきたものなんですね。そういう先達、敬愛する先輩がつくってきた運動に、ここでさらにエネルギーを継ぎたして、この状況にむかっていかなければならない時なのに、おのれの拙なさから消滅してしまう。非常に残念な気持でいます。
新日本文学会の運動というのは、文章によって、あるいは文学の力によって状況に対峙しよう、状況を切り拓いていこうという運動であったし、さらに活字ばかりではなく、あらゆるジャンル、映像や演劇や音楽の運動をもふくめた、いろんなかたちの総合的な運動としてやっていく、というような方向性を孕んでいたはずです。花田清輝がいいつづけていた、文学の大衆化、総合化、あるいは共同制作とか、いろんな課題を彼は提起したわけですけど、わたしたち後輩は、さらにいろんな人たちと手を結んで、時代の気分に対峙するようなものをつくっていくべき、もっとも重要な時期であると思います。
しかし、たしかに雑誌はなくなりますけど、そこで培ってきたものというのがあるわけでして、それをこれからどういう形で伝えていくのかというか、ということが問われていると思います。この重要な時代に、ぼくたちの表現の場であり、抵抗の場である雑誌を衰弱死させてしまったのです。最終号の編集後記でちょっと厳しく書きまして、物議をかもしているわけですが、会員の中に運動の意志が弱くなってしまった、大胆に外にむかって働きかける能力も意志もなくなっていたのです。
これは自己批判をこめていってるのですが、取材で外に出歩くことが多く、ぼく自身もマスコミの方に吸収されていまして、ほかの運動にはいくつかクビを突っこんでいましたが、新日文の運動の方が留守になってしまった。それを、ぼく自身は悔やんでいるのです。最後のこの二年間はそれなりにやりましたけど、もっとはやくからテコ入れというか、まあテコ入れなどというとこれまでやってきた人たちに申し訳ないんですけれども、いまの状況を迎え撃つような編集体制をつくるために、なんらかの時間とエネルギーを割いておけばよかった、という自責の念があります。
もうひとつは、新日本文学の運動としては、これは花田清輝さんの「功罪」のひとつでもあるんですけど、インパーソナルな運動ってことを盛んにいってまして、彼の有名な「心臓は犬にくれてやった俺ではないか」という文言がありまして、個人的なパーソナルな関係で運動をやっていくのではない、うじゃうじゃした、うじゃけた精神で個人的に関与していくんじゃなくて、運動的に関わっていくっていう彼のテーゼが、あまり個人的に親しくならないようにというブレーキになっていたようなキライがあります。
運動は人間関係だけでやっていくと、どうにも馴れ合いになってしまう、そうじゃなくて、素知らぬ振りのインパーソナルな関係で全部説いていくスタイル、それがたぶん花田テーゼの影響だったと思うんですけれども、そういう個人的な結びつきがかなり弱かったんじゃないかという気もしてます。
今日は「新日本文学会」最後の会合でして、これからわたしたちはどっかに飛び散っていくわけなんです。しかしまだまだやるべきことは残されています。それをどういうふうに受け止めていくのか、それを個人個人でもう一度胸に落として、次のことにむかっていかなくてはいけない、そういうふうな集会になっていければと思います。
まあ、あまり政治的な話をしてもしょうがないんですけど、改憲問題がいま大きく動いてまして、これは労働運動の衰退化とかなり強くからみあってます。つまり、総評の「連合」化という形になりまして、政治的な課題を労働運動が引き受けていく、ゼネストの方向が全部否定されてしまったと思います。そういう労働運動の政治的問題、ひいては職場闘争という、職場の中に根っこを据えた運動をつくっていこう、というところから、サークル運動とか、地域の文化運動とかのいろんな表現が生まれてきたわけですけれども、経済的な高度成長と「繁栄」とそれをささえた企業意識がその根っこのところで、他者と連帯する意識と運動とを全部切ってしまったのですね。
それでも、各課題をかかえた市民運動は、それぞれの地域で、それぞれの人々が、それこそ裸足で飛びまわってるって形で残されています。このような社会状況の中で、たしかに、いま一つの雑誌が消えますけど、もう一度文学とはなんであるのか、あるいは文学によってなにができるのか、その根本的な課題を、解散を契機にして考えさせられてます。
なぜ解散することになったのか、結局、やり残したこと、できなかったこととはなんであったのか、いろんな宿題を残しながら、今日の解散集会となったのです。
まあ、それはともかく、ここに新日本文学の60年の作品のいくつかを集めてあります。どこからでも、お読み下さい。
内容説明
文学になにができるのか。「文学の革命」と「社会の革命」を目指し、戦後文学を牽引した文学運動60年のエッセンス。焦土から重い出発を遂げたはずの日本文学は、いま、奇妙なケバケバしさに包まれている。新しい出発のため、戦後の精神に立ち返る里程標。
目次
歌声よ、おこれ―新日本文学会の由来
第三十六号
ちっぽけなアヴァンチュール
嘘と文学と日共臨中
組織と人間と方法―被害者と加害者
「共産主義者」ホセとの対話
旅にて
闇黒を這ふ唄
狼がきた―現代詩の方向についての感想
創刊百号記念号 目次〔ほか〕
-

- 電子書籍
- 漆黒のガヴァネス~婚約破棄?では復讐さ…
-

- 電子書籍
- ロゥブルーの標本 分冊版(3)
-
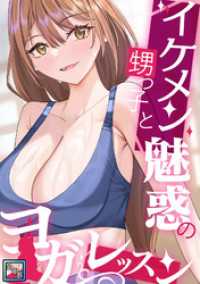
- 電子書籍
- イケメン甥っ子と魅惑のヨガレッスン【全…
-
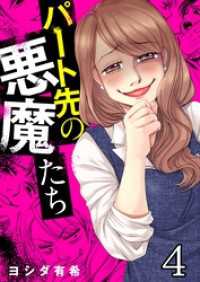
- 電子書籍
- パート先の悪魔たち(4) ブラックショ…
-

- DVD
- 清左衛門残日録(新価格)



