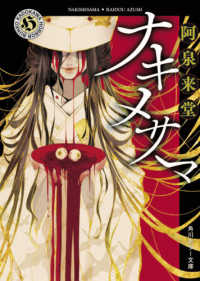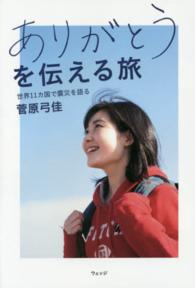出版社内容情報
7万部突破! 『仕事が速いのにミスしない人は、何をしているのか?』の著者が贈る
あなたの仕事の
「スピード」×「質」×「評価」を
最大化する失敗の活かし方
「ミスや失敗が汚点となって、うだつが上がらない人」と
「ミスや失敗を乗り越えて、メキメキ評価を上げていく人」には、
明確な差がありました!
「ミス・失敗」は、その扱い方を変えるだけで、
あなたと職場の分析力・計画力・学習力・伝達力が上がります。
本書では、その方法を、わかりやすい図を用いて紹介します。
「やばい?」「しまった?」を、最高のチャンスに変える仕組みを、
今すぐ、日々の仕事に取り入れましょう。
★本書は、こんな人によく効きます★
・「この人に任せれば間違いない」と評価されたい人
・臨機応変な対応力を身につけたい人
・立場上、ミスをミスのまま終わらせるわけにはいかない人
・トラブルがあると、すぐに動揺してしまう人
・ケアレスミスが多く、叱られがちな人
・仕事を通して自分自身が成長できているのか、不安のある人
――失敗やミスに、「正しく対処」するだけで、
あなたの評価がガラリと変わる。
内容説明
「やばい!!」「しまった!!」が最高のチャンスに変わる。分析力、計画力、学習力、伝達力をたちまち上げる「ミス・失敗」の扱い方。
目次
はじめに「ミスしたのに、評価が上がる」仕事術
1章 ミスしてしまったとき、「評価される人」はこう対処する
2章 だから、乗り越えた先に「急成長」が待っている
3章 問題点をピンポイントで見抜く―ミスを通して「観察力」「分析力」をつける方法
4章 「圧倒的な結果」を生み出す「計画の質」の高め方―ミスを通して「計画力」をつける方法
5章 「何歳になっても成長し続ける人」は何が違うのか?―ミスを通して「学習力」をつける方法
6章 仕事をスピードアップでき、関係性までよくなる「伝え方」―ミスを通して「伝達力」をつける方法
7章 「どんなうっかり者でも、うっかりできない」仕組みをつくる―ミスを通して「注意力」を見直す方法
8章 なぜ「ミスを正しくシェアする」だけで、あなたの評価が上がるのか?―ミスを通して、組織と人を育てる方法
著者等紹介
飯野謙次[イイノケンジ]
スタンフォード大学工学博士。東京大学特任研究員。失敗学会事務局長。1959年大阪生まれ。東京大学大学院工学系研究科修士課程修了後、General Electric原子力発電部門へ入社。その後、スタンフォード大で機械工学・情報工学博士号を取得し、Ricoh Corp.へ入社。2000年、SYDROSE LPを設立、ゼネラルパートナーに就任(現職)。2002年、特定非営利活動法人失敗学会副会長となる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
assam2005
ニョンブーチョッパー
チャー
Yoshie S
-

- 電子書籍
- ふたりの千佳~完璧な彼女には秘密があり…
-
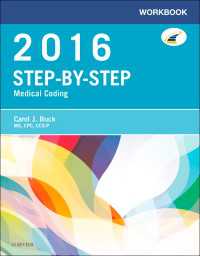
- 洋書電子書籍
- Workbook for Step-b…