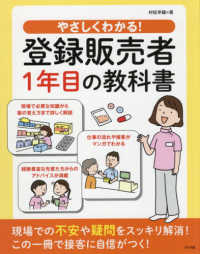内容説明
「早期教育」「1万時間の法則」「グリット」にだまされるな!最新研究で読み解く、不確実性の高い現代で成功する方法。
目次
はじめに タイガー・ウッズvsロジャー・フェデラー
早期教育に意味はあるか
「意地悪な世界」で不足する思考力
少なく、幅広く練習する効果
速く学ぶか、ゆっくり学ぶか
未経験のことについて考える方法
グリットが強すぎると起こる問題
「いろいろな自分」を試してみる
アウトサイダーの強み
時代遅れの技術を水平思考で生かす
スペシャリストがはまる罠
慣れ親しんだ「ツール」を捨てる
意識してアマチュアになる
あなたのレンジを広げよう
著者等紹介
エプスタイン,デイビッド[エプスタイン,デイビッド] [Epstein,David]
アメリカの科学ジャーナリスト。ネットメディアのプロパブリカ記者、元スポーツ・イラストレイテッド誌シニア・ライター。同誌でスポーツ科学、医学、オリンピック競技などの分野を担当し、調査報道で注目を集める。記事の受賞歴も多い。コロンビア大学大学院修士課程修了(環境科学、ジャーナリズム)
東方雅美[トウホウマサミ]
翻訳者、ライター。慶應義塾大学法学部卒業。米バブソン大学経営大学院修士課程修了(MBA)。日経BPやグロービスなどでの勤務を経て独立(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Carlyuke
63
忙しかったので時間がかかった。ビル・ゲイツからとQuoraで続けて推薦されている本であったのが読むきっかけ。最近の読書で同じ概念を読んだ覚えがあった。その時はある分野の概念は別の分野に応用可能であるということ。 この本からは専門分野だけに集中するより様々な経験や分野を行き来することの方が発想が豊かになれるということ。面白いし, 確かにそうかなと思う。良書なのでまた読みたい。例によってアメリカ人の著す本らしく十分な実例が多数出てくる。主張をきちんと裏付けるためのルールのように捉えられているのかなと思う。2021/03/15
R
59
様々な知識の組み合わせがイノベーションの原動力になる、それを支持する内容でした。いわゆる1万時間の法則とか、早い内に専業化したほうがよいといったことへの反証と、実際にあれこれやってきた集大成的に成功した例を挙げていて興味深かった。結局何かをするという攻略法があるわけではなく、そういった知識をどのように獲得するか、どう利用するかといったところに才能があれば成功するということだと思われる。応用力ということでもあろうが、何事も何か一辺倒でできるものではないな。2021/03/08
かおりんご
38
自己啓発本。んんー、なぜこの本を読みたかったのか、全く覚えてないけれど、結論「めちゃ読みにくかった」です。簡単に言えば、回り道に思えることも、その人の幅となり強みとなるということでしょうか。スペシャリストより、ゼネラリスト、、、自分の今の仕事も、この先どう転ぶか分からんよね。2022/11/23
りょうみや
34
スペシャリストよりもジェネラリストを勧めているわけではなく、ただ一直線に目的に向かう「早期教育」や「効率性」重視の風潮に一石を投じている。人生における「寄り道」や「試行錯誤」で経験の幅を広げておくことが最終的には何かの専門家になるにしても重要だし、実際にその道で成功する人は多いことを言っている。巻末に「学力の経済学」で有名な中室牧子氏の解説があるが、エビデンス重視、すなわち効率性重視となりやすい教育に中に、なかなか結果を示しづらい「寄り道」教育を取り入れることの難しさを語っている。2020/07/12
こばたく
28
【変化の激しい現代の荒波を生き抜くバイブル。】 なぜ多様性が重要視されてるか、あなたはその本当のご利益を知っていますか?【1つの分野で深い知見を持つ人材と、幅広い分野に知見を持つ人材。】組織には両者欠かせないが、その天秤は大きく傾きつつある。デジタル化による情報共有の円滑化により、あらゆる分野の知識を持つことが容易になった。その結果、知見の融合が加速した現代。そこで、複数の分野の知見を持ち、知見を融合できる人材の重要性が高まった。数多くの研究結果と成功者への取材に基づく、現代社会で生き抜く指針を示す一冊。2021/08/20
-

- 和書
- 理工系微分積分