内容説明
驚異のベストセラー「プログラムはなぜ動くのか」第6弾。登場から10年、誰も書かなかったJavaの本質を解き明かします。
目次
第1章 Javaとはそもそも何か
第2章 すべてのハードウエアを同じに扱う
第3章 すべてのOSを同じに扱う
第4章 言語仕様、実行環境ともにオブジェクト指向を追求
第5章 メモリー管理を自動化する
第6章 企業システムに必要な機能を搭載
第7章 オープンテクノロジーである意味
第8章 Javaが本当に目指すもの
著者等紹介
米持幸寿[ヨネモチユキヒサ]
1987年、日本アイ・ビー・エム株式会社入社。入社当時は、カスタマーサービス部門にて、メインフレーム系OSであるVSEやVMのソフトウエア障害担当エンジニアとして昼夜を問わず16進数のダンプアウトとネットワークトレースを解析し、アセンブラのソースコードを追跡する毎日であった。障害解析ソフトウエアや、自動運用ワークフロー・システムの開発を通じてソフトウエア開発を経験。Webシステムの構築プロジェクトにも複数参加し、オープンシステムやオブジェクト指向開発を経験。2000年6月にソフトウエア事業部に移籍。Java、XML、EJBなどそのときどきの最新テクノロジーを啓蒙するエバンジェリストとして活動中
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
baboocon
8
超速読で読了。Javaがなぜ普及したのかを解説しているが、要はマンセー本のような。最近の状況は詳しくないけど、Androidアプリ開発で需要は根強くなんだかんだJavaできれば食ってけるって感じなのだろうか?2016/12/31
Kazuya
5
恥ずかしながらJavaとはプログラム言語のひとつだと思っていた私です。でも本書を読み終えていろいろ理解することができました。世の中には沢山のプログラム言語があるわけで、それぞれに良し悪しや向き不向きがあると。それが時間とともに進化したり統合したり淘汰されたり。生物多様性にも似た...そう、歴史絵巻を読み解くような感覚を覚えました。202014/01/13
roughfractus02
4
RubyやPHPでなくなぜJavaなのか?という問う読者を想定するように、著者はJavaを実行環境という観点で、その歴史と有用性を概説する。専用ハードウェアと専用ソフトウェア競争に始まるコクピュータ開発史は、プログラミング言語においては汎用性を求め、アセンブラ、コンパイラ、インタープリタへと改善されて、OS上の仮想的なOS環境(JVM/Java Virtual Machine)を作ることで、個々のOSに依存しないJavaが出てきたとされる。非オブジェクト指向やJava以外との比較もほしい(2005年刊)。2018/03/21
常磐条(ときわとおる)
4
Javaによってプラットフォームの違いを乗り越えて永く使われるプログラムを作成することができること、C言語と異なりメモリの利用に関するバグが減らせることなどが、仕組みの解説と共にわかりやすく書かれている。またなるほど、ゲーム開発のようにメモリ領域を厳しく節約しながらプログラムを走らせなければ行けない場合にはC言語を使う理由もなんとなくわかった。2013/08/21
朧月
3
古本で購入。 JAVAの歴史、取り巻く環境、利点を丁寧に説明し、JAVAの意味と意義について再確認する本。プログラムを再勉強しようと思って、読んでみた。 プログラム入門書ではなく(実際にコードの説明は一切ない)、あくまでJAVAとはどんなものなのかを説明する本です。どっちかというと雑学本のような印象を受けました。 プログラムを書かない人でも、世の中でのプログラムの歴史や動きを知るための本としては良いと思います。一気読みだと後半はちょっと読み飛ばし気味でしたが……。2015/03/28
-
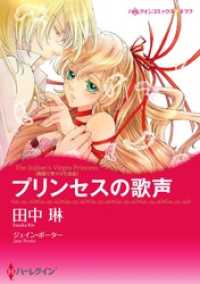
- 電子書籍
- プリンセスの歌声〈異国で見つけた恋 I…








