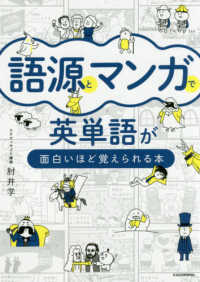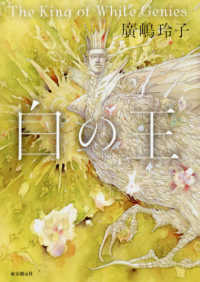- ホーム
- > 和書
- > 経営
- > マーケティング
- > マーケティングその他
内容説明
今、知っておくべきデータ活用の基本。多彩な31事例収録。
目次
第1章 日本航空が挑んだデータ分析プロジェクト
第2章 データに語らせる
第3章 顧客は意外なきっかけで動く
第4章 データ分析の効果を捉える
第5章 顧客化力10の発見
第6章 データ分析は思考力・チーム力でライバルの先を行く
著者等紹介
大木真吾[オオキシンゴ]
株式会社博報堂プロダクツダイレクトマーケティング事業本部データベースマーケティング部部長。シニアデータベースマーケティングディレクター。1974年札幌生まれ。東洋大学卒。空間ディスプレイ・内装会社、セールスプロモーション会社等を経て、2005年より博報堂グループに参加。主に営業・施策プロデュースに従事し、2007年から現事業本部にて様々な業種の「戦略設計から実施まで」を対応。ダイレクトマーケティングをベースとした店舗送客・通販・CRMなどのコミュニケーション立案が専門であり、データ分析による「買われ方の可視化」を根拠に戦略設計・PDCA推進に力を入れている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。