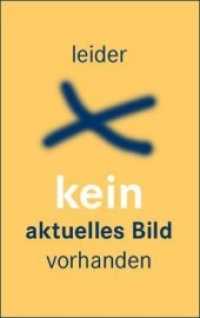内容説明
業務を3タイプに分類すると、(A)感覚型:経験や知識から高度に判断。(B)選択型:一定のパターンから選択。(C)単純型:誰がやっても同じ。チームの生産性はもっとアップする。
目次
第1章 「働き方改革」の理想と現実
第2章 生産性とは何か
第3章 業務の「仕組み化」とは
第4章 仕組み化の実践:見える化
第5章 仕組み化の実践:標準化とマニュアル化
第6章 仕組み化の実践:ツール化と事例
著者等紹介
庄司啓太郎[ショウジケイタロウ]
株式会社スタディスト取締役COO。東京工業大学卒。国内シンクタンクにて、都市計画等の調査業務に従事。その後、株式会社インクスにて、設計支援システム導入や、製品開発プロセス改革、業務分析のプロジェクトリーダーを歴任。同社マネージャー職を経て、2011年1月インクスを退社。同年2月に株式会社スタディストに参画。主に営業部門を統括し、業務効率化や生産性向上に関する講演等も多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっしー@challenge
1
人は良かれ(改善だ!)と思って品質や生産性を目的に仕事を増やす。その時点では必要であっても時間が立てば過剰で必要ない業務であったりする。やってる本人は必要だと信じて、誇りを持っていることもあるため、「その仕事ムダです」と頭ごなしに否定するアプローチはその人のモチベーション、自尊心を大いに傷付ける。見直しの際は"そもそもどうありたいか"の視点に立って共有することから。業務の分類は①経験やスキルから判断する感覚型②一定のパターンから選択する選択型③誰がやっても同じ単純型。比率はどこもだいたい①15:②③852020/05/05
ふーいえ
1
仕組み化できるのが8割。面白い推察。これから税理士なども不要になるんだろうなぁ。2019/01/11
Chie Azuma
1
勉強のため。 だいたいどの会社も、クリエイティブな能力が求められる仕事は10〜20%, それ以外は機械がやったって構わない仕事だということ。 でも現実は全部自動化するのは難しい。自動化の為のコストと、見返りのバランスを重視しよう。 大きな改革を目標としているが、やれることは目の前の小さな仕事一つ一つの改善。計画に時間をかけ過ぎず、サクッと試してからまた考えよう。2018/05/12
-
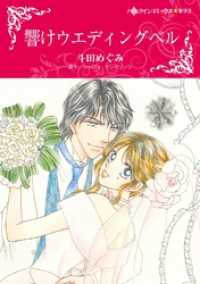
- 電子書籍
- 響けウエディングベル【分冊】 6巻 ハ…
-
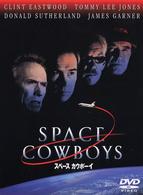
- DVD
- スペースカウボーイ 特別版