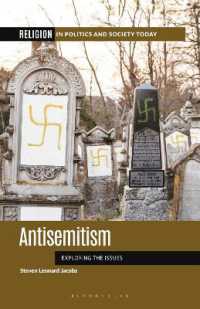出版社内容情報
注目のSDGsをビジネスの視点で解説。15の産業グループ別にリスクと機会を分析する。企業担当者、金融市場関係者必読の書。注目のSDGs(持続可能な開発目標)をビジネスの視点で解説。
15の産業グループ別にSDGsのリスクと機会を分析する。
企業担当者、金融市場関係者必読の書。
「企業はSDGsを経営にどう位置づけるべきか?」
「『17の目標への紐づけ』の先にあるものは?」
「なぜ投資家がSDGsに関心を示すのか?」
「SDGsからみる金融市場の未来とは?」――その答がここにある
2030年を目指した国連の持続可能な開発目標、SDGsが時代のキーワードになっている。
中期経営計画にSDGsを取り込む企業も登場した。
新規事業立案や企業価値向上にどのように生かしていくのか。
新たに登場したSDGs関連の金融商品など、ESG(環境、社会、ガバナンス)
投資との関係を明らかにしながら、企業の活用法を紹介する。
第1部は、SDGsの成り立ちや企業にまつわるSDGs推進の動きを解説する。
各業界の代表的な取り組みを紹介するとともに、SDGsの具体的な活用方法を探る。
既存の製品・サービスを棚卸してSDGsを経営に位置付けるとともに、
情報開示をいかに進めるか、将来の成長とリスク回避につなげるための考え方を紹介する。
そして、近年急拡大しているESG(環境・社会・ガバナンス)投資とSDGsとの
関係にも踏み込み、金融市場の今後の展望を明らかにし、さらに民間企業がESG投資を
呼び込むためのビジネスの展開方法を解説する。
第2部は「食品・飲料品」「建設・不動産」「鉄鋼・非鉄金属」
「機械・精密機械」「輸送用機器」など15の産業グループ別にSDGsに
取り組んだ場合の機会と、SDGsに向き合わなかった場合のリスクを分析する。
どのような分野にビジネス機会があるのかについても紹介する。
◆はじめに
◆本著の構成
◆第1部 ビジネスと金融からSDGsを読み解く
1.SDGsとは何か
(1)SDGs採択までの背景
MDGsからSDGsへ -普遍的な国際目標-/策定プロセスとステークホルダ/目標設定と求められるアプローチ方法/資金需要と期待される資金源
(2)SDGsと企業
SDGsのリスクと機会/企業行動指針‐SDG コンパス-/業界別取り組み事例集 -SDGs Industry Matrix-/企業によるSDGsの情報開示 - Business Reporting on the SDGs-/企業側のレスポンス
(3)日本におけるSDGs -政府と企業の動きを中心に-
日本のSDGs達成状況の評価/政府のSDGs実施指針、SDGsアクションプラン2018/なぜ政府がSDGsを進めるのか/
民間企業の現状認識 -経営陣に求められる理解促進-/経団連 -企業行動憲章の改定-/各ステークホルダーへの期待
2.金融市場とSDGs
(1)なぜ、投資家がSDGsに関心を示すのか
投資家からの高い期待/機は熟していた
(2)金融市場におけるカタリスト
気候リスクの主流化/グリーンボンド市場の成長/インパクト投資市場の成長
(3)SDGsから見た金融市場への期待
マイクロファイナンスによる金融包摂(SDGsターゲット1.4、8.10)/持続可能な農業・畜産業・漁業のための金融(SDGsターゲット2.c)/
農産物デリバティブ市場の機能(SDGsターゲット2.3)/女性活躍のための金融(SDGsターゲット5.a)/中小零細企業やベンチャー支援(SDGsターゲット8.3、9.3)/
送金コスト引き下げとフィンテック(SDGsターゲット10.c)/途上国におけるインフラ開発(SDGsターゲット9.a)/保険(SDGsターゲット3.8、8.10、11.b)
(4)意思を示す投資家、それに応える金融市場
投資家の視点:自分の勘定をどこに振り向けるのか/資産運用:商品・サービスとしての付加価値/
金融市場を後押しするステークホルダー:そして、メインストリームへ/資金調達手法の視点:色のついたお金のループ
(5)SDGsに貢献する金融市場となるために
責任投資原則によるSDGsの促進/ポジティブ・インパクト・ファイナンス原則の浸透/求められる投資効果:インパクト評価の普及/国を挙げた取り組み:オランダの例から
(6)SDGsからみる金融市場の未来
時間軸の悲劇を回避する/使途にこだわる投資家になる/インパクトを企業評価に反映する:三次元か、二次元か/持続可能性資本主義への挑戦
3.企業はSDGsをどう経営に位置づけるべきか
(1)日本企業にとって魅力的なSDGs
(2)SDGsが求めるマテリアリティ・配慮事項
自社のマテリアリティの考え方/SDGs達成に貢献する企業の取り組み類型と事例
(3)企業の取り組みへのヒント
自社の事業を17の目標に紐付けることの意義/既存の製品・サービスをたな卸ししてみよう(ロジックモデルの効用/インパクト評価を試みよう/
17の課題を表の右におくのか、左におくのか/内需中心の企業でも取り組みはできる/SDGsをバブルに終わらせないために
◆第2部 産業別・SDGsのリスクと機会
1.農林水産
2.食品・飲料品
3.建設・不動産
4.石油・化学
5.鉄鋼・非鉄金属
6.機械・精密機械
7.輸送用機器
8.医療
9.繊維・アパレル
10.生活資材
11.流通
12.エネルギー
13.運輸
14.観光
15.情報通信
足達 英一郎[アダチ エイイチロウ]
著・文・その他
村上 芽[ムラカミ メグミ]
著・文・その他
橋爪 麻紀子[ハシヅメ マキコ]
著・文・その他
内容説明
SDGs(持続可能な開発目標)達成のカギとなる、ESG投資の拡大、企業の最新動向を解説。15の産業グループ別に、SDGsのリスクと機会を分析。企業はSDGsを経営にどう位置づけるべきか?「17の目標への紐付け」の先にあるものは?なぜ投資家がSDGsに関心を示すのか?SDGsからみる金融市場の未来とは?―その答えがここにある。
目次
第1部 ビジネスと金融からSDGsを読み解く(SDGsとは何か;金融市場とSDGs;企業はSDGsをどう経営に位置づけるべきか)
第2部 産業別・SDGsを巡るリスクと機会(SDGs達成に向けた産業別取り組み;農林・水産;食品・飲料品;建設・不動産;石油・化学;鉄鋼・非鉄金属;機械・精密機械;輸送用機器;医療;繊維・アパレル;生活資材;流通;エネルギー;運輸;観光;情報通信)
著者等紹介
足達英一郎[アダチエイイチロウ]
株式会社日本総合研究所理事。一橋大学経済学部卒業。1990年日本総合研究所入社。経営戦略研究部、技術研究部を経て、現職。主に企業の社会的責任の観点からの産業調査、企業評価を手がける。2005年3月~2009年5月のあいだISO26000規格化作業部会日本国エクスパート
村上芽[ムラカミメグム]
株式会社日本総合研究所マネジャー。京都大学法学部卒業後、日本興業銀行(現みずほ銀行)で再生可能エネルギー分野のプロジェクトファイナンスに従事。2003年に日本総合研究所に入社し、現職。ESG投資や評価型融資向けの企業評価、気候変動リスクと金融、子どもの参加論などを手がける
橋爪麻紀子[ハシズメマキコ]
株式会社日本総合研究所マネジャー。上智大学総合人間科学部卒業後、NTTデータで交通・エネルギー分野におけるサービス企画に従事。その後、マンチェスター大学大学院国際開発政策研究院修士課程を修了、国際協力機構においてエネルギー分野の政府開発援助事業に携わる。2012年に日本総合研究所に入社し現職。ESG側面での企業評価、インパクト創出に向けた事業検討に従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
TATA
takam
にわ
MADAKI
裕樹
-
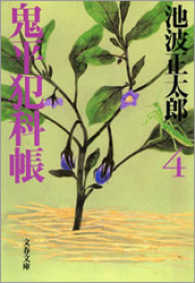
- 電子書籍
- 鬼平犯科帳 〈4〉 文春文庫