目次
まえがき 模倣のパラドクス
第1章 「天才のなぞかけ」―メタファーとイノベーション
第2章 「インドの露天商」―模倣すべき本質をモデリングする
第3章 「クロネコの革命」―4つの要素と5つのステップ
第4章 「2つのカフェ」―模倣の創造性
第5章 「4人の教師」―誰をどのように模倣するのか
第6章 「守破離」―手本と現実のギャップを越える
第7章 「わな」―模倣できそうで模倣できない会社
第8章 「反転」―逆発想のモデリング
第9章 「作法」―倣い方を倣う
あとがき 経営書を「消費財」で終わらせないために
著者等紹介
井上達彦[イノウエタツヒコ]
早稲田大学商学学術院教授。1997年神戸大学大学院経営学研究科博士課程修了、博士(経営学)。広島大学社会人大学院マネジメント専攻助教授、早稲田大学商学部助教授(大学院商学研究科夜間MBAコース兼務)などを経て、2008年より現職。2011年9月より独立行政法人経済産業研究所(RIETI)ファカルティフェロー、2012年4月よりペンシルベニア大学ウォートンスクール・シニア・リサーチフェローを兼務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
takam
15
イノベーションというと、どうも真似してはいけない創造的で崇高なことのような気がする。実際はイノベーションはNew Combinationであり、新しい結合であり、それは模倣が前提にある言葉なのだと思う。トヨタ生産方式もスターバックスも真似から入っていて、その真似から得られた経験を活かすことでより高度なシステムへと洗練することができる。日本も昔は模倣によって世界の製造業をリードしたが、今では模倣に対して変にプライドを持っているように見える。最初は模倣から始まり、そこから洗練されたサービスを作ることが大事。2020/02/26
kubottar
11
何事も模倣から始まる。しかし、尊敬できる人を真似るのは実は難しい、なぜなら人間としての地力がなければただの猿真似で終わってしまうからだ。模倣も1から10まで全て真似るのではなく、他の全く違う業種と組み合わせてみたり、自分の色を入れていく等その「先」を目指さなければならない。例外として公文式教室のようにマネようとしてもマネができない会社を目指すのが一番いいかもしれないが、難しいだろうな。2012/05/14
tkokon
7
【ふむふむ】「あなたは、トヨタから何を倣う?」「そうだろう。いろいろと倣うことができるから困惑するのも当然だ。模倣というのは実に創造的な行為だからね」確かにその通り。 ヨーロッパのカフェ文化をみた二人の人物が本書に登場する。一人は日本に持ち帰って「ドトール」を作った。一人はシアトルに持ち帰って「スターバックス」を作った。どちらも模倣からはじめて、新しい形に昇華させている。真似が出来そうでできない「公文」は未だに同じ業態でライバルと呼べる存在が無い。模倣は実に奥が深いのだ。2013/06/03
nizimasu
6
経営というのはつくづく模倣から入る守破離の世界などだと痛感する今日この頃。そんな時に我が意を得たりな本に出会えて驚いた。トヨタのかんばん方式にしろ、セブンイレブンのシステムにせよ、すべてはマネから生まれテリルのを具体的な例をあげながら詳説。なおかつ、その模倣のバリエーションについても単にまねるのか、反面教師にするのか、実は社内の横のセクションから真似ぶという手法もあるとまで紹介していて、確かに思い当たることばかり。素晴らしい現実と経営学の成果がマッチングした本でした2014/12/24
yashiti76
6
3⃣徹底して見倣い、模倣する。その過程で個人の能力は相当高まる!その高まった能力によって個人のオリジナリティが生まれる!内部の中心に近い人物が自ら気づき、自ら行動しなければ自己否定のモデリングは成功しない!守破離はお手本を守り、壊し、調和させること!公文は自分の気づきをサポートする教材!2013/12/28
-

- 電子書籍
- ドキドキわっか遊び ~汗まみれで震える…
-

- 電子書籍
- 転生したらSSS級ゴブリンになりました…
-

- 電子書籍
- 幼い皇后様【タテヨミ】第69話 pic…
-

- 電子書籍
- 鈴木聖 キミとの思い出は、宝物。 【S…
-
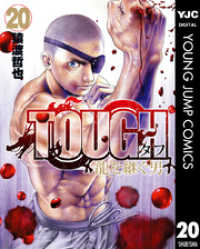
- 電子書籍
- TOUGH 龍を継ぐ男 20 ヤングジ…




