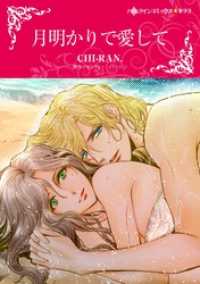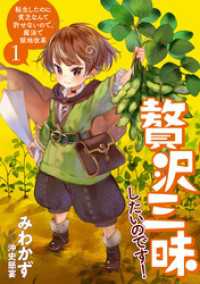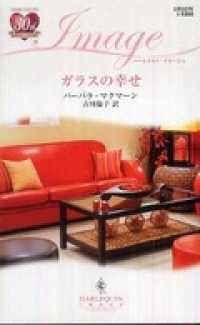内容説明
世界の構造改革のバイブル。1962年初版、フリードマンが最も愛した著作、待望の新訳。郵政改革、教育バウチャー、規制撤廃など絶対自由主義の政策の意味を説いた名著。
目次
経済的自由と政治的自由
自由社会における政府の役割
国内の金融政策
国際金融政策と貿易
財政政策
教育における政府の役割
資本主義と自由
独占と社会的責任
職業免許制度
所得の分配
社会福祉政策
貧困対策
結論
著者等紹介
フリードマン,ミルトン[フリードマン,ミルトン][Friedman,Milton]
1912年~2006年。アメリカの経済学者。競争的市場を信奉するシカゴ学派の主要人物。1976年度ノーベル経済学賞受賞者。当初、その理論は主流派からは異端視されたが、変動相場制、税率区分の簡素化、政府機関の民営化といったフリードマンの政策提言は、いまや世界の常識となった
村井章子[ムライアキコ]
翻訳家。上智大学文学部卒業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えちぜんや よーた
62
この文章を読んでいると、Amazonの創業者であるジェフ・ベゾスを思い出します。自叙伝である、ワンクリックで、オンライン書店の立ち上げの下りを読んでいると、こんな見出しが出てきます。・「人間の介入は必要悪である」つまるところ、一国の政策もweb上の書店運営も、根本思想は同じなのでしょう。人間がこねくり回して考えるのではなく、システマチックに決めてしまえば人間の恣意的判断よりも、資源の分配が効率的に行われると、フリードマンもベゾスも考えているのでしょう。 2013/04/24
ころこ
49
解説を高橋洋一が書いているように、民営化のアイデアが詰まった本だ。設計主義的で硬直的な制度よりも民営に任せた方が、市場の自動調整機能が働くことにより、自ずと望ましい状態になる。問題は国営でやらなければならないところ、つまり民営の限界を確定した上で国営と民営をすみ分ければ良いというのが論旨だ。サッチャー、レーガン、中曽根康弘の時代には民営化「小さな政府」が潮流になった。現在、全く異なる景色でこれらの言葉を聞く。宗教なき時代に大きな物語に従いたいという気持ちがそうさせているのだろうか。2023/10/27
死んだらシリウスへ行きたい
27
経済学、その言葉に永く馴染みはあっても、大学は中退、その後とんとご無沙汰の学問、株式投資を7年続けている、続いている、そんなこともあり、ある書評家の推薦図書としていろいろ経済書を読み始めた、その一冊、初学者というか未学者が、資本主義に立ち向かう、それはそれで私の勝手、実務、実益を目指しての学問、これからもこの種類の本をたくさん読みたい、学問としての経済学を理解するとともに、自分自身の考えとしての経済学は、どうあるべきかを考えたい。明日図書館へ返して、次の経済書を読む。2023/10/12
たかしくん。
22
他の方のレビューの通り、初版が1962年にしては、内容に古さを感じません。著者は徹底した自由主義者です。故に、資本主義や自由主義に敢えて制限を施す国家の役割に、かなり強いメスを入れます。そして、行き過ぎた金融政策、為替や貿易の介入を批判し、また義務教育のバウチャー制や郵政民営化等様々な規制を取り除くプランを強く推してきます。まあ、累進課税を批判し、一律税率の導入を主張する部分は、さすがに?!、と思いましたが…。(資産への累進課税を主張する後のピケティさんは、どう感じられたのでしょうか?(笑))2017/09/24
ヒロキです
16
競争的市場を信奉する経済学者フリードマンの本。変動相場制の導入や、政府機関の民営化等現在に実現している制度の多くを説得力を持って提言していて、その影響力の高さを感じた。論点では、医師免許などの職業免許制度撤廃や累進課税や年金強制加入も反対していて自由主義色が強い。中でも子供1人あたりの年間教育費に相当する利用券を支給する教育バウチャー制度は何度も取り上げられていて面白い施策に感じた。政府の支援は目に見えやすいが副作用があるとのこと。まだまだ完全に理解出来なかったので、期間を空けて読む価値がある本だと思う。2024/12/24