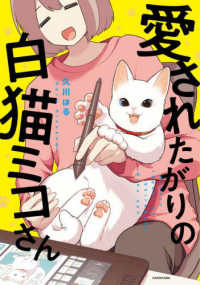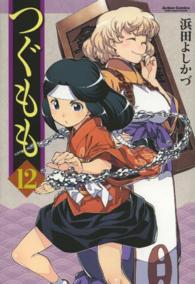出版社内容情報
現代日本における死のかたちを通して、供養の意義、宗教の本質に迫る。『寺院消滅』の著者、渾身の第2弾。「多死時代」に突入した日本。今後20年以上に渡って150万人規模の死者数が続く。
遺体や遺骨の「処理」を巡って、いま、“死の現場”では悩ましい問題が起きている。
首都圏の火葬場は混み合い「火葬10日待ち」状態。
遺体ホテルと呼ばれる霊安室ビジネスが出現し、住民運動が持ち上がっている。
都会の集合住宅では孤独死体が続々と見つかり、スーパーのトイレに遺骨が捨てられる---。
原因は、地方都市の「イエ」や「ムラ」の解体にある。その結果、地方で次々と消える寺院や墓。
地方寺院を食う形で、都市部の寺院が肥大化していく。
都心では数千の遺骨を納める巨大納骨堂の建設ラッシュを迎えている。だが、そこに隠される落とし穴----。
日本を覆い尽くさんばかりの「無葬社会」の現実。
現代日本における死のかたちを通して、供養の意義、宗教の本質に迫る。
ベストセラー『寺院消滅----失われる「地方」と「宗教」』の著者、渾身の第2弾。
【目次】
(第1章) 彷徨う遺体と遺骨
火葬10日待ちの現実
遺体ホテルが繁盛する時代
増える献体、捨てられる遺骨
超高齢社会が招く孤独死の悲劇
孤独死現場を「リセット」する人たち
(第2章) 変わりゆく葬送
葬儀のない葬儀場
都心のビルに一万基の遺骨
日本海に浮かぶ散骨島
理想の墓が新潟にあった
無数の遺骨を集めて仏像に
お坊さん便、食えない僧侶を走らす
仏具屋が見る「寺院消滅」
(第3章) 縁を紡ぐ人々
孤独死を防ぐ縁のかたち
路上生活者を供養する僧侶
難民キャンプに図書館を
地域再生と寺院
都市と地方の寺院をつなぐ
(第4章) 仏教存在の意義 ?原始仏教研究者・佐々木閑氏に聞く?
日本仏教の特殊な成り立ち
今を生きる人のための仏教
社会の受け皿としての仏教
「律」の精神で現代日本を見直すと
本質ではなく、かたちが変わってゆく
(資料) 現代社会における葬送データ
(第1章) 彷徨う遺体と遺骨
火葬10日待ちの現実
遺体ホテルが繁盛する時代
増える献体、捨てられる遺骨
超高齢社会が招く孤独死の悲劇
孤独死現場を「リセット」する人たち
(第2章) 変わりゆく葬送
葬儀のない葬儀場
都心のビルに一万基の遺骨
日本海に浮かぶ散骨島
理想の墓が新潟にあった
無数の遺骨を集めて仏像に
お坊さん便、食えない僧侶を走らす
仏具屋が見る「寺院消滅」
(第3章) 縁を紡ぐ人々
孤独死を防ぐ縁のかたち
路上生活者を供養する僧侶
難民キャンプに図書館を
地域再生と寺院
都市と地方の寺院をつなぐ
(第4章) 仏教存在の意義 ?原始仏教研究者・佐々木閑氏に聞く?
日本仏教の特殊な成り立ち
今を生きる人のための仏教
社会の受け皿としての仏教
「律」の精神で現代日本を見直すと
本質ではなく、かたちが変わってゆく
(資料) 現代社会における葬送データ
鵜飼 秀徳[ウカイ ヒデノリ]
鵜飼 秀徳(うかい・ひでのり)1974(昭和49)年6月、京都市右京区生まれ。成城大学文芸学部卒業後、報知新聞社に入社。2005年、日経BP社に移籍。「日経ビジネス」記者などを歴任。2016年4月より「日経おとなのOFF」副編集長。事件、政治、経済、宗教、文化など幅広い取材分野の経験を生かし、企画型の記事を多数執筆。一方、浄土宗僧侶の顔も持つ。1994年より浄土宗少僧都養成講座に入行。1996(平成8)年に浄土宗伝宗伝戒道場(加行)を成満する。現在、京都・嵯峨野にある正覚寺副住職。大学や宗教界などでの講演も多い。京都市景観市民会議委員を務める。著書に『寺院消滅----失われる「地方」と「宗教」』(2015年、日経BP)。
内容説明
2030年、孤独死予備軍2700万人。65歳以上の「一人暮らし+夫婦のみ世帯」=孤独死予備軍。毎日、都会のどこかで、誰にも看取られず、続々と人が死んでゆく。変わりゆく葬儀と供養のかたち、変わらぬ仏教界、もがく僧侶―。ベストセラー『寺院消滅』の著者による渾身の最新刊!
目次
第1章 彷徨う遺体と遺骨(火葬一〇日待ちの現実;遺体ホテルが繁盛する時代 ほか)
第2章 変わりゆく葬送(葬儀のない葬儀場;都心のビルに一万基の遺骨 ほか)
第3章 縁を紡ぐ人々(孤独死を防ぐ縁のかたち;路上生活者を供養する僧侶 ほか)
第4章 仏教存在の意義―佐々木閑氏に聞く(日本仏教の特殊な成り立ち;今を生きる人のための仏教 ほか)
著者等紹介
鵜飼秀徳[ウカイヒデノリ]
1974(昭和49)年6月、京都市右京区生まれ。成城大学文芸学部卒業後、報知新聞社に入社。2005(平成17)年、日経BP社に中途入社。「日経ビジネス」記者などを歴任。2016(平成28)年4月より「日経おとなのOFF」副編集長。事件、政治、経済、宗教、文化など幅広い取材分野の経験を生かし、企画型の記事を多数執筆。一方、浄土宗僧侶の顔も持つ。1994(平成6)年より浄土宗少僧都養成講座(全3期)に入行。1996(平成8)年に伝宗伝戒道場(加行)を成満。現在、正覚寺副住職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
どんぐり
HANA
おかむら
keroppi
きいち