内容説明
学校を子どもたちの「心の安全基地」に。生野南小学校・田島中学校から田島南小中一貫校へ!進化し続ける授業づくり。10年間の学校再生の実践に学ぶ。
目次
第1章 「『生きる』教育」9年間の教育プログラム(なぜ、今、「『生きる』教育」なのか;「『生きる』教育」4つの柱実践のポイント;「『生きる』教育」とは―子どもたちの幸せを願って;私にとっての「『生きる』教育」と「人権教育」;「自分の体と心を大切にする」養護教諭の実践)
第2章 小学校「『生きる』教育」学習指導案(1年 たいせつなこころと体―プライベートゾーン;2年 みんなむかしは赤ちゃんだった;3年 子どもの権利条約って知ってる?;4年 (1)10歳のハローワーク―LSWの視点から
(2)考えようみんなの凸凹―あつまれ!たしなんの星
5年 (1)愛?それとも支配?―パートナーシップの視点から
(2)スマホについて考えよう
6年 家庭について考えよう―結婚・子育て・親子関係)
第3章 中学校「『生きる』教育」学習指導案(7年 脳と心と体とわたし―思春期のトラウマとアタッチメント;8年 (1)リアルデートDV―支配と依存のメカニズム
(2)思春期における情報モラル教育―誹謗中傷を考える
9年 (1)社会の中の「親」と「子」―子ども虐待の事例から
(2)社会における「子どもの権利」)
付録 「『生きる』教育」教材集
著者等紹介
西澤哲[ニシザワサトル]
山梨県立大学人間福祉学部特任教授。虐待などでトラウマを受けた子どもの心理臨床活動を行っている
辻由起子[ツジユキコ]
社会福祉士、大阪府子ども家庭サポーター、こども家庭庁参与。主な活動は、相談業務、イベント開催、政策提言、研修講師、マスコミ発信、行政のスーパーバイザーなど。内閣官房こども政策参与として、こども家庭庁設立に関わる。活動はマスコミに多数取り上げられている
西岡加名恵[ニシオカカナエ]
京都大学大学院教育学研究科教授。さまざまな学校と連携して、カリキュラム改善やパフォーマンス評価の活用などの共同研究開発を行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
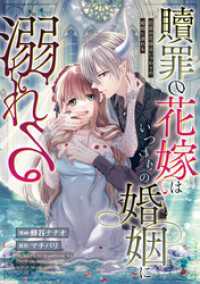
- 電子書籍
- 贖罪の花嫁はいつわりの婚姻に溺れる(分…
-

- 電子書籍
- 絶対にやってはいけない彼女 15
-

- 電子書籍
- ツカ子の婚活デスゲーム 第08話【単話…
-
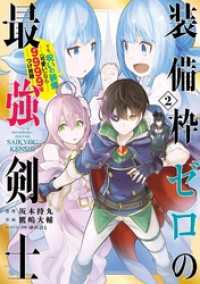
- 電子書籍
- 装備枠ゼロの最強剣士 でも、呪いの装備…
-
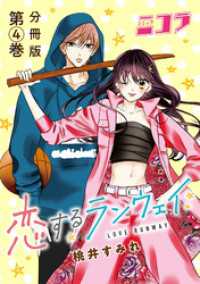
- 電子書籍
- 恋するランウェイ 分冊版第4巻 コミッ…



