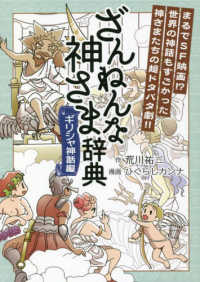出版社内容情報
取締役・経営幹部のガバナンス・コード対応力強化と業績責任完遂に必要なビジネス・アカウンティング能力向上を図るための本です。『戦略的な意思決定のために、財務諸表から経営を“診る”』
取締役・経営幹部の
●ビジネス・アカウンティング&ファイナンス能力向上
●コーポレートガバナンス・コードへの対応力強化
●中期計画の策定推進による業績責任の完遂
会計・財務が苦手な取締役・経営幹部も含め、業績責任を果たすために必要なビジネス・アカウンティング能力を体系的かつ極めてわかりやすく解説。コーポレートガバナンス・コードへの対応力を強化する。
また銀行や投資家がどのように会社を評価するのかを知り、彼らのニーズに応えるために、経営者視点から財務諸表を活用し、戦略策定に役立てる方法を、ふんだんな事例や実際の財務諸表を用いて学ぶ。
公認会計士、経営コンサルタントして、数多くの企業・団体で指導してきた経験を持つ著者が、身近な事例から実際の経営を“診る”ところまでを具体的に、そして体系立てて伝える。
この本を読めば取締役・経営幹部に求められるビジネス・アカウンティング能力は格段に向上する。
○はじめに
1章.そもそも財務諸表から何が分かるのか
1章?1.財務諸表を説明できるか
1 P/L(損益計算書)からは「経営成績」が分かる
2 B/S(貸借対照表)からは「財政状態」が分かる
3 C/F(キャッシュフロー計算書)からは「財務戦略」が分かる
4 事業セグメント情報からは企業戦略とその成果が分かる
2章.キャッシュフロー計算書が最も簡単な財務諸表
2章?1.家計簿の要約表がキャッシュフロー計算書
1 キャッシュフロー計算書はたった5つのキーワードで理解できる
1-1. 家計簿要約表がキャッシュフロー計算書
1-2. 5つのキーワードとは
1-3. 3つしかないお金の使いみち
1-4. キャッシュフロー計算書の読み方
2章?2. あの世が近づくと必要になる我が家のバランスシート
1 B/Sの構造を理解するための3つのキーワード
1-1. 純資産=資産?負債
1-2. 債務超過とは
1-3. 固定資産評価は企業会計では取得原価が原則
2 B/S=?CF ?B/SとC/Fの関係?
2-1. B/Sは累計のC/F(キャッシュフロー計算書)
2-2. 2期のB/Sから作成する間接法のC/F
2-3. 家計と企業の貸借対照表の違い
3章.キャッシュフローと利益計算の違い
3章?1.なぜFCFを経営成績と見なせないのか
1 生涯利益=生涯FCF ?P/LとC/Fとの関係?
1-1. P/LとC/Fの違いは計上タイミングにある
1-2. FCFを経営成績と見なせない4点の理由
1-3. 利益計算の3つのキーワード
1-4. 利益概念に訪れた大きな2つの変化
2 財務諸表の相互関係を1枚の絵にする
2-1.13のキーワード
2-2. B/Sを起点に財務諸表の相互関係を理解する
2-3.P/LとC/Fの関係整理
3章?2.押さえるべき2つの利益計算ルール
1 黒字倒産の事例研究
1-1. アーバンコーポレーションの経営指標推移
1-2. 在庫増が黒字倒産の原因
2 利益計算に魔力を与えた棚卸資産の費用配分ルール
2-1. 利益計算は在庫を資産計上する?棚卸資産の費用配分?
3 固定資産の費用配分ルール
3-1. 固定資産の価値減少額を減価償却により把握する
4 営業CF≒当期利益+減価償却
4-1.営業CFの推定能力を持つ
4-2. 当期利益+減価償却費=減価償却費控除前利益とは
3章?3.グローバル化が進む会計ルール
1 日本企業には3つの会計基準が認められている(金商法)
1-1. 財務諸表の公表を義務付ける2つの法律
1-2. 金融商品取引法における財務諸表の特徴
2 連結財務諸表で押さえるべき作成ルール
2-1. グループ外への売上が連結売上となる
2-2. 未実現利益は控除される
2-3. 連結B/Sでは資本と投資勘定は相殺消去される
2-4. 連結子会社の親会社以外の持分が「非支配株主持分」
2-5.親会社の子会社投資額と子会社の純資産との差額が「のれん」
4章.債権者(銀行)視点からの財務分析?財務諸表分析の3つの定石?
4章?1.定石1:3視点分析で経営課題を知る
1 生産性・健全性・成長性が3つの視点
1-1. 3つの代表指標
2 生産性の代表指標がROA
2-1. 経営者視点からのお金の生産性指標がROA
2-2. ROAの年度別推移
2-3. 著名企業のROA比較
3 健全性は自己資本比率で把握する
3-1. 財政状態の健全性を示す代表指標が自己資本比率
3-2. 自己資本比率の平均値は20%?40%
3-3. 著名企業の自己資本比率
4 比較年度がポイントとなる 成長性分析
4-1. 売上の成長性分析
4-2. 業種・業界で異なる成長性
5 著名企業の3視点分析
5-1. 著名企業の財務指標比較
5-2. なぜ3視点が重要なのか
4章?2.定石2:ROAの原因分析
1 金儲けの鉄則にのっとりROAを分析する
1-1. ROA=売上高経常利益率×総資産回転率
1-2. 効率性を示す総資産回転率
1-3. 収益性を示す売上高経常利益率
1-4. 自動車業界のROA分析
2 収益性が高い(低い)原因を特定する
2-1. P/Lの表示ルールは段階的利益表示
2-2. 収益性分析は段階的利益表示を活用する
2-3. 自動車会社の収益性分析
3 効率性が高い(低い)原因を特定する
3 -1. B/Sは流動性配列法で表示されている
3-2. 要約B/S作成の奨め
3-3. 効率性分析?なぜ総資産回転率が低い(高い)のか?
3-4. 自動車会社の効率性分析
3-5. 分析結果の要約
4章?3.定石3:借入余力分析
1 借金の水準はストックとフローの両面から診る
1-1. D/Eレシオ
1-2. 債務の償還年数は10年未満か
2 スコアリングシートによる格付け
2-1. あなたの会社はスコアリングシートで評価されている
5章.投資家視点からの企業価値分析
5章?1.企業価値分析のための3つの指標
1 PER・PBR・ROEが株価評価の代表指標
1-1. PER=株価÷1株当たり利益
1-2. 株価のもう一つの代表指標がPBR
1-3. ROEは株主視点の財務指標
1-4. ROEの最低ラインは、伊藤レポートでは8%
2 資本コストを上回るROEを上げ続ける
2-1. 株主資本にもコストがかかる!?
2-2. 株式益回りが株主資本コストを示す
5章?2.PBR=ROE×PER
1 株価分析マップによる企業価値分析
1-1. PBR=ROE×PER
1-2. 東証一部上場会社の株価分析と企業価値向上仮説
1-3. 著名企業の株価分析マップ
2 PBR=ROE×PERとは
2-1. PBR=ROE÷株式益回り(株主資本コスト)
2-2. ROEを高めるのではなく、株主の期待利回りを下げる
6章.財務諸表の向こうに戦略が見える
6章?1.C/Fから財務戦略を把握する
1 キャッシュフロー計算書の要約方法
1-1. 要約C/Fの作成
2 財務戦略の分析手法
2-1. 絵にしてイメージアップ
2-2. 事業投資/償却費倍率で投資政策を分析する
2-3. 資金政策を判断する
2-4. 株主還元政策は「配当性向」「総還元性向」で判断する
3 著名企業の財務戦略分析
3-1. 財務戦略のパターン分類
3-2. 財務戦略パターンごとの代表企業分析
3-3. ロイヤルロード型のファナック
3-4. リスクテイキング型の代表例がソフトバンク
3-5. 財務CF重視型には3つのパターンがある
3-6. CFからは再構築型に位置づけられる任天堂
4 財務戦略の転換点をつかめ
4-1. 投資政策の転換点
4-2. 財務CFの転換点
4-3. 著名企業9年間のFCF推移
5 財務戦略立案の基本ロジック
5-1. 将来のための金の使い方を明らかにするのが財務戦略
5-2. 財務戦略の策定手順
5-3. 財務戦略が決まれば目指すB/Sは描ける
6章?2.事業セグメント情報から企業戦略とその成果を読む
1 マネジメント・アプローチに変わった事業セグメント情報
1-1. 事業セグメント情報とは
1-2. 事業セグメント情報の分析手法
2 キヤノンの業績の原因を探る
2-1. 2001年から2007年までの企業戦略とその成果
2-2. 事業セグメントの変更による影響
2-3. 2007年以降の新事業セグメント別企業戦略と成果
2-4. キヤノンの中期経営計画の振り返り
7章.事業経営を分析する3+1の視点
7章?1.業績原因を事業経営視点から分析する
1 「事業・能力・成果+環境」が3+1の視点
1-1. 業績がなぜ良いのか(悪いのか)
1-2. 「事業戦略」と「事業戦略遂行能力」の何れが問題なのか
1-3. そもそも事業戦略とは何か
1-4. 「経営基盤能力」と「差別化能力」の峻別
1-5. 事業戦略会計のフレーム
7章?2.取締役の業績責任とは
1 いま株式会社に何が起きているのか
1-1. リスキーな株式会社制度
1-2. 1929年アメリカでの世界大恐慌で一般投資家の保護が課題となる
1-3. 株式会社の暴走
2 日本企業の持続的成長に向けて
2-1. 中期計画とは何か
2-2. なぜ、中期計画は実現できないのか
飯田 真悟[イイダシンゴ]
公認会計士、経営コンサルタント。
1976年 横浜市立大学商学部を卒業後、監査法人中央会計事務所入所。
1978年 公認会計士第3次試験合格。その後、1981年 社団法人日本能率協会に入職し、株式会社日本能率協会コンサルティングに転籍。現在は同社テクニカルアドバイザー。
財務・会計分野における専門家として公認会計士、経営コンサルタントおよび全国の企業・団体向けの研修・セミナー講師の活動をしながら、後進の育成に努めている。
内容説明
戦略的な意思決定のために財務諸表から経営を“診る”。取締役・経営幹部のビジネス・アカウンティング&ファイナンス能力向上。コーポレートガバナンス・コードへの対応力強化。中期計画の策定推進による業績責任の完遂。
目次
1章 そもそも財務諸表から何がわかるのか
2章 キャッシュフロー計算書が最も簡単な財務諸表
3章 キャッシュフローと利益計算の違い
4章 債権者(銀行)視点からの財務分析―財務諸表分析の3つの定石
5章 投資家視点からの企業価値分析
6章 財務諸表の向こうに戦略が見える
7章 事業経営を分析する3+1の視点
著者等紹介
飯田真悟[イイダシンゴ]
公認会計士、経営コンサルタント。株式会社日本能率協会コンサルティング(JMAC)テクニカルアドバイザー。1976年横浜市立大学商学部を卒業後、監査法人中央会計事務所入所。1978年公認会計士第3次試験合格。その後、1981年社団法人日本能率協会に入職し、株式会社日本能率協会コンサルティングに転籍。現在は同社テクニカルアドバイザー。財務・会計分野における専門家として公認会計士、経営コンサルタントおよび全国の企業・団体向けの研修・セミナー講師の活動をしながら、後進の育成に努めている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- セシル内科学 〈第4巻〉