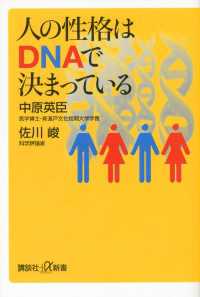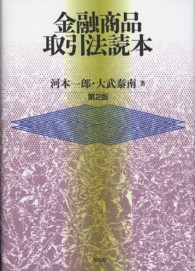出版社内容情報
「エンゲージメント経営」を切り口に人・組織の課題を展望する一冊。日本企業で働く社員のエンゲージメントが低い本当の理由を探る。皆さんは組織で幸せに働けていますか?
ここ日本でも、会社経営の現場で「社員エンゲージメント」という言葉が数年前から聞かれるようになった。日本人にはあまり馴染みが深くないエンゲージメントという言葉と考え方が、日本を代表するような会社にまで浸透してきた背景には、取り巻く競争環境の変化が横たわっている。
国内市場は成熟期を迎え、海外に飛躍の糸口を見出さなければ持続的な成長が不可能になっている。これまでの成長を支えてきた主力事業のビジネスモデルが陳腐化し、コスト構造の改革が急務となっている会社も多く、「目の前の仕事を一所懸命に頑張っていれば会社は成長していく」という時代はとうに終焉を迎えている。
さらに日本における労働市場のオープン化も見逃せない環境変化の一つだ。一昔前であれば転職は異例でネガティブに捉えられることが多かった転職も、今やキャリアアップの大きな機会として人材獲得競争の様相をも呈している。
自分の会社の先行きが見えず、社外には転職の機会が転がっているとなれば、「今の会社を辞めようかな?」と考えてしまうのも自然な成り行きだ。さらに会社の将来に対して期待が持てないまま、かといって会社を移るという決断もできずに、中途半端な気持ちのままで残り続ける会社員も出てきている。明るい将来を描くことができなければ、仕事へのモチベーションも上がらず、当然のことながら生産性も低下してしまう。事実、優秀な社員の離職防止、社員の生産性向上といったテーマが、日本の大企業でも課題としてあげられている。
エンゲージメントは、これらの課題を解決してくれる概念として注目されている。
社員エンゲージメントとは「自分が所属する組織と、自分の仕事に熱意を持って、自発的に貢献しようとする社員の意欲」である。かつて日本で流行した、社員満足度という考え方とは180度異なり、似て非なるものだ。
社員満足度は「社員が会社に満足しているか?」という社員から見た一方向的なものなのに対して、社員エンゲージメントは「会社は社員が期待する事を提供できているか?」「社員が仕事に幸せを感じて意欲的に取り組めているか?」と、会社と社員の双方向的な関係を問うものだ。
幸せな結婚が長続きする要因が「自分が求めるものを相手が実際に提供してくれているかではなく、自分の理想とする相手だという期待を抱き続けられること」であるように、社員エンゲージメントが高い状態というのは、期待を媒介にして会社と社員の間に幸福な関係が築けていることが必要だ。
いま「あなたの会社の社員は幸せに働けていますか?」と聞かれて、自信を持って「もちろん」と答えられる方がどれくらいいるだろうか。
価値観の多様化やダイバーシティ―といった言葉が代弁しているように、社員一人ひとりの価値基準や仕事に対する動機を、一昔前のように一律に考えることはもはや不可能である。
はじめに
第1章:いま、見直すべき人と組織の関係性
1.1.頑張って採用し、手塩にかけて育てた社員が辞めてしまう
1.2.会社は辞めない、しかし意欲が乏しい社員が続出
1.3.社員エンゲージメントが低い日本の会社
1.4.日本の会社が、社員の幸せを真剣に考えてこなかったわけ
第2章:社員が働くことに幸せを感じる構造
2.1.社員エンゲージメントの高低に影響を与える要素
2.2.手本とすべきグローバル企業との比較を通じて学べること
2.3.何より大事な会社の存在意義
2.4. 正しい方向感を見出せない会社で起こっている、仕事の生産性の低下
2.5.自己実現や成長という淡い幻想
第3章:無意識的に社員の意欲を削いでいる日本の会社
3.1.会社の中に、善と悪が潜んでいる
3.2.管理職のマネジメント力を再考する
3.3.日本の会社が今すぐできること
第4章:「幸せの感じ方は人それぞれ」で終わってしまわないように
4.1.働くことに対する動機を考える
4.2.社員の琴線に触れる仕事の与え方
4.3社員の動機を上書きすることはできるのか?
第5章:人と組織の関係を見直して、社員のエンゲージメントを高める方法
5.1.社員エンゲージメントをリーダーシップ論から捉え直す
5.2.現場のリーダーシップを見つめ直して、社員の意欲を喚起する
5.3.日本の会社が、社員エンゲージメントのコンセプトを自分のものとするために
おわりに
柴田 彰[シバタアキラ]
著・文・その他
内容説明
日本企業で働く社員はなぜエンゲージメントが低いのか?自分が所属する組織と仕事に熱意を持って、自発的に貢献する社員の意欲を最大化する。世界の成長企業が取り組む、これからの経営。
目次
第1章 いま、見直すべき人と組織の関係性(頑張って採用し、手塩にかけて育てた社員が辞めてしまう;会社は辞めない、しかし意欲が乏しい社員が続出 ほか)
第2章 社員が働くことに幸せを感じる構造(社員エンゲージメントの高低に影響を与える要素;手本とすべきグローバル企業との比較を通じて学べること ほか)
第3章 無意識的に社員の意欲を削いでいる日本の会社(会社の中に、善と悪が潜んでいる;管理職のマネジメント力を再考する ほか)
第4章 「幸せの感じ方は人それぞれ」で終わってしまわないように(働くことに対する動機を考える;社員の琴線に触れる仕事の与え方 ほか)
第5章 人と組織の関係を見直して、社員のエンゲージメントを高める方法(社員エンゲージメントをリーダーシップ論から捉え直す;現場のリーダーシップを見つめ直して、社員の意欲を喚起する ほか)
著者等紹介
柴田彰[シバタアキラ]
コーン・フェリーシニアクライアントパートナー。慶應義塾大学文学部卒PWCコンサルティング(現IBM)、フライシュマンヒラードを経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぽりま
Go Extreme
mkt
Takashi
Kenta