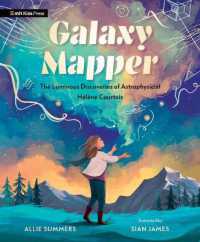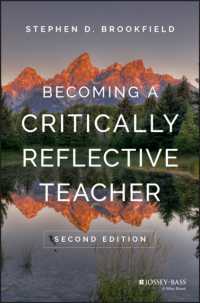目次
総論―現代日本社会教育史研究の課題と方法
第1部 戦間期社会教育論の形成(『社会と教化』誌にみる1920年代初期の社会教育発想;乗杉嘉寿の社会教育論の形成とその特質;乗杉嘉寿の婦人教育論―その意義と限界;1920年代前半期文部省社会教育行政における少年団論の形成)
第2部 戦前期児童保護・感化教育論の生成と展開(社会教育における「児童保護」の特質―1920年代『社会と教化』『社会教育』を中心に;感化教育における特殊児童観―1922年少年法制定までの時期を中心に;感化教育における教育的機能の深化と障害児問題の展開に関する研究;東京帝国大学セツルメント託児部の子ども観と保育実践)
第3部 占領期における社会教育の成立と展開(戦後教育改革におけるGHQ社会教育政策―その意義と限界;占領下公民館政策の形成と地域展開;占領期における地域社会教育の形成―岐阜の公民館を中心に ほか)
著者等紹介
新海英行[シンカイヒデユキ]
1938年愛知県に生まれる。1962年名古屋大学教育学部卒業。1972年名古屋大学大学院教育学研究科博士課程満期退学。1972年香川大学教育学部助教授を経て現在、名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授(社会・生涯教育学)。博士(教育学)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 洋書
- MELO