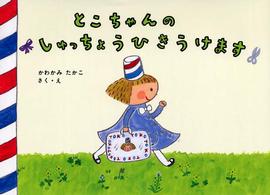出版社内容情報
4820528033
徳冨蘆花集(第1回・全10巻)
編集・解説●吉田正信
A5判・上製函入
本体140,000円
徳冨蘆花集(第1回・第2回)
全20巻+別巻1
編集・解説●吉田正信
A5判・上製函入・全11,200頁
セット本体280,000円
全巻一括発行1999年2月
”問いかけの文学”を紡いだ蘆花の主要作品を網羅した待望の資料集成!
初版本による確かなテクストの提供により近代文学研究の間隙を埋め、さらなる進展をはかる、研究者・大学・図書館等必備の著作集。
「おもひ出の記」(初出第一回)「自然と慰薪」「黒潮の解」「第百版不如帰の巻首に」など、蘆花全集・文学全集などに未収録の貴重資料十余篇を翻刻(別巻)。
特長
1.蘆花の著作のうち、小説・随想等20冊を集成し、復刻(影印)版として、刊行する。
2.復刻は、原則として初版本を底本とし、扉から前付・本文・後付等すべてを収める。
3.判型・装丁等は全巻統一する。ただし、底本の版面は原則として原寸で収める。
4.各巻に凡例を付し、復刻にあたっての仕様を明記する。
推薦のことば
『徳冨蘆花集』によせて
紅野敏郎
(早稲田大学名誉教授)
蘆花の刊行した単行本を一括し、『徳冨蘆花集』として複刻されるという。
本当は、新しいかたちでの『徳冨蘆花全集』として編集してもらいたいのだが、それへの重要なワンステップとして考えれば、このたびの複刻はきわめて朗報なりと言い得る。
蘆花の全業績を幅広く見わたし、解説・解題の類も、吉田正信さん一人で責任を持たれるという。
堅実な吉田さんの什事には定評がある。
トルストイとの関係をはじめ、おびただしいほど版を重ねた『自然と人生』や『不如帰』『思出の記』などは、蘆花再評価につながる要素にみちている。
大逆事件に際しての『謀叛論』なども、近代文学研究に不可欠の発言である。
徳冨蘆花という人物については、中野好夫の刺激的にして好奇心をそそられる好著があるが、一般には研究者がムキになってみずからの研究の対象としない傾向がある。
これはまことに憂うべき現象で、大きなヒズミと私には思える。
これを契機に、蘆花の作品を読みなおし、再検討し、研究にはげむ人の出現を心から期待したい。
編者のことば
徳冨蘆花の文学
吉田正信(愛知教育大学教授)
漱石が出現する以前、文豪といえば徳冨蘆花であると見られた一時期があった。
中等教育の教材としても、かつては蘆花がすば抜けて多かった。
しかし今日の文学史においては、位置づけは傍流扱いにとどまっている。
生前の栄光については蘆花自身とまどいを見せていた。
だが戦後の不遇な扱いは、正当な評価によるものとはいえない。
蘆花に注目する識者は少なからずあり、継承すべき遺産としての再評価はいずれはなされなければならない課題であった。
他の作家に比べて遅れている蘆花研究の深化は、それを通じて近代の文学史・思想史の再検討も促すことになる、きわめて有意義な為事なのである。
明治大正期とかさなる六十年を生きた蘆花徳冨健次郎は、文学者としても人間としても興味深い独特の存在である。
読者の支持をえてロングセラーになった『不如婦』『自然と人生』『思出の記』は、蘆花によっても否定的に顧みられているが、平民主義の文学的達成として評価できる。
中絶した社会小説『黒潮』の構想には、日本だけでなく兄蘇峰との愛憎関係の解脱も託されていたと見られる。
その執筆動機は晩年の『冨士』にまで続く。
日露戦後、指針を求めての聖地とトルストイ訪問は、蘆花ならではの壮挙であった。
講演「謀叛論」は不朽の文学、とは中野好夫の弁であり、『新春』を特異な告白文学と評したのは荒正人であった。
「美的百姓」の心境を映した『みゝずのたはこと』の滋味も尽きないものである。
発狂の噂まで流れたが、人間としてはきわめて真摯。
社会だけでなく自己のなかの、理念と現実の矛盾の克服に、苦闘し悩み抜いた生涯であった。
『蘆花全集』は没後まもなく全20巻の立派な全集が編まれたが、今日では特に本文校訂などの不備のため、研究資料としては依拠しがたいという憾みがある。
その不備を補うのが今回の複刻による著作集である。
この有用性は、完全に近い全集が刊行されても、本文の手堅さゆえに失われることはない。
蘆花没後七十一年、活用されてどのような研究成果が見られるか、期待されるわけである。
第1回全10巻
本体140,000円
ISBN4-8205-2803-3
●構成
第1巻
トルストイ
*初版・底本=明治30年4月26日、民友社
第2巻
青山白雲
*初版=明治31年3月25日、民友社。底本=再版
第3巻
小説 不如帰
*初版・底本=明治33年1月15日、民友社
第4巻
自然と人生
*初版・底本=明治33年8月18日、民友社
第5巻
小説 思出の記
*初版・底本=明治34年5月15日、民友社
第6巻
青蘆集
*初版=明治35年8月21日、民友社。底本=第10版
第7巻
黒 潮
第一篇
*初版=明治35年2月27日、黒潮社〔私家版〕。底本=再版
第8巻
順礼紀行
*初版・底本=明治39年12月15日、警醒社書店
第9巻
小説 寄生木
*初版・底本=明治42年12月8日、警醒社書店
第10巻
みゝずのたはこと
*初版・底本=大正2年3月13日、新橋堂書店・服部書店・警醒社書店
第2回全10巻+別巻
本体140,000円
ISBN4-8205-2802-5
●構成
第11巻
小説 黒い眼と茶色の目
*初版=大正3年12月13日、新橋堂。底本=第4版
第12巻
死の蔭に
*初版・底本=大正6年3月15日、大江書房
第13巻
新 春
*初版・底本=大正7年4月11日、福永書店
第14巻
日本から日本へ 東の巻
*初版・底本=大正10年3月8日、金尾文淵堂
第15巻
日本から日本へ 西の巻
*初版・底本=大正10年3月8日、金尾文淵堂
第16巻
竹崎順子
*初版・底本=大正12年4月21日、福永書店
第17巻
小説 冨 士 第一巻
*初版=大正14年5月10日、福永書店。底本=第26版
第18巻
小説 冨 士 第二巻
*初版・底本=大正15年2月11日、福永書店
第19巻
小説 冨 士 第三巻
*初版・底本=昭和2年1月15日、福永書店
第20巻
小説 冨 士 第四巻
*初版・底本=昭和3年2月11日、福永書店
別 巻
徳冨蘆花-人と文学 吉田正信
作品解説 吉田正信
資料編=「おもひ出の記」(連載第一回)「自然と慰籍」「何故に余は小説家となりし乎」他(年譜・著作目鋒・主要参考文献)
*注=第14・15巻、第17~20巻は、徳冨愛共著
徳冨蘆花 トピックス
蘆花が草深い千歳村粕谷の地に荒屋を購めて引越したのが明治40年2月で、ここが永住の地となった。
当時は、草葺の六畳二間と土間のみの家で、土地は一反4畝(約1500㎡)だったという。
当時、蘆花の家から東京への往還は、徒歩で渋谷まで8キロ強(府中街道)、新宿まで約10キロ(甲州街道)。
なお甲州街道を馬車が一日4便(新宿-調布間)あったが、京王電鉄はまだ開通していなかった。
現在蘆花の旧居跡一帯は芦花公園となり、恒春園内には蘆花記念館(昭和34年竣工)をはじめ、母屋(移住当初の居宅)・奥書院(明治44年、古屋を購入して移築。「秋水書院」)・つなぎ廊下・表書院(梅花書屋)などがあり、他に地蔵尊(業者から購めたもので六地蔵の一体という。「宝永六歳云々」と彫られている)、蘆花夫妻の墓などがある。
「恒春園」命名の由来は、大正7年ごろ、堺古川が、台湾の恒春に蘆花の農場があると伝聞の聞き違いから蘆花宛に書生の紹介を申し込んで来たことがあり、その時の書面に見える「恒春」という名前に魅かれたからだという。
蘆花の別号
健二郎・健二・雁金之友・蘆花逸生・高眼低手生・驚濤生・画湖仙史・春夏秋冬居士・敬亭居士・敬亭生・ゝゝゝ・秋水生・丁々生・寒香生・秋山生・麹塵生・不知火生・AB子・蘆花生・漫遊生・楓葉・週遊生・健。
蘆花のスケッチ
蘆花は、明治29年10月頃から洋画を習いはじめ、翌年2月頃から和田英作について洋画を学んでいる。和田は明治7年、鹿児島県生。30年、東京美術学校卒。美校在学中の29年には白馬会の設立にかかわり、のち美校の教授をへて校長となる。蘆花が絵を習いはしめた動機は、愛子が挿画などを描いていたことに触発されたともいえるが、もっと根深いところでは、自然との交感願望が指摘されるという。
徳冨蘆花年譜
明治元年(1868)
10月25日(戸籍簿の記載は20日)、肥後国葦北郡水俣(現・熊本県水俣市浜)に生まれる。
本名、健次郎。父一敬、母久子。四姉と兄猪一郎(蘇峰、以下蘇峰と記す)がいた。
母方の伯母に竹崎順子(茶堂の妻)、叔母に横井津世子(小楠の妻)、日本基督教婦人矯風会を興した矢島揖子がいた。
明治3年(1870) 2歳
6月、父一敬が熊本県庁出仕(明治5年辞職)。
秋、一家をあげて大江村(現・熊本市大江町)に移る。
明治7年(1874) 6歳
この年、竹崎茶堂の私塾日新堂の幼年塾(のち本山小学校に併合)に入る。
明治10年(1877) 9歳
西南戦争の難を避けて熊本市郊外の沼山津、杉堂などで数ヵ月過ごす。
明治11年(1878) 10歳
6月、同志社英学校に在学中の蘇峰に伴われて京都に赴き、同校に入学。
明治13年(1880) 12歳
5月、蘇峰が同志社を退学して上京したのを機に、6月、同志社を退学して帰郷。
9月、父らの設立した熊本共立学舎に入る。11月、蘇峰帰郷。
明治15年(1882) 14歳
3月、蘇峰設立の大江義塾に入る。
明治18年(1885) 17歳
3月、姉光子とともに熊本のメソジスト教会で受洗。
ほどなく父の方針で愛媛県の今治町で牧師をしている従兄の伊勢(横井)時雄のもとに赴き伝道に従事する。
明治19年(1886) 18歳
6月、同志社の神学部教授として赴任した伊勢時雄に呼ばれ京都へ行き、同志社に復学する。
同志社女学校の生徒で、新島襄夫人の姪の山本久栄を知り交際をはじめ、結婚を考える。
蘇峰は、9月、大江義塾を閉鎖し、10月、『将来之日本』を経済雑誌社より刊行、12月、蘆花を除き一家をあげて上京する。
明治20年(1887) 19歳
2月、蘇峰は民友社をおこし『国民之友』を創刊。
夏休に上京して両親の家に滞在中久栄との関係を断つよう説諭され、かねて伊勢時雄の反対もあって9月、久栄に訣別の手紙を出す。
12月、京都から鹿児島へ逃避行する。
明治21年(1888) 20歳
2月、叔父徳永昌竜に迎えられて鹿児島から水俣に帰り、義兄河田精一につきそわれて熊本に赴き、竹崎順子宅に身を寄せ、熊本英語学会(9月より熊本英学校と改称)の教師となる。
明治22年(1889) 21歳
5月、上京。京橋の滝山町に下宿。民友社に入り校正および海外の雑多な記事の翻訳、雑録欄を担当。
9月、『如温、武雷土伝』12月、『理査土、格武電』など翻訳物の人物伝を民友社より刊行。
明治23年(1890) 22歳
2月、蘇峰、「国民新聞」を創刊、同紙および「国民之友」に海外事情の紹介、翻案ものを発表。
明治25年(1892) 24歳
11月、「グラツドストーン伝」を民友社より刊行。
明治26年(1893) 25歳
7月、編著『近世欧米 歴史之片影』を民友社より刊行。
明治27年(1894) 26歳
1月、芝桜田町の下宿に移る。4月、父から田畑10町歩、紡織株千円を分与される。
5月、一敬や蘇峰によって縁談がすすめられていた熊本県出身の原田愛子と結婚、赤坂氷川町の勝海舟邸内の借家に入る。
明治30年(1897) 29歳
1月、生活や精神的転機を図り、逗子の旅館柳屋に転居。
4月、「拾弐文豪」第拾巻「トルストイ」を民友社より刊行。
明治31年(1898) 30歳
3月、文芸小品集「青山白雲」、4月、「世界古今 名婦鑑」(共著)、10月、『外交奇譚』をそれぞれ民友社より刊行。
11月29日より「国民新聞」に「不如帰」の連載をはじめる(32年5月24日完結)。
明治33年(1900) 32歳
1月、初出を半年がかりで全面的に改稿した『小説 不如帰』を民友社より刊行、多大の反響を呼ぶ。
3月、「灰燼」を「国民新聞」に発表。同月、「おもひ出の記」の連載をはじめる(34年3月完結)。
8月、『自然と人生』を民友社より刊行。
10月、千駄ヶ谷村原宿に移る。
11月、『探偵異聞』を無署名で民友社より刊行。
明治34年(1901) 33歳
5月、『小説 思出の記』(「おもひ出の記」改題)を民友社より刊行。
12月、『ゴルドン将軍伝』を警醒社より刊行。
明治35年(1902) 34歳
1月より、「黒潮」を「国民新聞」に連載(6月完結)。
3月、「慈悲心鳥」を「文芸界」に発表。
8月、随筆小品集『青蘆集』を民友社より刊行。
12月、「国民新聞」に寄稿した「霜枯日記」の無断削除に噴激して、蘇峰との袂別を決意。
明治36年(1903) 35歳
1月、自宅に黒潮社を設立。
2月、『小説 黒潮第一篇』を黒潮社より発行(自費出版)。
同書巻頭の蘇峰への告別の辞は蘇峰との年来の確執を吐露したもので文壇の反響を呼んだ。
8月、北海道旅行。
明治37年(1904) 36歳
この年修善寺・昇仙峡・利根水郷等に遊ぶ。
2月10日、日本、ロシアに対し宣戦布告。
4月、『Nami-ko』(英訳「不如帰」)がボストンから刊行される(その後『不如帰』は、中国語・フランス語・ポーランド語訳等が出る)。
明治38年(1905) 37歳
1月~3月、九州を旅行、桜島滞在。
8月、愛子と富士山に登り、山頂で人事不省に陥るが九死に一生をえる。
この経験を神の警鐘と受けとめ、再生のための精神革命が始まる。
12月、蘇峰と和解。逗子で越年。
大正2年(1913) 45歳
2月、護憲派の民衆の襲撃を受けた国民新聞社に駆けつけ、蘇峰を慰問し、蘇峰の懇請により社を援助するため小説の連載を受諾。
3月、田園生活の記録『みゝずのたはこと』を警醒社(他二社連合)より刊行。
6月より小説「十年」を「国民新聞」に連載をはじめるが11回で中止。
9月~11月、愛子らと九州・満州・朝鮮・山陰地方を旅行。
途中京城で蘇峰と会うが、以後死の直前まで絶交状態に陥る。
大正3年(1914) 46歳
5月、養女鶴子を蘇峰のもとにかえす。
同月、一敬死去、葬儀には参加せずこの頃より面会文通を謝絶する閑居生活を始める。
12月、告白物の第一作『小説 黒い眼と茶色の目』を新橋堂より刊行。
大正6年(1917) 49歳
3月、大正2年の旅行に材をとった『死の蔭に』を大江書房より刊行。
この年伊香保・九十九里浜などに滞在。
大正7年(1918) 50歳
4月、『新春』を福永書店より刊行。
5月~7月、瀬戸内の各地を旅行し、故地の今治も訪ねる。
大正8年(1919) 51歳
1月、夫婦で、第二のアダムとイヴ、日子と日女の自覚に達しこの年を新紀元第一年と宣言し、二人で一年二ヵ月の世界一周旅行に発つ。
大正10年(1921) 53歳
3月、愛子との共著『日本から日本へ』東の巻・西の巻を金尾文淵堂より刊行。
同月、関西旅行。4月、伊香保に赴く。
大正11年(1922) 54歳
1月~3月、愛子をともない九州から朝鮮を旅行し、各地で講演。
大正12年(1923) 55歳
4月、『竹崎順子』を福永書店より刊行。同月、伊香保に赴く。
大正13年(1924) 56歳
9月、日米間の諸問題などの論集『太平洋を中にして』を編集し、文化生活研究会より刊行。
大正14年(1925) 57歳
5月、『小説 冨士』第一巻(愛子と共著、以下同じ)を福永書店より刊行。同月、伊香保に赴く。
翌15年2月、同書第二巻を福永書店より刊行。
昭和2年(1927) 59歳
1月、『小説 冨士』第三巻を福永書店より刊行。
2月、衝心症の発作をおこす。7月、愛子と看護婦同行で伊香保の千明仁泉亭に赴き療養。
9月18日、蘆花の希望で蘇峰が訪ね和解する。
同夜死去。翌3年2月、絶筆『小説 冨士』第四巻が福永書店より刊行された。