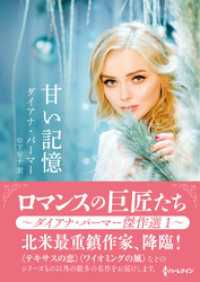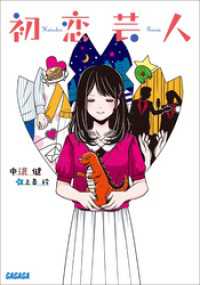- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 図書館・博物館
- > 図書館・博物館学一般
目次
1章 学校に図書館を設置すること
2章 高まる学校図書館への期待
3章 図書館のはたらきを備える学校
4章 学校図書館の教育力
5章 教育力の7項目を個別にみる
6章 教育力を活かせる要件
7章 これからの学校づくりと学校図書館―教育力を活かした学校図書館づくり 課題と展望
資料編
著者等紹介
塩見昇[シオミノボル]
1937年2月京都市に生まれる。1960年3月京都大学教育学部卒業。4月大阪市立図書館入職(司書)。1971年4月大阪教育大学専任講師(図書館学)。1980年8月同教授。1997年4月同教養学科長(併任)。1998年4月同附属図書館長(併任)。2002年3月同定年退職。4月同名誉教授、大谷女子大学教授。2005年3月大谷女子大学退職。5月日本図書館協会理事長。2013年5月同退任。2016年5月同顧問(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。