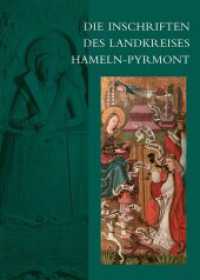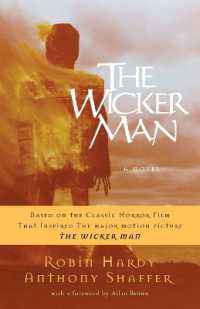出版社内容情報
季刊誌SOWER(ソア)連載「人物と聖書」の単行本化。各方面で活躍した日本人がキリスト信徒であるなしに関わらず、聖書とどう向きあい、生き方にどのような影響を受けたか。それを日本キリスト教史の第一人者で、内村鑑三研究で知られる鈴木範久氏(立教大学名誉教授)が探りました。『学鐙』(1999年)に掲載された「鈴木大拙の聖書」も収録。
鈴木範久[スズキノリヒサ]
1935年生まれ。専攻: 宗教学、宗教史学。立教大学名誉教授。著書に『明治宗教思想の研究』(東京大学出版会1979)、『内村鑑三日録』全12巻(教文館1993-99)、『聖書の日本語』(岩波書店2009)など多数。