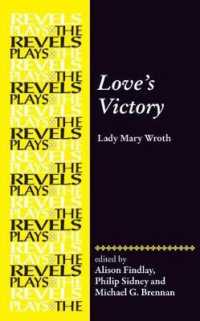内容説明
永田町、霞が関の地方支配からの離脱。カギは市民と地域社会のパワー。本格的な地域再生に向けてのヒントを提示。
目次
第1章 市民的地域政策は可能か(住民と市民的地域社会の出番;市民的地域政策による地域再生 ほか)
第2章 農村地域再生の胎動―あたらしい「互酬と共同性」を求めて(脱「構造政策」への道―構造政策と農村政策の非対称性;「農地の自主管理」と集落営農―成立と変貌 ほか)
第3章 地域の支え合いから「福祉まちづくり」へ―地方分権を活かした新たな取り組み(地域における福祉(支え合い)の状況
現行の地域福祉推進システム ほか)
第4章 現場に見る地域再生の可能性―カギ握る理念の確立(意気消沈する地域の現状;地域が衰退した原因 ほか)
第5章 1727通りのまちづくり計画―脱国土計画に始まる地域再生(市町村まちづくり計画の意味;全総計画は何をもたらしたか ほか)
著者等紹介
本間義人[ホンマヨシヒト]
法政大学名誉教授。1935年生まれ
檜槇貢[ヒマキミツグ]
弘前大学大学院地域社会研究科教授。1949年生まれ
加藤光一[カトウコウイチ]
信州大学教授(農学部)。1953年生まれ
木下聖[キノシタタダシ]
埼玉県立大学保健医療福祉学部准教授。1962年生まれ
牧瀬稔[マキセミノル]
財団法人地域開発研究所研究員。1974年生まれ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
0
市民とは、住民とはやや謂いが異なり、「生活を遠くからみつめつつ、生活世界のサイドから夢を創り上げ、地域社会づくりの運動に重ね合わせる人たち」(5ページ)である。地域経営の貧困(9ページ~)は、どうしたら軽減できるだろうか。行政中心でない、市民主体の地域経営にシフトすることであろう(20ページ~)。伊那のグリーンファームは同一労働・同一賃金というので、立派な経営姿勢だ(81ページ)。地域再生法では、多義的な地域再生を見ている。地域資源を活かし、地域雇用の創造がある(218ページ)。現実はハローワーク低調。2012/10/19
-

- 和書
- 宙