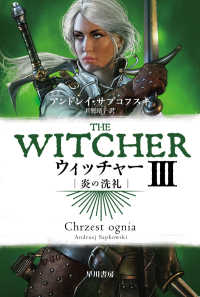内容説明
「受け入れ難いリスクが存在しないこと」という従来の安全の考え方では、十分な効果が得られない状況が多々生じ、新しい安全へのアプローチが求められている。レジリエンスエンジニアリングはその答えであり、「安全は変化する条件下で成功する能力」との考えのもと、事象に対処する能力、進展しつつある事象を監視する能力、未来の脅威と好機を予見する能力、過去の失敗・成功双方から学習する能力―が重視される。それらをどのように実装すればよいか、その具体例を示した実務家への手引書。
目次
第1部 現実に対処する(レジリエンスと対処能力;ハドソン川からの教訓;不確実さを処理する―麻酔におけるレジリエントな決定;エスカレートする状況における組織的レジリエンスの訓練)
第2部 危機を監視する(監視―レジリエンスエンジニアリングでの重要な能力;飛行時間の制限から疲労リスクマネジメントシステムへ―レジリエンスへの取組み;重大なことに気づき、対処するための訓練―発電所保守からの事例研究;緊急事態と異常事態の訓練における認知方略―航空管制のレジリエンスについて)
第3部 脅威を予見する(レジリエンスと予見能力;適応システムが失敗する基本パターン;鉄道土木工事の計画立案におけるレジリエンスの測定;バランスの技術―競合する目標に取り組むために上向きのレジリエンスの特徴を利用する;金融サービスシステムにおける機能的相互依存性の重要性)
第4部 事実から学習する(学ぶべきか学ばざるべきか、それが問題だ;事実の解明なくして安全性の向上なし;社会・技術システムにおける近視眼的な協調からレジリエンスへ―病院における事例研究;レジリエントな組織でインシデント報告が成功する必要条件;航空産業はレジリエンス的な考え方を導入できる段階になっているか?航空部門のヒューマンファクターズの前提を俯瞰する)
著者等紹介
Hollnagel,Erik[HOLLNAGEL,ERIK] [Hollnagel,Erik]
フランスMINES(パリ鉱山大学)の産業安全部門長、教授およびノルウェー科学技術大学(トロンハイム)客員教授。これまでいくつもの国の大学、研究センター、企業などで多様な問題の研究に従事。関心領域は産業安全、レジリエンスエンジニアリング、事故調査、認知システム工学、認知人間工学など
Pari`es,Jean[PARIES,JEAN] [Pari`es,Jean]
フランス民間航空国立学校を卒業しエンジニア資格取得。航空安全規制を行うフランス民間航空局(DGAC)に入所。ICAOのヒューマンファクターズ・航空安全研究グループに1988年の創設時から参加。1990年にはフランス航空事故調査局BEAの副主任、主任。1994年にBEAを退社しD´edale SAS社を設立。2000年から2004年までCNRSの研究副ディレクターを兼務し、高リスク活動の失敗に関するハザードと個人・チーム・組織によるその制御に関する業務に従事
Woods,David D.[WOODS,DAVID D.] [Woods,David D.]
オハイオ州立大学総合システム工学部教授および自然・社会・技術システムの複雑性に関する大学自発研究のディレクター。認知システム工学の設立から実践応用までを推進。麻酔業務、航空、宇宙、医療などの分野において人間と自動化機器のチームとしての活動を研究。ヒューマンファクターズと人間工学会の会長、米国科学アカデミーをはじめとする諮問委員会活動などに従事。米国医療安全基金の設立当時からの運営委員、退役軍人局の医療安全調査中西部センターの副センター長、スペースシャトル・コロンビア号爆発事故調査委員会のアドバイザーなどを歴任
Wreathall,John[WREATHALL,JOHN] [Wreathall,John]
システムズエンジニアリング手法の専門家。安全性、信頼性、品質に関係した人的および組織的パフォーマンス分野が主な対象分野。ヒューマンパフォーマンス分析を目的とした定量的・定性的手法の開発と応用を先導。応用分野は医療、輸送、原子力、宇宙航空など
北村正晴[キタムラマサハル]
東北大学名誉教授、株式会社テムス研究所所長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
The pen is mightier than the sword
-

- 電子書籍
- 無能は不要と言われ『時計使い』の僕は職…