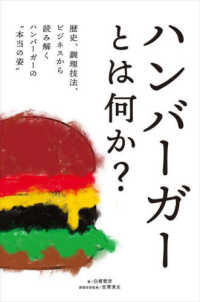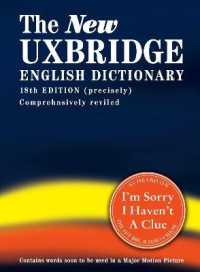内容説明
奈良・京都を中心に伝統と由緒ある寺社が集まる近畿地方。安土・桃山時代と江戸時代の傑作が共存する京都・滋賀・三重・和歌山・大阪・奈良・兵庫の100寺社。知られざる江戸彫物大工たちの壮麗なる超絶技巧を再発見!!
目次
様々な建築を生んできた中央の彫物棟梁とその彫物
西本願寺
高野山
京都の寺社彫刻
滋賀の寺社彫刻
紀州の建築彫刻は「語る」
三重・和歌山の寺社彫刻
大阪・奈良の寺社彫刻
丹波柏原の名彫刻師中井権次一統の足跡を訪ねて
兵庫の寺社彫刻
著者等紹介
若林純[ワカバヤシジュン]
1957年東京都生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業。在学中にヒマラヤ・ダウラギリ2峰登頂。その後もネパール、チベット、アラスカに遠征。以来、国内外の自然、建築、社寺彫刻を主に撮影、企画、執筆。(社)日本写真家協会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
chang_ume
7
蟇股・欄間・手挟などに施された寺社建築彫刻の写真集。注目は、18世紀の丹波地域に花開いた、稠密で微分的なロココスタイルの建築彫刻文化。独自色の強い作品群を残した、彫物師家系「中井権次一統」(柏原中井家)の活躍が光る。全般的に、仏像がそのままはめ込まれたような立体感を特徴とした17世紀までの流れに対して、18世紀以降はエッジの効いた造形が絵画的に表現される一大変化を指摘できるような。「装飾の自立」といえるような様式変遷ですが、これも地域単位のパトロン事業あっての展開だろうか。近世美術の極致と思う。2020/09/03