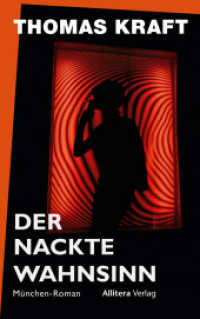内容説明
科学哲学の思考を応用して精神医学の世界をつぶさに分析、精神医学批判のさまざまな疑念に答えつつ、医療現場の実践に即した提言を行う。複雑化する精神疾患や臨床試験をめぐる問いに、いかに向き合うのか―。切実な問いにこたえる待望の書。
目次
精神疾患の本性(精神疾患は神話なのか?;精神疾患が実在するのなら、それは何なのか?)
精神医学における説明(自然誌に基づく説明;個別の個人誌)
理論と理論との関係(異なるパラダイムが出会うとき;還元主義)
価値と利害関心の取り扱い(価値負荷的な科学としての精神医学;大企業と治療の評価)
著者等紹介
クーパー,レイチェル[クーパー,レイチェル] [Cooper,Rachel]
ケンブリッジ大学で博士号(科学史・科学哲学)を取得。現在、ランカスター大学上級講師。精神疾患の分類をめぐる概念的問題を主な研究テーマとする
伊勢田哲治[イセダテツジ]
1968年生まれ。1999年京都大学文学研究科博士課程単位取得退学。2001年メリーランド大学よりPh.D.(philosophy)取得。名古屋大学情報科学研究科助教授などを経て、京都大学文学研究科准教授
村井俊哉[ムライトシヤ]
1966年生まれ。1997年京都大学医学研究科博士課程修了、医学博士号取得。マックスプランク認知神経科学研究所、京都大学医学部附属病院助手などを経て、京都大学医学研究科精神医学教室教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ソーシャ
2
おいしいものとおいしいものの組み合わせなんだからおいしくないはずがないじゃないといった感じの本。英米系哲学の視点から、精神医学の科学性を論じているのですが、論旨が明快で科学哲学や心の哲学の概念の説明も初学者にも理解できるように丁寧になされています。明快なだけに著者の主張の問題点にも気づきやすいのですが、「精神疾患は実在するのか」「精神疾患を生物学に還元して説明することは可能なのか」などの疑問を抱いたことがある人はもちろん、「医学は科学哲学の視点からどのように見えるのか」に興味がある人にもおすすめします。2017/03/21
PukaPuka
2
先日の日仏会館でのボリス先生のお話で、デカルトの二元論が諸悪の根源、といった話があったのですが、本書では、訳者解説でも指摘されていますが、筆者は、どんな先鋭的な神経科学的発見も二元論が誤りであることを示すものでない、と言っています。精神科の臨床医には退屈な議論が多い本書で、この箇所は光って見えます。デカルトといえばJe pense, donc je suisしか思い浮かばない私としては、まずデカルトをちょっと読まなきゃ、というところでしょうか(いつになるやら)。2015/11/08
アン
2
読み応えある本だった。私が抱いていた精神科の「胡散臭さ」が解き明かされ、不確定要素は内科に比べて多いけれど精神科に進むのも良いかもしれないと思えた。2015/09/13
くじらい
1
すごくいい本です。2024/11/05
トクナガ
1
精神医学に関してはあまり知らないが科学哲学には結構興味があるので読んでみた。そのあたりの入門書よりも科学哲学に関する内容が豊富で非常に面白かった。2021/08/13
-
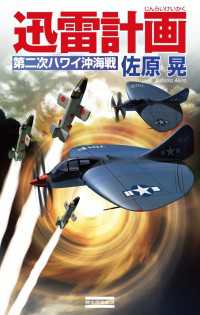
- 電子書籍
- 迅雷計画 第二次ハワイ沖海戦 歴史群像…